製薬マーケティング現場が直面する「3つの壁」とその突破口|2025 Veeva Japan Commercial & Medical Summit
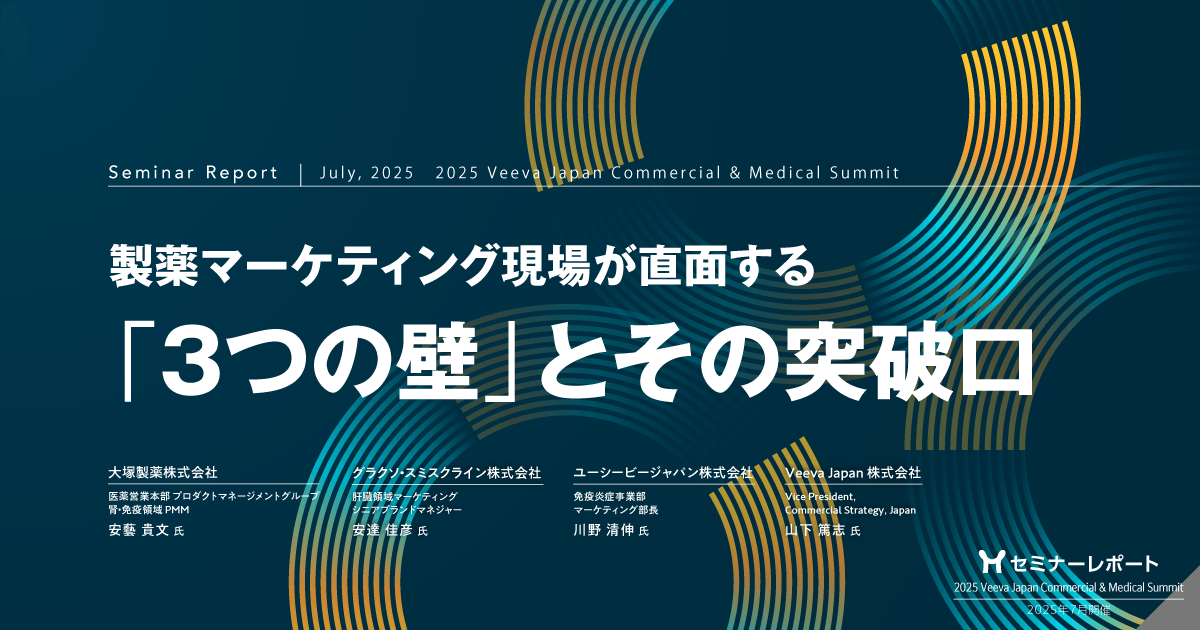
デジタル化やオムニチャネルの活用が当たり前になった今も、製薬マーケティングは依然として「顧客理解」「情報提供」「能力・組織」という3つの壁に直面しています。ターゲットの精度やデータの信頼性、限られたリソースの中でのコンテンツ設計、部門間のサイロ化など、現場と本社の双方で解決すべき課題は山積みです。
2025年7月に開催された2025 Veeva Japan Commercial & Medical Summitでは、製薬企業3社から、マーケティング責任者が登壇。Veeva Japan山下氏によるモデレートのもと、3つの壁の実態と、それを乗り越えるための現実的なアプローチが議論されました。
本稿では、その議論を整理し、今後の製薬マーケティング戦略に活かせる実務的なヒントを提示します。
■パネリスト
大塚製薬株式会社
医薬営業本部 プロダクトマネージメントグループ 腎・免疫領域 PMM
安藝 貴文氏
グラクソ・スミスクライン株式会社
肝臓領域マーケティング シニアブランドマネジャー
安達 佳彦氏
ユーシービージャパン株式会社
免疫炎症事業部 マーケティング部長
川野 清伸氏
■モデレーター
Veeva Japan 株式会社
Vice President, Commercial Strategy, Japan
山下 篤志氏
顧客理解の壁:患者視点を持ち続けるには

医師へのアクセスが制限されるなか、精度の高い顧客理解とターゲティングは製薬マーケティングの基盤となるテーマです。しかし実際には、ターゲットの定義やデータの信頼性、さらには時間の経過とともに組織が会社視点に傾いてしまうことなど、複数の壁が存在します。
顧客の再定義から始まる戦略構築
大塚製薬の安藝氏は、この壁を乗り越える第一歩として「顧客の再定義」を挙げます。ブランドマネージャーの視点では、患者・医師・MR・研究開発という複数の顧客像が存在しますが、中でも患者を起点にペイシェントジャーニーを描くことが不可欠です。診断から治療開始までの動線を可視化することで、医師へのターゲティング戦略も精緻化されます。
医師に実際にアプローチしていく際には、MR活動は生活習慣病ではShare of Voice型、希少疾患ではOne Patient Detailing型のいずれかに大別されます。希少疾患領域ではOne Patient Detailing型の活動が有効ですが、MRが全領域を網羅するのは容易ではありません。そこで同社では本社にオムニチャネルマーケター(OCM)を配置し、支店単位で戦略会議を行いながらMRと共同で面談を重ねる体制を構築しています。
「MRはターゲットを広げたがる傾向があり、関係性があるような面談しやすい医師ばかりにアプローチして成果につながらない場合もある」と安藝氏。そのため、外部データを活用しつつ本社と現場でキャッチボールを行い、精度を高めながらターゲットを絞り込むことが重要だと強調しました。
さらに、顧客視点を損なわないための工夫として、大塚製薬では「ペイシェントボイスデー」を設け、患者の声を直接ヒアリング。 それを基に戦略を再評価し、常に患者中心の視点に立ち返る仕組みを整えています。
情報提供の壁:効果的なコンテンツ戦略の構築
ターゲット精度を高め、医師へのアクセスに成功しても、そこで終わりではありません。重要なのは、その瞬間に「最適なコンテンツ」を届けきることです。日々大量の情報にさらされる医師にとって、ポイントが絞られないメッセージは容易に埋もれてしまいます。
グラクソ・スミスクラインの安達氏は、個別化の要望すべてに応えるとコンテンツが過剰に増え、多くが消費されずに終わるというジレンマを指摘します。医師が信頼する情報源は今も昔も変わらずMRやPeer to Peerであり、その数は限られています。同氏は、以下のような医師がよくアクセスする情報を、簡潔かつ的確に届けることが大前提だと強調しました。
- エビデンスに基づく診療ガイドライン・臨床試験データの詳細情報
- 新薬情報と最新の治療ガイドライン
- 医師の学習を支援する講演会・Webセミナー
- 患者指導のためのサポートツール
【関連記事】
#1 製薬コンテンツ運用を成功に導く道筋とは|AI時代のコンテンツマネジメント法
製薬マーケにおけるパーソナライゼーションの重要性と進め方
フェーズ・領域に応じたチャネル最適化と“目的志向”の情報提供
製品のフェーズや領域によって有効なチャネル設計は異なります。例えば、プライマリケアではマルチチャネル型、スペシャリティではOne to One型が基本です。
適切なチャネル設計を見極めるために、「ローンチ直後で精度向上に余地がある段階では広めのアプローチから入り、データをもとに絞り込むプロセスが必要」 と安達氏。ROIの低いチャネルは売上が伸びていても整理するなど、チャネルポートフォリオの見直しも欠かせません。
一方で、パーソナライズやOne to Oneにも限界はあります。製薬業界ではデジタル活用の課題感が10年以上大きく変わっていません。そのため、医師が本当に必要とする質の高いコンテンツを提供し、使われない資材を減らすことこそが重要です。単なる「How」にとらわれず、情報提供の目的を明確にする姿勢が求められます。
能力・組織の壁:顧客体験を統合管理するために

製薬業界のエンゲージメントモデルは、MRが唯一の接点であった時代から、2010年代のマルチチャネル、そしてオムニチャネルの構想へと移ってきました。しかし、ユーシービージャパンの川野氏は「生成AIの時代に入った今でも、現実はマルチチャネルからオムニチャネルへの進化の過渡期である」と指摘します。
「業界の有識者と議論すると、オムニチャネルに関する議論は、10年前から変わっておらず、製薬業界が一丸となって取り組む必要性があります。加えて、製薬業界では、オムニチャネルは必ずしも必要ではなく、マルチチャネルやシングルチャネルでも目的を果たすことが大切なのです」と川野氏。
背景には、コロナ禍を経て新設された部門ごとのサイロ化とデジタルスキル・ケイパビリティのギャップがあります。メガファーマを中心に、チャネル管理が縦割りとなり、顧客起点で統合的に体験を設計することが難しいのが実情です。川野氏は、全社で統合管理できる体制を理想としつつ、それが難しければアジャイル的に小さく試し、改善を重ねるアプローチが必要だと強調します。
さらに、企業内の「製品・会社中心」の考え方から「顧客中心」への価値観転換も欠かせません。顧客ニーズを起点に学び続ける文化を醸成し、外部とのパートナーシップも積極的に取り入れることで、自社だけでは得られない知見やリソースを活用できます。
【関連記事】
#2 オムニチャネルの定義と位置づけを整理する|製薬マーケ部門担当者と考えるオムニチャネル時代の包括的なブランドプラン
製薬業界の“当たり前”を問い直す-真のオムニチャネル実現に向けた参加型ワークショップ|MDMD2025 Summerレポート
マーケターが変革を牽引するための視点と備え
マーケターの役割は、これまで以上に広がりを求められています。限られた予算や権限の中でも、部門間の壁を越えて顧客体験を統合していくリーダーシップが欠かせません。安達氏は、この変化を「経営課題であっても、現場のマーケターが主導できる余地は大きい」と捉えています。
一方で、デジタルを専門部門に委ねてしまいがちな現状に対し、川野氏は「自らの役割のスコープを広げる姿勢」が必要だと指摘。山下氏も、AIの導入は業務の棚卸しと役割の再定義を促すため、組織変革の契機になり得ると見ています。
安藝氏は、アフターコロナのMR回帰の動きを踏まえつつも、医師の世代交代やデジタル化の進展を考えれば「必要になれば即座にオムニチャネルに切り替えられる状態」を備えておくことが不可欠だと強調しました。
未来のマーケティングエコシステム構築に向けて
患者視点の精緻なターゲティング、質の高い情報提供、部門間の連携による顧客体験の統合管理は、変化の激しい市場で成果を上げ続けるための基盤です。マルチチャネルとオムニチャネルを目的に応じて使い分け、現場・本社・外部パートナーが知見を共有し合うことで、真に顧客起点のエコシステム構築を実現する土台となるでしょう。
【関連記事】
#1「顧客理解の限界」をどう越える?データ活用の現状と課題の把握方法|データ連携で導く真の顧客価値
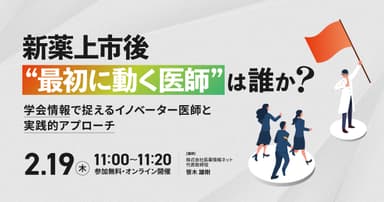





.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)


