「会えるMR」から「選ばれるMR」へ。現場の変化に本社はどう応えるべきか?|2025 Veeva Japan Commercial & Medical Summit
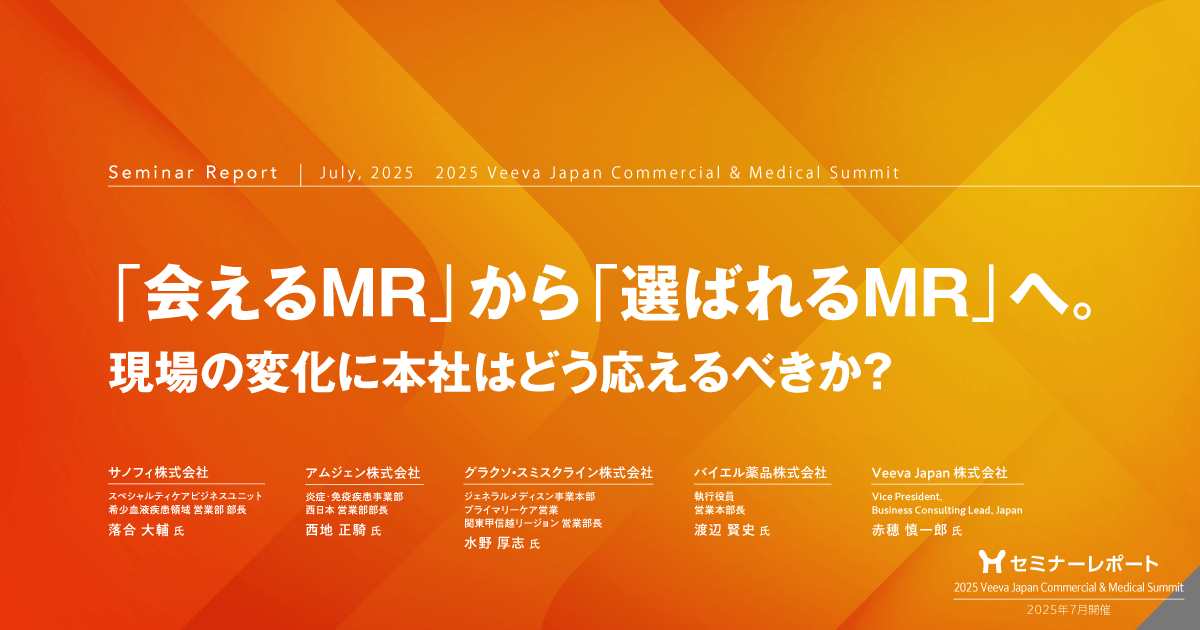
AIの活用が加速する中、さまざまな業界で「人にしかできない価値」が問われるようになっています。製薬業界においても例外ではなく、医師との関係構築を担うMRの役割や価値を見直す動きが強まっています。
2025年7月開催の2025 Veeva Japan Commercial & Medical Summitでは、製薬企業4社のセールスリーダーが登壇し、MRに今求められる力と、現場でのAI活用、評価・育成のあり方について語りました。本稿では、現場の変化から本社が読み取るべきヒントを抽出し、戦略や支援設計に生かすための視座を提案します。
■パネリスト
サノフィ株式会社
スペシャルティケアビジネスユニット 希少血液疾患領域 営業部 部長
落合 大輔 氏
アムジェン株式会社
炎症・免疫疾患事業部 西日本 営業部部長
西地 正騎 氏
グラクソ・スミスクライン株式会社
ジェネラルメディスン事業本部 プライマリーケア営業 関東甲信越リージョン 営業部長
水野 厚志 氏
バイエル薬品株式会社
執行役員 営業本部長
渡辺 賢史 氏
■モデレーター
Veeva Japan 株式会社
Vice President, Business Consulting Lead, Japan
赤穂 慎一郎 氏
MRに求められるのは「価値を届ける力」

COVID-19の流行を経て、MRを取り巻く環境は大きく変化しました。医療現場における面会制限の強化により、一時は「MRはデジタルに置き換わるのではないか」との声も聞かれるほどでした。
しかし現在、製薬マーケティングにおいては「リアル回帰」の傾向が強まっています。実際、本講演では、「医師もFace to Faceを再び求めるようになっている」という現場の声が登壇者から複数あがりました。
とはいえ、すべてのMRが同じように歓迎されるわけではありません。医師が「会いたい」と思うのは、自らの診療に資する「価値のある情報」を届けてくれる存在です。
登壇者の一人であるサノフィの落合氏は、MRが医師に選ばれ続けるためには、医師が直面する臨床課題を的確に捉えた上で、その解決に資する情報を提供することが重要だと指摘しました。特に希少疾患のようにターゲットが明確な領域では、患者とのShared Decision Making(SDM)も重要性を増しています。患者の背景を理解し、医師と患者双方にとって意味のある対話を促すMRの存在が求められているのです。
グラクソ・スミスクラインの水野氏は「ここ3年で“医師のニーズを深く理解し、それに合わせた戦略的に情報を提供できるMR”が増えた」と現場の変化を語ります。現在は、医師の関心に即した情報を逆算して設計する姿勢が求められており、水野氏はその一例として、面談後に医師の要望に応じた情報をメールで提供することや、Web講演会を通じて関心を継続させる工夫を挙げました。こうした「選ばれる情報設計」への転換が進んでいます。
このような現場の変化は、マーケティング部門にとって捉えておくべき要素です。面会の「回数」や「資材の使用有無」といった表層的なKPIだけでは、MRの価値は測れません。「医師に情報が届いたか、医師の行動変容が起きたか」という視点を持つことが、今後のチャネル設計や支援策を考えるうえで不可欠だと考えられます。
【関連記事】
情報から「意味」へ。製薬マーケティングの新たな役割|MDMD2025 Summerレポート
働き方改革で変わった、医師の情報収集の実情|学会・リアル講演会・MR面談の時間減
AI時代の現場支援とは
製薬企業でも積極的にAIの導入が進む中で、現場支援の在り方も変わりつつあります。業務効率化や省力化が主目的だったAI活用は、いまやMR一人ひとりの行動の質を高めるための支援へと軸足を移しているのです。
各社が取り組むAIを活用した現場支援策
AIを活用した現場支援策について、各社の取り組みが共有されました。例えばHCP調査データの活用や面談記録(コールノート)の共有を通じて、医師ごとの最適な情報提供のタイミングやチャネル選定の精度を向上させていたり、特定の剤形が出た際の次のアクションまでをAIが示す取り組みが進んでいたりなど、医師の行動を予測した先回りのアプローチが可能になりつつあります。
また、MR教育では、医師役のAIとのロールプレイを取り入れた研修が注目され始めています。仮想の医師と会話を重ねて実践的なコミュニケーション訓練ができるという特徴から、導入が進んでいる企業もあるようです。
一方で、どれほど高度な機能を備えたツールであっても、MR自身が「使いたい」と感じるかどうかが運用の成否を大きく左右します。
バイエル薬品の渡辺氏は、システム提供側と現場の間にある「なぜ当初の想定より使ってくれないのか」というツール使用に対する課題に触れ、本社と現場の相互理解と信頼構築の必要性を指摘。現場から提供側に「こんなことを現場では実際に取り組んでいる」、提供側から現場に「こういう工夫をしている」といった事例を互いに開示しコミュニケーションを取ることが、認識ギャップを埋める一歩になると提案します。
アムジェンの西地氏も、「このツールを使うと、どう患者の笑顔につながるのか」という「使いたくなる理由」を本社側が提示することの重要性を強調しています。現場の納得感と意味づけがなければ、AIは真の支援ツールにはなり得ません。
【関連記事】
塩野義製薬の生成AI活用戦略-汎用的ツールでのスモールスタートが鍵
製薬マーケターの7割が活用。人間×生成AIの成果を高めるポイントは
現場とともにアップデートする組織へ

AIやツールが進化する今、MRによる情報提供活動で問われるのは、情報を「届けたか」ではなく「届いたか」です。医師の行動変容やフィードバックを起点にした評価視点が、現場支援の前提になりつつあります。
こうした変化を支えるには、MR個人の努力だけでなく、組織としてのアップデートが必要です。アムジェンの西地氏は、「使わせる」ではなく「やらせてあげる」環境づくりこそがリーダーの役割だと語り、挑戦を称賛する姿勢の重要性を強調しました。
また、同氏はMRに求められるスキルセットとして「問いを立てる力」「情報を解釈する力」「まずやってみる力」の3つを挙げています。
「問いを立てる力」は、AIから尖った回答を引き出すためのプロンプトの設計や、医師に臨床課題を気づかせるような対話を設計する力を指します。「情報を解釈する力」は、手元にあるデータや医師の言葉から示唆を導き出す力、そして「まずやってみる力」は、仮説をもとに行動し、試行錯誤から学ぶ姿勢を意味します。
これらの行動を現場で促すためにも、本社は現場との対話やフィードバックを通じて、柔軟な仕組みや支援のあり方を模索していく必要があるでしょう。本社こそが、現場の変化を後押しするアップデートの起点となれるのです。
【関連記事】
医師・患者向け施策がつながる、「臨床課題」起点の情報提供戦略|MDMD2025 Summerレポート
【そのほかの関連コンテンツを読む】

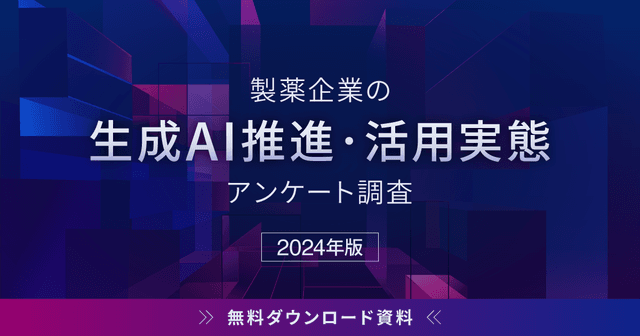

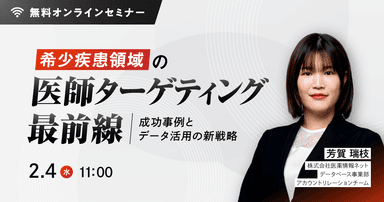




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)


