#2 MRやMSLが医師と対等なパートナーになるために必要なこと|Dr.心拍の「製薬本社にちょっと言いたい」
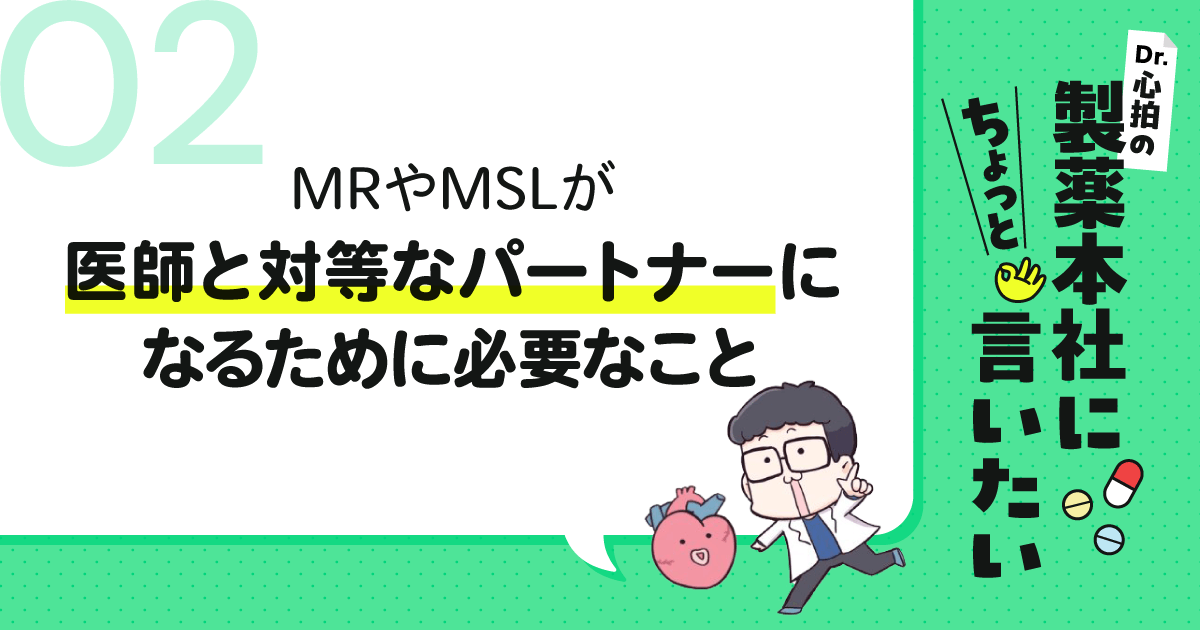
こんにちは。勤務医として臨床に携わりながら、専門的知見を生かしてさまざまなヘルスケア企業とお仕事をしております、Dr.心拍と申します。普段医療メディアやSNSで発信をしております。臨床医が本音で語る連載シリーズとして、製薬企業の情報提供や、医療現場との関係性について感じていることをお話しさせていただきます。
前回は医師以外の多職種へのアプローチについてお話ししました。
今回は、MRと医師の関係性としてDr.心拍が想うことをお話しします。前回の記事の冒頭でも触れたとおり、MRから何か新規性、独自性のある情報を得るというのは、昨今のレギュレーションを考慮しても難しく、また情報の速報性としてもSNSなどの方が早い現実があり難しいのが現状です。
そして、情報を提供するのではなく情報を我々から「無償で」得ようとしているアポイントにそもそも無理があるというのは前回の記事に記載した通りになります。
そのような背景をMRも理解しているからこそ、積極的に動けず、下手に出てしまうのも無理はありません。
しかしながら本来であればMRも医師も同じ方向を向き、対等な目線でディスカッションできるのが良いのではないでしょうか。我々も製薬企業が開発した薬剤がなければ患者さんに良い医療を提供できません。薬あっての治療ですから。
そういう視点で考えてみると、MRがまさに薬のエキスパートになりうるならばその存在価値は貴重なものとなるのではないでしょうか。
現実はそう甘くはありません。昨今のMRはどんどん人員が減らされています。そして、私が医師になった頃と比較して、自社の薬に対する理解が乏しくなってきたなと感じています。アポイントをとること、講演会に参加する署名をもらうこと、メールの返信率、自社オウンドメディアへの登録などが目的化され過ぎていて、いったい何をしたらよいのかわからなくなっているのではないでしょうか。
また、MSLの方は中立的立場での情報提供が必要になります。特に専門的知識をせっかくお持ちなのですからぜひそれを役立てられるような関わりをしていただきたいと思います。
それでは、MRやMSLが医師と対等なパートナーとなるにはどうしたら良いのでしょうか?
1.自社製剤・周辺薬剤についてしっかり把握しておく
まず前提としてしっかり知識を習得すること。自社の薬剤はもちろん、周辺薬剤知識も含めた網羅的な知識を習得する必要があります。自社の薬剤については決して持ち帰らなくても対応できるほど圧倒的に理解しておく。ここが結構肝だったりします。
我々は、多くの疾患と患者さんに対応しているなか、アポイントの時間を捻出しています。だからこそ、MRはせめて自社製品くらい誰よりも詳しいと自負できるくらい把握しておいてくれよと思ってしまうのです。質問した時に「お調べしてまたアポイントをお願いします」と言われると、もう2度目はないんだよと萎えてしまいます。
2.実臨床の現場を知る
また、もっと臨床現場を知ることです。実臨床に即して、実際医師が患者さんや患者家族とどのように接しているか、どんなインフォームドコンセント(IC)をしているかなどの実情を理解できるような研修を、医師と一緒に取り組むなどが対策として可能だと思います。その際、医師と患者、患者家族との関係性だけでなく、多職種連携も含めた把握が重要です。
3.副作用に迅速な対応ができるシステム作り
また、非常に重要な知識としては副作用管理です。特に新薬については使用経験が少なく、ドラッグインフォメーション(DI)に記載がない副作用などが出現することもあり、自社での情報が最新となる可能性があります。したがって、実際に副作用かもしれないとして相談された際に、迅速に対応できるシステム作りを構築しておく必要があります。
外来などで診療に当たっている医師の立場からすると、実際副作用が発現したときには目の前の患者さんに対応する必要があるので瞬時に対応できるのが理想です。外来は待ってくれないからです。1人の診察にかけられる時間は数分程度しかないのです。そのような実情を理解した対応ができるようにしてほしいです。
最後に、今のレギュレーションの厳しさは過去のディオバン事件が発端となっているのだと思いますが、現代の製薬企業の皆さんは正しいことをやっているのだからもっと胸を張ってほしい。今のMRに不正をして売りたいなんて方はいないでしょう。正しいと思う行動をすればよいと思います。
とはいえ、このような意識改革はMR個人の力だけでは改革できないことを知っています。決めるのは本社ですから。だからこそ私も最近は本社向けイベントへ登壇し、改革を訴えています。
興味がある製薬企業の方はぜひお問い合わせください。
さて、今回はMRが医師と対等なパートナーとなるためにはという内容をお伝えしました。医療はチームで行われるべきですから、MRも含めた製薬企業もその一員であることを常に意識してほしいと思います。




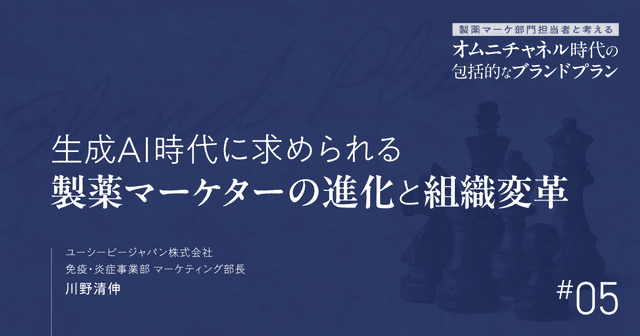
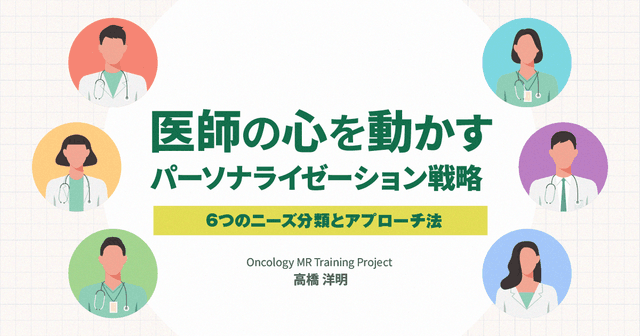
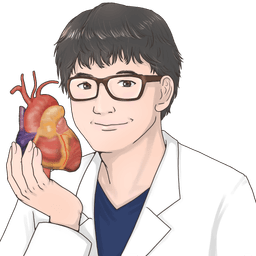





.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



