第4回 「インサイト」とは何か-情報の点をつなぎ、仮説を紡ぐ力|製薬マーケ部門担当者と考えるオムニチャネル時代の包括的なブランドプラン
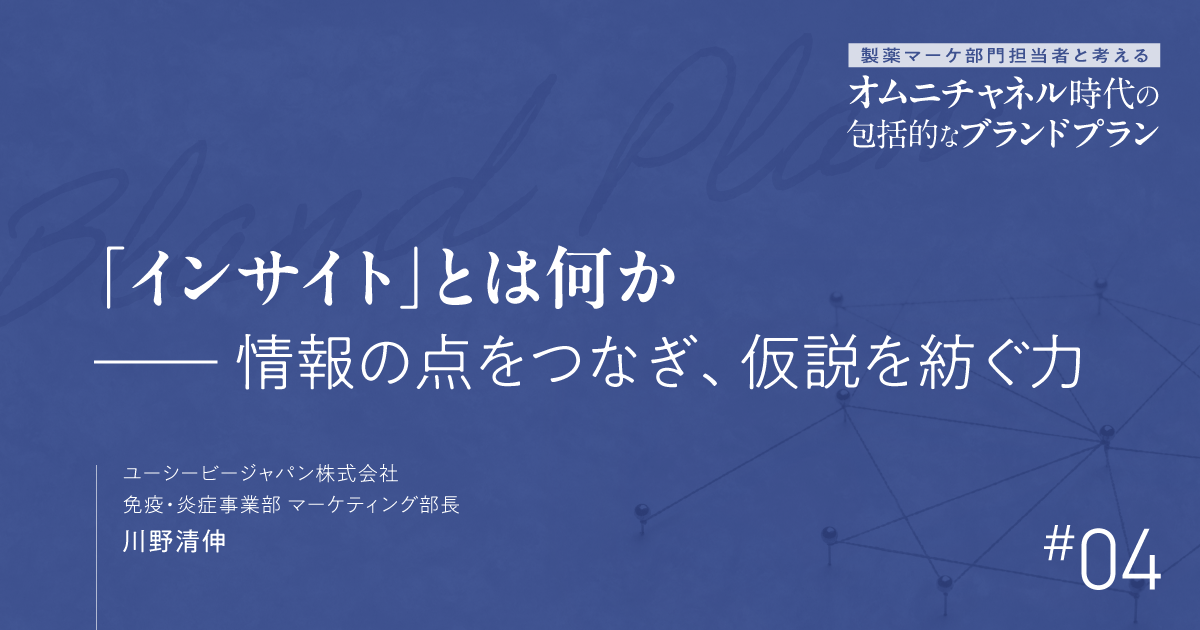
コラム第3回にて「インサイト」の重要性について触れました。偶然ですが「マーケティング担当者の立場からのインサイト」について講演する機会があり、頭の整理をする良いきっかけになりました。正直なところ、長らくマーケティング分野に携わりながら、インサイトについて十分に理解を深めてきませんでした。自戒の念も込めて、このタイミングでインサイトについて私見を踏まえて整理しておきたいと思います。
マーケティングにおけるインサイトは非常に重要なものです。今回は我々がよく耳にするインサイトについて、仮想の話をベースに私なりの見解・解釈を述べてみたいと思います。
(ユーシービージャパン株式会社 免疫・炎症事業部 マーケティング部長 川野清伸)
※記載内容は著者個人の見解であり、著者が所属する企業の見解や方針を代弁・表明するものではありません。また、記載内容は著者が所属する企業の状況に関するものではなく、あくまで著者の認識における製薬企業一般の話であることをご承知おきください。
ある日、会議室で「この施策は顧客インサイトに基づいています」と語る声を聞きました。資料にはプライマリーリサーチや各種データが並び、確かに情報は豊富でした。しかし、私はふと疑問に思いました。「これは本当に“インサイト”なのだろうか?」
「インサイト」という言葉は日常的に広く使われています。しかし、その定義を明確に理解し、使いこなしている人は意外と少ないのかもしれません。多くの場合、インサイトは単なる情報やデータと混同されているからです。それではインサイトとは一体、何なのでしょうか?
インサイトとは?
Insightという単語は英語のin(中に)とsight(見ること、視野)という2つの語から構成されています。また、日本語では「洞察」と訳されます。
つまり、「物事の内側を見ること」「本質を見ること」と解釈できます。マーケティング分野においては「消費者の“潜在的”なニーズや行動の背景を理解すること」、心理学の分野では「自己や他者の行動・感情の根本的な理解」、一般的なビジネスの分野では「データや経験から得られる深い理解や気づき」などと理解されていることが多いのではないかと思います。
それでは、インサイトについて私の経験を通しての解釈を述べていきたいと思います。
インサイトと「仮説」
インサイトから導き出された何かは「仮説」なのではないかと思います。例えば、ある製品が特定の層に支持されているというデータがあったとしても、その理由は明示されていません。そこに「なぜ?」と問いを立て、背景にある感情や価値観を探ることで、初めてインサイトが生まれます。
このプロセスは、論理学でいう「アブダクション(仮説的推論)」に似ています。観察された現象に対して、最も合理的な説明を仮説として構築する思考法です。
つまり、インサイトとは、単純に情報を受け取るだけではなく、情報の点と点をつなぎ、意味を見出す創造的な行為といえるのではないでしょうか。
Actionableであることの重要性
実務家として、インサイトが「行動につながる(Actionable)」ものであることは極めて重要なポイントです。単なる気づきではなく、戦略や施策に転換できる洞察でなければ意味がありません。具体的なアイデアに昇華され、アクションに繋がることが必要不可欠なのです。インサイトは、それらが活用された結果、顧客の行動を変える力を持ち、企業の意思決定を支える羅針盤となる重要な概念だと考えています。
インサイトを抽出する力をどう育てるか?
では、どうすればインサイトを抽出する力を養えるのでしょうか。私の経験から以下の3つの習慣と姿勢をご紹介します。
1. 問い続ける姿勢
ありのままの情報を、ただ受け取るだけでは本質を見誤ることがあります。表面的なデータに満足せず、「なぜ?」と問い続けることが大切です。背景にある感情や文脈を探る癖をつけましょう。
2. 発信と対話
思考を言語化し、他者と壁打ちすることで、オートクライン効果※により思考が深化します。さらに、異なる視点との対話はインサイトの精度を高めます。
※オートクライン効果:自分で発言した内容を自分で聞くことによって、自分の考えや感じていたことに気付きやすくなること
3. 顧客起点(人間理解)
顧客の立場に立ち、感情に寄り添う共感力が極めて重要です。これは、デザイン思考の根幹でもあり、共感を起点に顧客の「本当の課題」を見つけることができます。
これらを実際に行動へ移すことは決して容易ではありません。だからこそ、マーケティング部門を担うマネジメント層が、常に自らに問いかけ続ける姿勢こそが、人材育成や組織文化の醸成に繋がるのだと強く感じています。
マーケティング部門は日々多忙を極め、時には業務の中で妥協したくなる自分自身との葛藤も避けられません。そのような時こそ、マネージャーとしての自覚を持ち、この想いを胸に刻み続けたいと考えています。
コモディティ化の時代にこそ、インサイトが必要
製薬業界のビジネスはプライマリーケアから希少疾患領域へとシフトしてきました。希少疾患領域のビジネスモデルの根幹は「高薬価」と「収益性(販管費などが抑えられることで高い利益が得られる)」だったと私は考えています。
一方、多くの製薬企業が希少疾患領域にフォーカスしたため、一部では類似した薬剤が多数登場し、レッドオーシャン化しています。かつては治療薬が存在しないという未充足ニーズに応えることで、自然と処方が伸びる状況がありました。しかし現在のように選択肢が増えた環境では、顧客が自覚できていないこと、つまりインサイトが差別化のカギを握るのだと私は考えています。
さらに、規制の強化や市場の成熟により、戦略の自由度が狭まっている今だからこそ、どこにインサイトがあるのかを突き詰める力が求められているのではないでしょうか。これは戦略面にとどまらず、戦術面でも同様です。限られた選択肢の中で顧客の心に響く施策を打つには、深い洞察が不可欠でしょう。
最後に──「なぜ?」を問い続けること
インサイトは、見えないものを見ようとする姿勢の中に宿ります。日々の業務の中で、「なぜ?」という問いを忘れず、情報の背後にある物語を探ること。それが、マーケターとしての本質的な力を育てる道だと私は信じています。

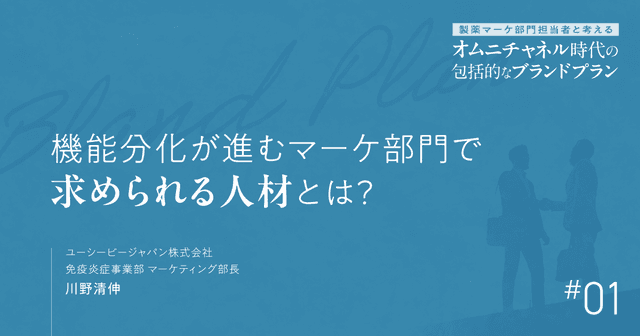


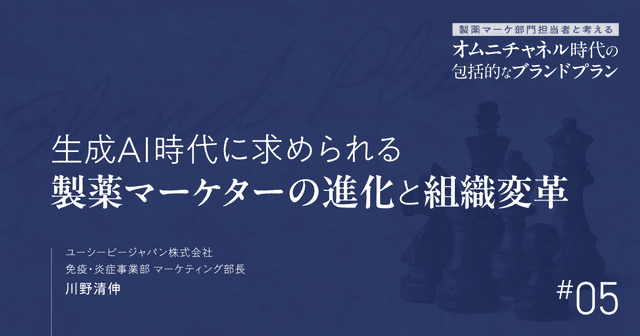
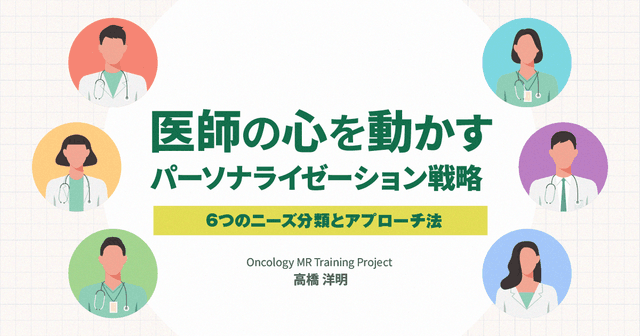

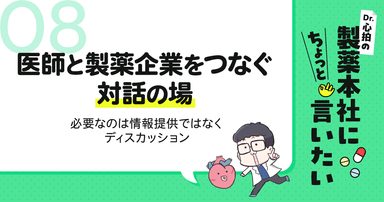
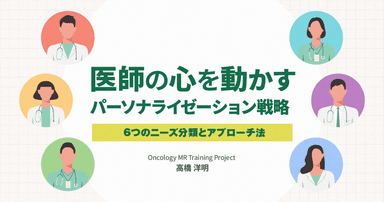



.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



