医師の心を動かすパーソナライゼーション戦略-6つのニーズ分類とアプローチ法
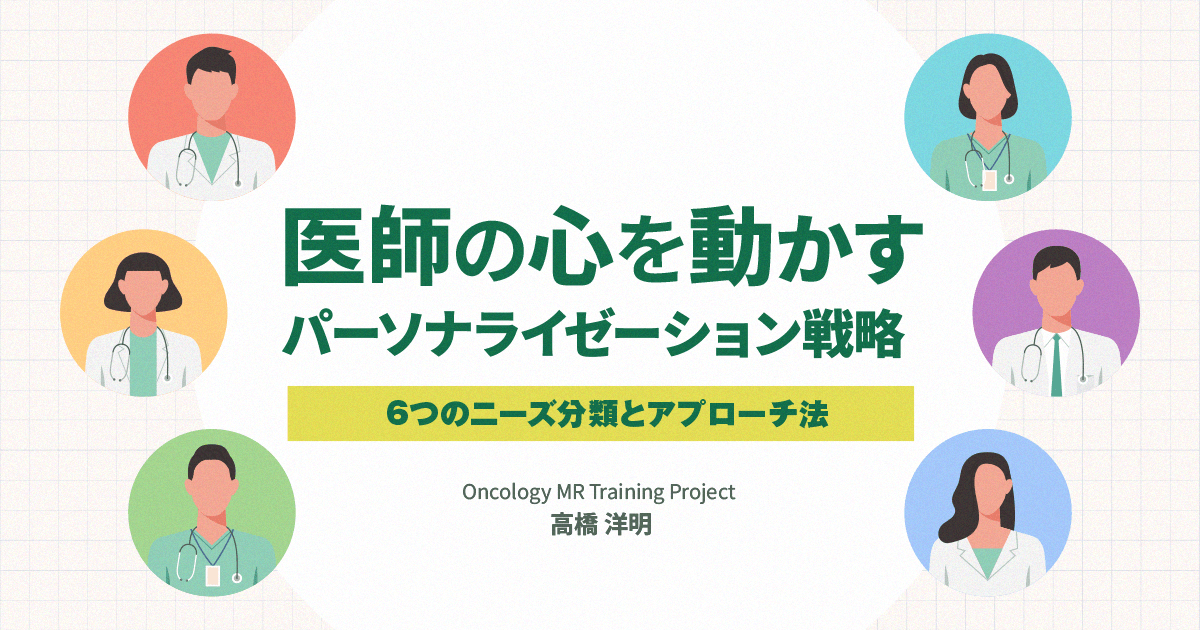
医師セグメントの最適化は、施策の成否に重要な影響を及ぼします。Medinewでは過去に、カスタマージャーニーや行動データに基づくセグメンテーションの手法を紹介しました。今回は、医師を「態度・価値観」でセグメントし、マーケティングに落とし込むための実務的手法を示します。医師を臨床のエビデンス、臨床、革新志向、予防志向、患者中心、経済性重視の6つに分類した上で、それぞれに最適化したアプローチを解説します。
(Oncology MR Training Project 高橋洋明)
- 医師セグメンテーションの3つのアプローチ
- 医師のニーズに基づく6つのセグメンテーション
- 1.エビデンス重視型(科学的根拠に基づく)
- 2.臨床重視型(患者事例重視)
- 3.新規治療法重視型(革新型)
- 4.予防型(治療よりも予防に関心)
- 5.患者中心型(患者とのコミュニケーション重視)
- 6.経済性重視型(コスト効果重視)
- セグメント別パーソナライゼーションの実行方法
- 1.エビデンス重視型の医師へのアプローチ
- 2.臨床重視型の医師へのアプローチ
- 3.新規治療法重視型の医師へのアプローチ
- 4.予防型の医師へのアプローチ
- 5.患者中心型の医師へのアプローチ
- 6.経済性重視型の医師へのアプローチ
- パーソナライゼーション施策実行時の重要なポイント
- データ基盤をつくる
- コンテンツのモジュール化
- MR/MSLを最適化
- コンプライアンスと個人情報保護
- KPI設計と実施後の効果測定
- 医師のニーズに基づくパーソナライゼーション戦略
医師セグメンテーションの3つのアプローチ
Medinewの記事では、過去に医師のセグメンテーションに有効な3つの切り口を紹介しています。
- カスタマージャーニーに沿ったセグメント
- 行動・接触チャネルベースのセグメント
- 態度・価値観ベースのセグメント
①と②のアプローチはもちろん有効ですし、多くの製薬企業で活用されています。とはいえ、「施策の成功確率をさらに高めたい」「そのためにカスタマージャーニーや行動データ以外にセグメンテーションできないか」と悩むプロダクトマネージャーもおられます。
そこで本記事では、③の「態度・価値観ベースのセグメント」にフォーカスして解説します。これは言い換えれば、医師をニーズの塊にセグメンテーションすることです。
医師が何を重視し、どのような情報を求めているのかという本質的な価値観に基づいてアプローチすることで、より高い成果が期待できます。
▼参考記事:製薬マーケにおけるパーソナライゼーションの重要性と進め方
https://www.medinew.jp/articles/marketing/marketing-strategy/personalization
医師のニーズに基づく6つのセグメンテーション
製薬業界のマーケティングで最もリターンが出やすいのは、医師の「価値観(態度)」に合わせた情報提供です。ここでは、臨床現場で観察される代表的な6つのプロファイルを以下に紹介します。
自社のターゲット医師がどのタイプに該当するかを見極めることで、より効果的なコミュニケーション戦略を立案できます。各タイプの特徴を理解し、医師のニーズに的確に応えるアプローチを設計していきましょう。
- エビデンス重視型(科学的根拠に基づく)
- 臨床重視型(患者事例重視)
- 新規治療法重視型(革新型)
- 予防型(治療ではなく予防に関心)
- 患者中心型(患者とのコミュニケーション重視)
- 経済性重視型(コスト効果重視)
1.エビデンス重視型(科学的根拠に基づく)
特徴:治療法の選択において科学的根拠を最も重視し治療法や薬剤を選定するタイプ。
ニーズ:治療選択の根拠となる科学的な証拠を求める傾向があり、以下のような信頼性の高いデータに関心を示す。
- 最新の臨床試験データ
- エビデンス(無作為化試験(RCT)、メタ解析の結果など)
- ガイドラインの変化
- 堅牢なデータ
見られる行動:日常的に情報収集を欠かさない医師が多く、以下のような行動が特徴的。
- 主要学会参加
- 査読論文の購読
- エビデンス指向の学術セミナー参加など
2.臨床重視型(患者事例重視)
特徴:日常診療の現場で得られる経験や実践的知見を重視。学術的な証拠よりも実践的なアプローチを好む。
ニーズ:現場で即活用できる以下のような実践的な情報を求める。
- 実際の患者に基づいた症例報告
- 治療法の実際の効果
- 日常診療での意思決定に直結する情報
見られる行動:実際の臨床現場での効果や使いやすさを重視する行動が見られる。
- 患者の経過を重視
- 実践的How Toを好む傾向
3.新規治療法重視型(革新型)
特徴:常に最新の治療法や技術に関心を持ち、医療の進歩を積極的に取り入れようとするタイプ。変化を恐れず、臨床への応用意欲が高い傾向にある。
ニーズ:最新の治療法や治療薬の情報、技術・デバイス、治療アルゴリズム、特に新薬の適応症や臨床結果に興味を持つ。
見られる行動:新しいものへの積極的な取り組み姿勢をもつ。
- 臨床試験への積極的参加・新技術の導入に前向きな姿勢
4.予防型(治療よりも予防に関心)
特徴:治療よりも予防に重点を置き、疾患の発症を未然に防ぐことを重視。
ニーズ:治療薬よりも予防策や健康管理、予防医療の手法に関心が高い。
- 疾患予防や予防介入
- スクリーニング、早期発見
- 生活習慣改善に関するツールや介入デザインに関連する情報
見られる行動:公衆衛生的観点を診療に取り入れる傾向。
5.患者中心型(患者とのコミュニケーション重視)
特徴:診療において患者との信頼関係を重視し、患者理解とコミュニケーションを軸に医療を実践するタイプ。
ニーズ:以下の項目に関心を持ち患者に寄り添った医療の提供を心がける。
- 患者とのコミュニケーションや患者教育
- 服薬アドヒアランス支援
- 説明資料やツール
見られる行動:患者との対話を重視し、説明時間を確保する傾向。
6.経済性重視型(コスト効果重視)
特徴:限られた医療資源の中で最も効率的な治療を追求するタイプ。
ニーズ:経済性を重要な判断基準とし、治療法の費用対効果やコスト効率の良い治療法を選ぶために以下のような情報を求める。
- 医療のコストや薬剤のコストパフォーマンスといった費用対効果
- 保険償還や院内調達に関する経済的な効率・数字
見られる行動:治療効果だけでなく、以下のような経済的側面も含めた総合的な判断を行う傾向。
- コスト比較
- ガイドライン上の経済性評価を参照
セグメント別パーソナライゼーションの実行方法
医師を6つのタイプに分類したら、次はそれぞれに最適化されたアプローチを設計します。同じ製品情報でも、医師のタイプによって響くメッセージ、効果的なチャネル、適切なコミュニケーション方法は大きく異なります。
本章では、各プロファイルに対するコンテンツの種類、最適チャネル、実行の具体的手法の事例をお示しいたします。
製薬企業各社におけるプロモーションのレギュレーションも十分考慮して、「このやり方だと当社では不可能」ではなく、「このやり方を、こうしたら当社でも実行可能かもしれない」と実現志向で検討を深めてみてください。
1.エビデンス重視型の医師へのアプローチ
エビデンス重視型の医師には、科学的根拠に基づいた信頼性の高い情報を提供することが重要です。
●コンテンツ
最新の臨床試験結果、エビデンスに基づく治療法、薬剤の有効性データ、論文サマリ、メタ解析のグラフ、他社製品の誹謗中傷にならない臨床試験の主要アウトカム比較表*など
(*製薬企業各社のMR活動のガイドラインに準拠してください)
●アプローチ方法:
デジタルチャネル(ウェビナー、学術的な資料、オンラインフォーラム、医療関連の学術コミュニティプラットフォームなど)を通じて提供する。
●実行方法:
(1)医師の閲覧履歴・ダウンロード履歴で関心トピックをスコア化する。
(2)関心が高いトピックに対して自動で論文サマリを配信するレコメンデーションを組む。データはCRMや推奨エンジンを経由して、MR/MLと共有する。
2.臨床重視型の医師へのアプローチ
臨床重視型の医師には、日常診療で即座に活用できる実践的な情報を提供します。
●コンテンツ:
症例動画(処置や手術手技など)、実際の患者ケーススタディ、臨床での治療実績や使用例、臨床データ、診療プロトコル、実地で使えるチェックリストなど
●アプローチ方法:
症例集や臨床に基づいた治療法を共有するウェビナー、セミナー、MSL主導による院内ワークショップ、ハンズオンセミナー、訪問時の症例レビューなどを行う。
●実行方法:
(1)MRやMSLに対して、それぞれの役割に応じた個々の症例に基づいたトークスクリプトを準備し、実際に遭遇する症例に応じた資料を当日提供できる仕組み(モバイルアプリやPDFテンプレート)を用意する。
(2)医師への訪問時に、症例に基づいた具体的な提案を行う。
3.新規治療法重視型の医師へのアプローチ
革新型の医師には、最新性と革新性を前面に打ち出したコンテンツを提供します。
●コンテンツ:
新しい治療法や新薬の臨床データ、作用機序のビジュアル、専門家インタビューなどによる治療法の革新性をアピールする資料
●アプローチ方法:
オンラインセミナーや個別ミーティングで提供する。ただ提供するだけでなく、KOLやキーパーソンとの小規模ラウンドテーブル(対面あるいはオンライン)といった企画、もしくはKOLインタビューの配信など
●実行方法:
(1)KOLとの共同ウェビナーやピアレビュー形式の動画を制作し、該当する医師に優先的に案内する。
(2)一部の治療薬では実施済みだが、臨床導入のためのハンズオンサポート(病院での導入キットなど)も提供する。
4.予防型の医師へのアプローチ
予防志向型の医師には、地域全体の健康向上に貢献できる情報とツールを提供します。
●コンテンツ:
疾患予防、早期発見、健康管理に関連した情報(ガイドライン、予防プログラム、スクリーニングアルゴリズム、地域別リスクマップ〔心血管系リスクを下げる治療薬向け〕、予防プログラムテンプレート、健康関連データ、早期発見のサポートツールなど)
●アプローチ方法:
医師と地域住民を対象に、公衆衛生セミナー、自治体連携のワークショップ、PHRなどの予防ツールの情報提供あるいはアプリの制作と配信
●実行方法:
(1)予防接種プログラムや早期検診を支援するためのデジタルツールを提供し、医師が積極的に患者にアドバイスできるようサポート。
(2)可能であれば、蓄積された地域データと個々の患者を比較可能なBIツール、ビューワーなどを提供し、医師が院内にいながらにしてリスクが高い住民を早期発見可能なフローを組み立てられるよう支援する。
5.患者中心型の医師へのアプローチ
患者中心型の医師には、患者との関係構築と教育に役立つツールを重点的に提供します。
●コンテンツ:
患者との対話に役立つ情報、教育ツール、患者への説明資料。例えば、患者説明用のショート動画、患者の共感を呼ぶ医師の説明事例、患者向けFAQなど
●アプローチ方法:
患者教育に関するセミナーやツール(パンフレット、動画、FAQ)、診察室で使えるツール(iPad用コンテンツ)と患者向けパンフレットを同時に配布
●実行方法:
医師ごとに患者教育キットをカスタマイズし、処方時に医師が使えるテンプレート(言い換え例、アドヒアランス支援など)を提供する。
6.経済性重視型の医師へのアプローチ
経済性重視型の医師には、治療法の経済的利益を明確かつ分かりやすく提示できるデータとツールを提供します。
●コンテンツ:
薬剤のコストパフォーマンスに関するデータ、費用対効果を示す証拠、注射剤などの院内導入時のROIケーススタディ
診療内容に応じて医療費を算出できる「費用対効果シミュレーターアプリ」の開発など
●アプローチ方法:
コスト効果分析に基づいた製品データを提供し、治療法の経済性に関連する情報を強調。自社内の医療政策担当者を通じて、医療機関の財務担当者や病院薬剤師を交えた説明会、短期ROIレポートを提示
●実行方法:
(1)治療法の費用対効果に関する情報をオンラインセミナーなどで提供し、医療機関とのパートナーシップの構築を通じてサポートを強化する。
(2)費用対効果シミュレーターアプリで薬価や院内コスト構造を反映した医療費を算出し、医師と病院管理者に提示できる資料を準備する。
パーソナライゼーション施策実行時の重要なポイント
ここまで、医師のニーズを6つのタイプに分類し、それぞれに最適化されたアプローチ方法をご紹介してきました。しかし、いくら理論的に優れた施策を設計しても、実行段階で適切な体制や仕組みが整っていなければ、期待した成果は得られません。
本章では、セグメント別アプローチを実際の施策として機能させるために重要な5つの実行ポイントを解説します。
データ基盤をつくる
パーソナライゼーション施策の成否を左右するのが、医師に関するデータの統合管理です。CRM/CDPで、医師の「行動」「チャネル接触履歴」「アンケートによる態度情報」を紐付け、統合的に管理する仕組みを構築します。紐付けた結果をMRやMSLに確認してもらい、現場の声を施策に反映することで、施策全体に本社と現場の一体感を持たせ、施策の実行時の立ち上げをより早くすることができます。
コンテンツのモジュール化
セグメント別に効率的なコンテンツ提供を実現するには、柔軟に組み合わせ可能なモジュール設計が不可欠です。
動画コンテンツを例にすると、コンテンツの内容と最適な長さに応じて短尺(1〜3分の製品紹介動画)・中尺(症例解説)・長尺(論文の詳細解説)などをモジュール化して、組み合わせ可能にすることで、医師のセグメント別に利用しやすくなります。これにより、医師のセグメントや視聴シーンに応じて最適な組み合わせを提供でき、コンテンツの利用効率が向上します。
MR/MSLを最適化
デジタルとリアルの接点を連携させることで、人的リソースの効果を最大化できます。
デジタルチャネルで収集した嗜好をMR、MSL訪問時のスクリプトに反映させます。限られた人的リソースは、KOL/ AOR、病院のレジメン決定権を持つ医師、クリニックを含む大口処方医といった影響力の高い医師への対面活動に集中させることで、投資対効果を最大化します。
コンプライアンスと個人情報保護
医師や患者からの確実な同意取得のもとでデータを取り扱い、個人情報の匿名化や正当な第三者データの利用を徹底します。
KPI設計と実施後の効果測定
施策は実施して終わりではなく、継続的な検証と改善のサイクルを回すことが重要です。
デジタルコンテンツのインプレッションではなく、処方患者数やガイドラインの遵守状況といった「臨床上の行動変化」を主要指標にします。そのためにレセプトデータを活用し、診療の実態を見える化します。また、A/Bテストなどで効果を検証可能な設計に整えます。
医師のニーズに基づくパーソナライゼーション戦略
製薬業界のマーケティングにおいては長い間、マーケティングプランの実効性をいかにして高めるかということが検討され続けています。おそらく今後もその取り組みは続くでしょう。
世の中を広く見ると、売れている製品・サービスは確実に顧客のニーズを満たし、顧客がその製品やサービスを「使いたくてしょうがない」という気持ちにしています。
このような状況を作り出すための「顧客理解を深める思考法」や、「新しい技術・サービスへの興味関心を持つ」ことが、これからのプロダクトマネージャーに求められる要件になるかもしれません。
顧客理解を深める第一歩として、医師をニーズの塊にセグメンテーションする方法も、ぜひ試してみてください。

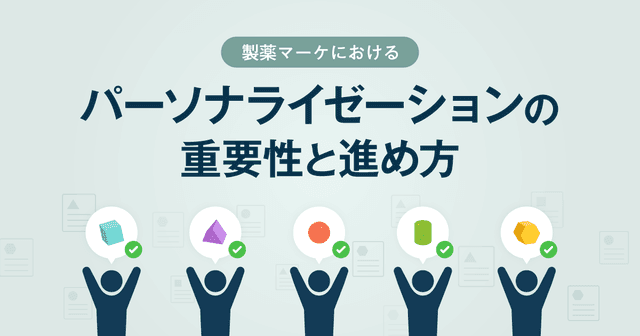


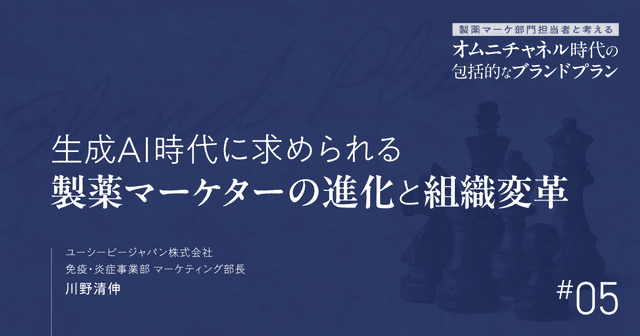
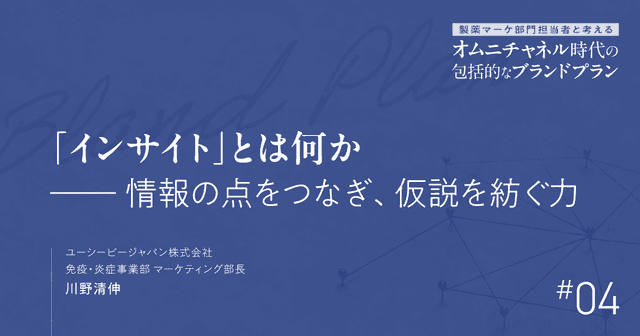

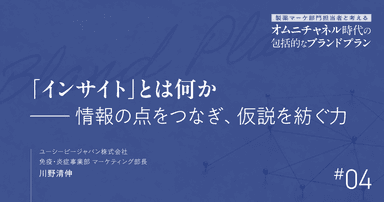




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



