第5回 生成AI時代に求められる製薬マーケターの進化と組織変革|製薬マーケ部門担当者と考えるオムニチャネル時代の包括的なブランドプラン
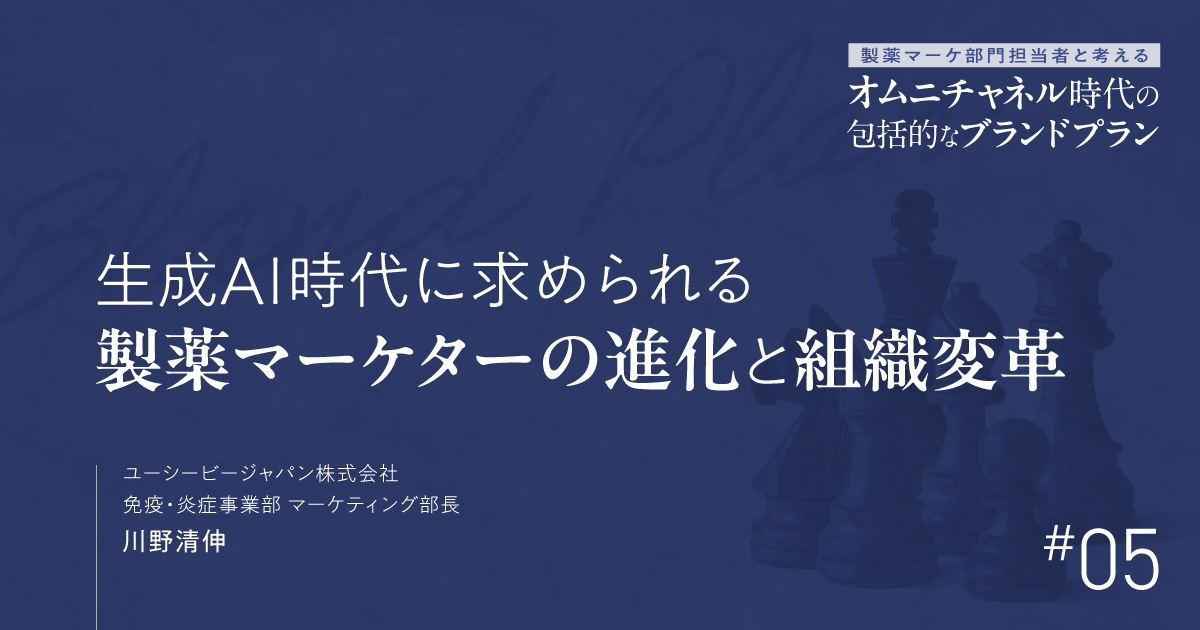
生成AIは、我々の仕事の在り方を根本から変えようとしています。この大きな波を受け、我々が活用する術を身に着ける必要性を強く感じています。また、マーケターの役割や組織体制を再定義する必要があるとも感じています。定型業務をAIが担うようになる一方で、これからのマーケターには一体何が求められるのか。本記事では、生成AIの普及が製薬マーケターに与える影響と、今後求められるスキルや組織の在り方について私なりの考えをまとめたいと思います。
(ユーシービージャパン株式会社 免疫・炎症事業部 マーケティング部長 川野清伸)
※記載内容は著者個人の見解であり、著者が所属する企業の見解や方針を代弁・表明するものではありません。また、記載内容は著者が所属する企業の状況に関するものではなく、あくまで著者の認識における製薬企業一般の話であることをご承知おきください。
生成AIの影響による業務構造の変化
多くの有識者が述べるように、生成AIが与えるインパクトは我々の想像以上なのだろうと私も感じています。特にマーケティング分野に与える影響は大きいと感じる一方、私を含めてクリアなイメージを持っている方は少ないのではないでしょうか。
我々は、その変化を見据えて生成AIの進化に乗り遅れないようにマインドやスキルをアップデートしなければなりません。部門の在り方やブランドマーケターの役割を再定義する必要もあるでしょう。
実際、生成AIの普及によって従来の業務プロセスは変化しつつあります。たとえば、資料作成や要約、会議の議事録作成といった業務は、今や生成AIが担える領域となりました。皆さんも、社内で導入されている生成AIを活用し、これらの業務効率化を実感されているのではないでしょうか。
余談になりますが、一般に提供されている生成AIツールを使えば、スライド作成なども手軽に行える時代になっています。こうした観点から見ると、平均的に大手の事業会社で働く方々よりも、スタートアップやフリーランスとして活躍されている方々のほうが、生成AIの活用レベルは一段と高いと感じます。
しかしながら、クリエイティブな発想や顧客との信頼関係の構築など、人間らしさが求められる業務は、依然として人間の役割として残り続けるでしょう。また、よく言われるように、生成AIは多様な回答案を提示することはできますが、最終的な意思決定はできません。しばらくの間は、判断力や決断力といった領域も、人間が担うべき重要な役割であり続けるのではないでしょうか。
重要なのは、生成AI時代においても人の創造性と判断力が中核となることです。AIは強力なツールですが、最終的な意思決定や戦略立案は、経験と洞察力を持った人間が担うべき領域です。
製薬業界のマーケターが今後担うべき役割と鍛えるべき力
製薬業界のマーケターには、役割を見直す時期が到来しています。上段で述べた通り、生成AIの浸透によって我々の業務に大きな変化が起こっているからです。他社の方々と議論をしていると、この変化のスピードは企業規模や内資・外資といった違いによっても異なるようですが、着実に変化の波は押し寄せています。
マーケターの進化する役割
製薬業界のマーケティングは消費材メーカーなど他業界とは異なり、戦略・戦術策定における変数に制約があります。さらに、薬機法などのレギュレーションが厳格であるため、表現の自由が限られています。
例えば、製品のキーメッセージについても、現在はファクトに基づく表現しかできません。製品のファンクショナルベネフィットやエモーショナルベネフィットのプロモーションはルールの範囲内で慎重に検討しなければなりません。そのほか、マーケティングの4Pで考えると、価格(Price)は薬価によって決まりますし、流通経路(Place)は日本の伝統的な制度(卸)があり介入することはできず、限られた変数しかコントロールできないのです。
さらにAI時代のマーケターは、戦略作成、分析、資料作成などの業務をどのように生成AIと分担すべきか我々の役割を含めて向き合っていかなければなりません。マーケターが担うべき役割がどんどん狭くなっていくことが容易に想定されますね。
だからこそ、ブランドマーケターは我々の役割をプロダクトマーケティングのみにこだわらず幅広く捉える必要があると私は考えています。オムニチャネルは良い一例です。
オムニチャネルでのアプローチをどのようにデザインするのか?テクノロジーをどのように活用するのか?クロスファンクショナルチームをリードしてプランを創っていきましょう。製品のみにフォーカスするのではなく、製品および会社(つまりより広いスコープで)をどのようにプロモーションするのかを社内の各部門との密な連携によって導き出すこともスコープに入れるべきだと考えています。そのため、私はプロダクトマーケティングではなくブランドマーケティングという言葉を用いるようにしています。
今後、AI時代のマーケターがどのような役割を担うべきかについては有識者の方々と議論しながら私自身も思考を深めていきたいと考えています。
AI時代のマーケターにとって重要なスキル、コンピテンシー
このような役割変化の中で、今後のマーケターは以下のスキルやコンピテンシーが重要になってくるのではないでしょうか。
1. 問いを立てる力
特に重要なのは「問いを立てる力」です。生成AIは与えられた質問に対して優れた回答を提供しますが、どのような質問をするべきかを決めるのは人間の仕事です。
ビジネスインパクトを出す上で「今、解決すべき問いは何なのか?」本質に迫るマインドと適切な問いを立てる力は不可欠ではないでしょうか。
いくら膨大なデータを保有して、AIを駆使した分析がなされていても、適切な問いが設定されてなければ無駄になってしまいます。
2. おもしろがる力
日々のテクノロジーの発展のスピードは凄まじいものです。その観点で個人的に重要視しているのは「おもしろがる力」です。生成AIを含めた新しいテクノロジーが発展していく生成AI時代において、「興味を持ち、自ら触って試す」ということは極めて重要です。
生成AIから得られた新たな発見に驚き、何かに活用できないのか?探求する姿勢が、革新的なマーケティングアプローチの創出につながるのではないでしょうか。
3. テクノロジーギャップを埋める力
生成AIを含めた新しいテクノロジーをどのように活用して課題を解決するのか、イメージできていない方は多いのではないでしょうか。
テクノロジーが発展する一方、ビジネス課題と結び付けて考えることができる人が非常に少ないのです。私はこれを「テクノロジーギャップ」と呼んでいます。
一部の製薬企業では「ビジネストランスレーター」が創設されこのギャップに取り組んでいますが、どの程度機能しているのかは不明です。これも部門のサイロ化の問題を生む一因になっているのかもしれません。
テクノロジーの価値を知り、我々が抱える課題に適合させていく力は益々重要性を増していくと考えられます。私は絵に描いたようなきれいな成功が重要だとは思っていません。新しいことにトライしてそこから学びを得て次につなげていく「テクノロジーギャップを埋める力」が重要と考えています。
4. 顧客視点に立ち続ける力
テクノロジーギャップを埋める上でも重要なのは顧客視点です。顧客目線を掲げながら気が付けば企業視点になっていることは往々にしてあります。
顧客のジョブ(特定の状況で成し遂げたい進歩)に迫るには、顧客視点に立ち、インサイトを読み解くマインドやスキルが不可欠です。言うは易く行うは難しですが、『ジョブ理論』(クレイトン・M・クリステンセン著)を読み返す度に、顧客のジョブにどれだけ迫れているのかと反省させられます。
生成AI時代においても変わらないのは、顧客ニーズに応えることが最優先であるということではないでしょうか。
マーケターは、新しいテクノロジーを活用しながらも、常に顧客の視点に立ち、彼らの課題解決に貢献することを忘れてはなりません。オムニチャネル、マルチチャネル、シングルチャネルのいずれであっても、顧客のニーズに最も適したアプローチを選択することが重要です。
生成AI時代の組織のあり方とコラボレーションの重要性
組織の在り方についても、根本的に見直す必要があると考えています。従来のように各部門がサイロ化され、内に閉じた状態では、AIを含めたテクノロジーの恩恵を最大限に活用することは困難です。
リアルタイムでの情報共有が可能なシームレスな組織デザイン
「データとインサイトの流通を促進する組織構造」が必要です。マーケティング部門やデータ分析部門、デジタル部門、メディカル部門、営業部門、そして外部のパートナーとの間で、スムーズかつシームレスな情報流通が可能な仕組みを構築することが重要です。
これにより、AIが生成した分析結果や予測を、迅速に意思決定に反映させることができます。
一方、サイロ化された組織においても、顧客を中心に据えて、クロスファンクショナルにオープンなリーダーシップをとる人材がいれば、組織構造は必ずしも壁にならないのかもしれません。私が伝えたいのは、傑出した人材が組織に存在しなくても価値を創出できる組織デザインのことを指しています。
内製と外注の最適配分
AIを活用した業務においては、内製化と外注化のバランスを慎重に検討する必要があります。戦略的な意思決定や顧客インサイトの解釈など、企業の競争優位性に直結する領域は内製化を進める一方で、データ処理や定型的な分析業務については外注化を積極的に活用することが効率的です。しかしながら、生成AI時代の昨今はデジタル化されたデータを活用したサードパーティーメディア、スタートアップが勃興しており、内製と外注の線引きが難しくなっていると感じます。いずれにしても、経営者は専門家を頼りながらこの問題に向き合っていかなくてはなりません。
枠組みを超えた取り組みやネットワークの価値
知識や情報が流通し、異なる能力を持つ人々が集まって議論を交わす。これこそが集合知(コレクティブ・インテリジェンス)の場をつくるのだと思います。
従来の製薬業界は、各社が独自の方法論やアプローチを追求し、競合他社との情報共有は限定的でした。しかし、オムニチャネル時代においては、業界全体で共通の課題に直面しており、個社の取り組みだけでは限界があります。特に、医療関係者の行動変容や新しいテクノロジーの活用については、業界横断的な知見の共有が不可欠です。
私が共同代表を務める製薬ビジネス研究会では、異なる会社のマーケターやメディカル部門、教育の担当者など幅広い専門家が一堂に会し、実践的な議論を展開しています。ここで得られるインサイトは、社内の議論だけでは到達できない視点や解決策を提供してくれます。例えば、A社のデジタルマーケティングの成功事例を、B社の顧客セグメンテーション手法と組み合わせることで、全く新しいアプローチが生まれることもあります。
このようなネットワークの力は、生成AI時代においてさらに重要性を増します。AIが提供する情報や分析結果を、どのように解釈し、実際のビジネスに活用するかは、人間の知見と経験に依存する部分が大きいからです。多様な背景を持つ専門家との議論を通じて、AIの出力を適切に評価し、実践的なアクションに変換する能力を磨くことができるのです。
オープンイノベーション推進の可能性
製薬業界におけるオープンイノベーションは、単なる技術的な協力を超えて、マーケティングやビジネスモデルの革新にまで及んでいます。多くのサードパーティーメディアやスタートアップ企業との協働により、従来の発想にとらわれない新しいアプローチが生まれています。
例えば、患者向けアプリの開発において、製薬企業の医学的知見とIT企業のユーザーエクスペリエンス設計能力を組み合わせることで、より効果的なソリューションが生まれています。また、AIを活用した創薬プロセスにおいても、異業種との協働が新しい可能性を開いています。
生成AI時代の製薬マーケティングが向かう進化の方向性
今後の製薬マーケティングは、デジタルマーケティング部門との融合も含めて、以下のような方向性で進化していくのではないでしょうか。
1. パーソナライゼーションの深化
AIを活用した個別最適化により、一人ひとりの医療関係者に合わせたコンテンツやタイミングでのアプローチが推進されていくでしょう。
業界関係者と議論していると、データ基盤などの問題はクリティカルであると感じます。また、コンテンツ作成での生成AIの活用は日本の厳格なレギュレーションや文化がネックとなるでしょう。しかしながら、ナレッジは蓄積されており、パーソナライゼーションは加速していくでしょう。
2. リアルタイム分析と即座の戦略修正
フィジカルおよびデジタルチャネルから得られるデータをリアルタイムで分析し、キャンペーンなどを即座に修正できるようになるでしょう。
実行には役割分担やプロセスのデザインが重要です。さらに組織文化(私の解釈は共通の価値判断基準)の改革も重要になってきます。
私はこれからの時代、戦術レベルの最適化が競争優位性を生むと考えています。上段でも述べましたが、製薬マーケティングは戦略部分でコントールできる変数が少ないからです。
さらに、製薬業界の希少疾患ビジネスモデルに陰りがみられることも一つの要因です。私の理解では、製薬各社はプライマリーケアから希少疾患領域への開発投資を加速させ、多くの薬剤を発売してきました。これは高い薬価が獲得できること、かつ競争の少ない分野で販管費を抑えることで利益率を高める狙いが含まれていたと考えています。
しかしながら、現在では希少疾患領域においても(一部を除き)多数の薬剤が開発・発売され、SOV(Share of Voice)が処方に大きな影響を与えています。つまり、戦術を含めて実行力が処方に大きなインパクトを持つのです。これらの理由から、実行を含めた戦術レベルの最適化が競争優位性を生むと考えています。
3. エコシステム全体の設計
繰り返しになりますが、デジタル化が一因となり、日本でも多くのサードパーティーメディアが誕生しています。サービスが多様化しており分類ができないくらいです。
つまり、顧客を中心に据え、多くのプレイヤーがタッチポイントを持つ構造ができつつあります。よって、製薬企業単独ではなく、患者や医療機関、他の製薬企業、さらには業界外のステークホルダーを含むエコシステム全体を考慮した包括的なプラン構築の重要性はますます高まってくるでしょう。
戦術レベルで展開される一つの施策を、他社とコラボレーションすることで何倍もの価値を提供できる可能性を秘めています。ブランドマーケターは高い視座、多様な視点を持ち、担当領域のエコシステムを踏まえながらブランドプランを検討していくべきでしょう。
4. 価値創造の多様化
単なる製品プロモーションではなく、ブランドの価値最大化を広義に捉え、医療関係者の業務効率化や患者の QOL向上に直接貢献するソリューションの提供も考えていくべきでしょう。SaMDの保険償還のニュースはそれらの動きを再活性化させる一つのきっかけになるのではないかと考えています。
経営者視点ではROIの観点から投資を判断せざるを得ないと思いますが、ブランドマーケターは違います。顧客への価値創造・提供が長期的な自社の利益につながることを訴え、オリジナリティ溢れる取り組みをどんどんリリースしていただけることを期待します。
今回述べた事項一つひとつをもっと掘り下げて議論することで、新しい示唆が得られるのではないかと思います。次回は、これらの概念を踏まえて、具体的なブランドプラン策定のプロセスについて、実践的な観点から詳しく解説します。
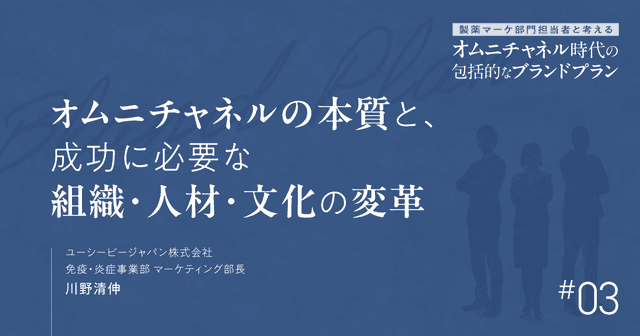



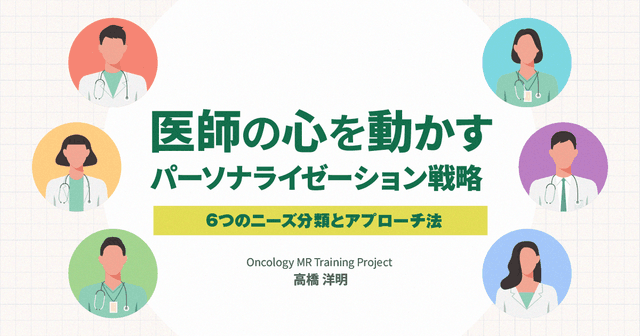
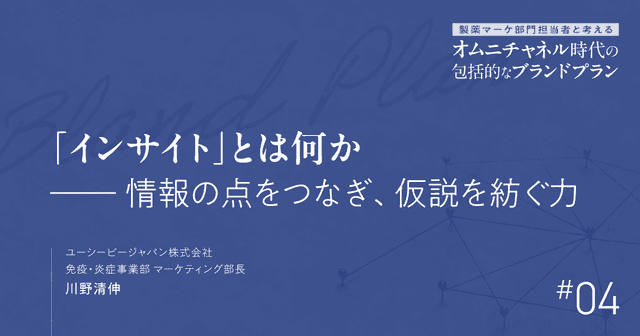


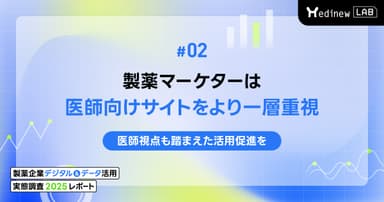



.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



