第3回 オムニチャネルの本質と、成功に必要な組織・人材・文化の変革|製薬マーケ部門担当者と考えるオムニチャネル時代の包括的なブランドプラン
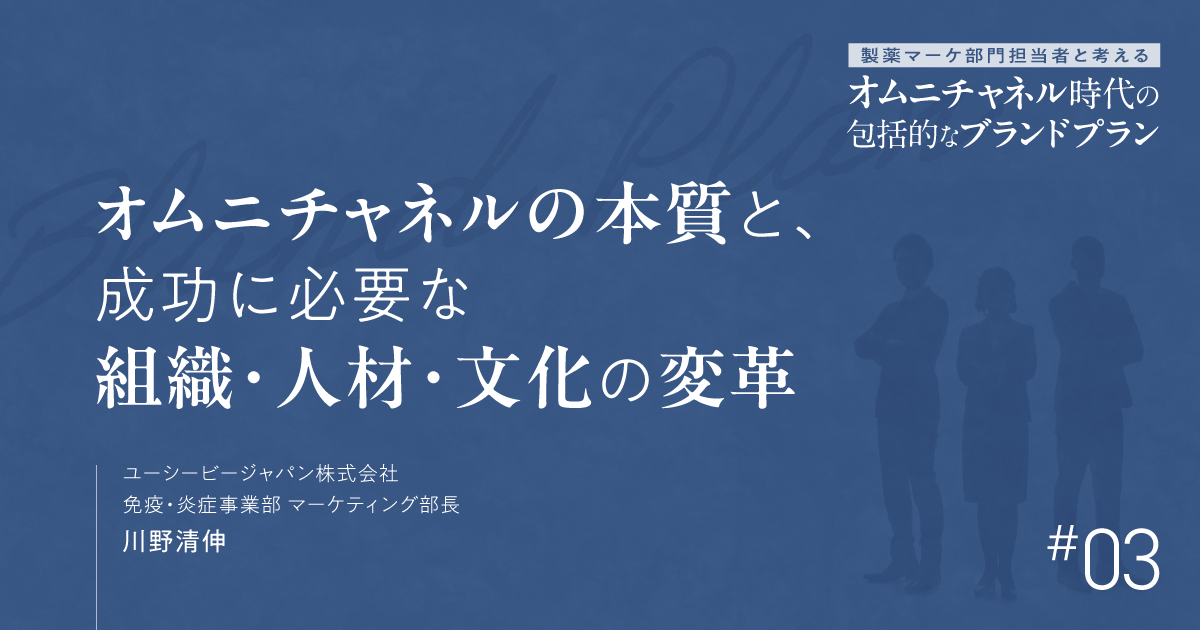
本連載の第2回「オムニチャネルの定義と位置づけを整理する」では、一般的なオムニチャネルの定義や製薬業界での位置づけについて私なりの考えを述べました。今回は、7月初旬に登壇した2025 Veeva Japan Commercial & Medical Summitの場でさまざまな方とのディスカッションを通じて得られたインサイトを踏まえ、オムニチャネルの本質と、その成功に必要な組織、ケイパビリティ、そして企業文化の変革について私見を交えながら改めて整理します。
(ユーシービージャパン株式会社 免疫・炎症事業部 マーケティング部長 川野清伸)
※記載内容は著者個人の見解であり、著者が所属する企業の見解や方針を代弁・表明するものではありません。また、記載内容は著者が所属する企業の状況に関するものではなく、あくまで著者の認識における製薬企業一般の話であることをご承知おきください。
10年前から変わらない製薬オムニチャネルの課題
2010年代前半からサードパーティーメディアやWeb講演会が登場し、マルチチャネルの時代が到来しました。当時からオムニチャネルに関する議論が活発になり、業界全体でその重要性が強調されるようになりました。
しかし、10年以上が経過した今でも、本質的な課題は変わっていないということを痛感します。事実、とあるデジタルマーケティングの重鎮から「製薬業界のオムニチャネルは確実に前進しているものの、多くの企業では依然として技術論やツール論に終始し、顧客を置き去りにした議論が展開されている」とコメントをいただいたこともあります。
特に、オムニチャネルを目的化してしまっていることに違和感を覚えます。オムニチャネルは手段であり、顧客である医療関係者にとって最適な体験を提供するための方法論にすぎません。しかし、「オムニチャネルを実現すること」が目標になってしまい、本来の目的である顧客価値の向上が二の次になってしまっているケースが少なくないのではないでしょうか。
また、多くの企業はデジタル化の波に乗り遅れまいと、急速にデジタルチャネルの拡充を進めましたが、そこに明確な戦略や顧客インサイトに基づく設計が伴っていない場合が多いのが現状です。
マルチチャネルは悪なのか?
このような背景から、何のためのチャネルアプローチなのか?を考えるようになりました。私は、マルチチャネルが悪いのではなく、目的を達成するために適切なチャネルアプローチが選択されるべきだと考えています。製薬業界においては、以下のような理由から必ずしもオムニチャネルを前提とする必要はないと思われます。
- 未だMRを中心とした市場構造であり、デジタルへの依存度が小売業に比べて低い
- 薬のポテンシャルへの依存度が大きく、ライフサイクルに応じたリソース投下が売上を大きく左右する(複雑なテーマなので、別途議論したいと思います)
- 処方する医師と購買する人が異なる
- 処方する医師の年齢層が依然として高い
- 規制業界であり他業種からの参入が容易ではない
日本ではアフターコロナの今、デジタル化は着実に進んでいるものの、MRを中心とした対面アプローチへの回帰が見られています。実際、多くの医療機関で対面での面談が再開され、医療関係者からも「やはり直接話すことで得られる情報の価値は高い」という声を聞きます。
この事実は、チャネルミックスを顧客のニーズとコンテキストに合わせて最適化することの重要性を、改めて示していると言えるでしょう。
最終的にどのチャネルでのアプローチを心地よいと感じるかは、顧客自身が決めることです。だからこそ、企業は「オムニチャネル」や「マルチチャネル」といった言葉に囚われるのではなく、顧客が本当に求めているアプローチは何かを第一に考える必要があります。顧客によっては、複数のチャネルが連携された一貫した体験を好む場合もあれば、単一のチャネルで完結するシンプルな情報提供を好む場合もあるでしょう。
例えば、以下のように顧客の状況に合わせてチャネルを使い分けることが考えられます。
- 対面が有効なケース:新薬の効能効果や副作用について詳細な説明と議論をする際など、複雑な情報交換が求められるとき。情報提供から生じた疑問を即時に解決する、提供された情報を消化して、薬の使い方に昇華させるプロセスでは、即時性や柔軟性が求められるためです。
- デジタルが有効なケース:学会で発表された最新の情報やPublicationについての情報など、医師が多忙な中でも把握しておきたい情報を提供するとき。空いた時間にスマートフォンを通じて情報を視認できるデジタルチャネルや、通勤時間に音声として情報を得られるPodcastなどは有用であり、ニーズは高まっていくでしょう。
このように、顧客の時間的制約やライフスタイルまでも考慮し、最適なコミュニケーションを追求する姿勢が、これからの製薬企業のマーケティングには求められるのではないでしょうか。
原点回帰から真のオムニチャネルへ
しかし、原点回帰するだけで満足してはいけません。業界の潮流に乗り遅れず、シニアマネジメントの期待に応えるためにも、将来を見据えた進化は不可欠です。
今この時代にオムニチャネルでのアプローチが有効なセグメントは確かに存在しますし、将来的にはより多くの顧客に対してオムニチャネルでのアプローチを行う必要性は高まると考えられます。
だからこそ我々は、「顧客視点でのチャネル最適化」という原点をしっかりとふまえた上で、その先にある「真のオムニチャネル」とは何かを構想し、その実現に向けた準備を進めていく必要があるのです。
人や組織の観点から、オムニチャネル成功の要因を考察する
それではオムニチャネルを成功に導くにはどのような観点からアプローチをする必要があるのでしょうか?先日Veeva Summitに登壇した際、「組織や人の観点から」というお題をいただき、私なりに整理してみました。組織、人、文化の観点から考えを述べてみたいと思います。
組織の観点
統合的なチャネルマネジメントが可能な組織体制
コロナの到来は製薬業界にも大きな変化を与えました。デジタルマーケティング、オムニチャネル部門の設立がデジタル化を促しましたが、同時に組織のサイロ化を進めました。このサイロ化されたアプローチから、顧客を中心においたジャーニーを設計してアプローチをすることが求められました。マーケティング部門、営業部門、メディカル部門がそれぞれ独立して活動し、顧客との接点も分断されました。
真のオムニチャネル実現のためには、サイロ化を前提とした独立したチャネルマネジメントから、統合的なチャネルマネジメントへの変革が必要です。具体的には、Cross-functional teamの設置や、Customer Experience Managerのような横断的な役割の創設が考えられます。実際に大手を中心に横串でマネジメントをする部門や担当者の設置が進んでいます。
柔軟かつ迅速な意思決定を可能にする組織運営
加えて、アジャイル型のアプローチも一つの選択肢ではないかと思います。従来のウォーターフォール型の意思決定プロセスでは、市場の変化に迅速に対応することが困難だからです。顧客からのフィードバックを素早く戦略に反映させるためには、より柔軟で迅速な組織運営が求められます。
とはいえ、アジャイル型のアプローチが製薬業界に適しているのかについては有識者を交えて議論する必要があるように思います。上段で述べましたが、製薬業界は変化のスピードが他の業界に比べて遅く、頻繁に方針転換することが多くはないと想定できるからです。
製品のライフサイクルに応じてアプローチ方法を分けることも一つの選択肢なのかもしれません。
人&組織(ケイパビリティ)の観点
製品中心志向から顧客中心志向へ
オムニチャネル戦略を成功に導くためには、ケイパビリティ*の強化が不可欠です。とりわけ重要なのは、顧客を中心に据え、UXを軸として思考から行動まで実践できる素養を育むことです。
*ケイパビリティ(Capability:企業競争力を高める組織的な能力)
しかし顧客志向と言いながら、いつの間にかプロダクト中心の思考に戻ってしまう――それが現場での難しさの一つでしょう。私も限られた経験の中でその難しさを痛感しています。
真の顧客中心の思考を身につけるためには、デザインシンキングやカスタマージャーニーマッピングなどの手法を習得すると共に、常に我々のMissionやVisionに立ち戻れる仕組みをつくることも重要であると考えます。
例えば「年に1回患者さんの声を聴く」だけではなく、
- 患者の声を聴く機会をルーチン業務に組み込む
- 患者志向の企業・人と定期的に交流する機会を設ける
など、顧客視点を常に意識し続けられる環境づくりも併せて考えていくべきでしょう。しかしながら、言うは易く行うは難しです。
インサイト・データドリブン型の意思決定への変革
経験や勘に基づく判断からインサイト・データドリブン型の意思決定への変革を加速させることも重要です。多くの企業ではすでに、データ基盤の整備やAI技術の活用が推進されています。
一方、インサイトに基づく仮説構築ができる人材の育成も急務です。散在する情報からインサイトを導き出せる人材が圧倒的に不足しているように感じるからです。
インサイトの定義は多々あるのだと思いますが、私は大前提として、「顧客が自覚していない、つまり言語化できていないこと」であるとした上で、以下を満たすものだと考えています。
- 点と点の情報を掛け合わせて一つの示唆を導くこと
- その示唆が顧客の抱える課題にインパクトを与えること
インサイトについて、ここでは語りつくせないため、また別の機会に私なりの考えを述べさせてください。デジタル化やAIが急速に普及する今後の世界において、論理的に導き出すことができない何かを読み解く力がより一層求められるのかもしれません。
今後は、データ(とくにファーストパーティーデータ)とインサイトの両輪を回すことが、企業の競争優位の源泉になるのではないでしょうか。
もちろん、AIなどを活用した高度な分析は、これらの変革を後押しします。機械学習を活用した顧客セグメンテーションや、予測分析による最適なタイミングでのアプローチなど、従来では不可能だった精度の高いマーケティングが製薬業界でも実現可能になっていくでしょう。
当然、マーケターはこれらの新しいテクノロジーを使いこなすスキルを習得する必要があります。しかし、顧客のインサイトを読み解き戦略を立てるという、マーケターとして求められる本質的なスキルやコンピテンシーはこれからも変わらないのかもしれません。その場合、誰がテクノロジーの専門家としての役割を担うべきなのか?についても重要な論点になってくると考えられます。理想的な役割分担やチームのあり方を検討し、各社に合った最適な体制を構築していく必要があるでしょう。
文化の観点
「当たり前」を変える
「文化」とは何を指すのでしょうか?ここではあえてオムニチャネルの文脈で語られる“チェンジマネジメント”といったビッグワードを用いておりません。言葉自体が独り歩きして、定義が曖昧な状態で使われている印象もあり、違和感を覚えているからです。
私は文化とは「共通の価値判断基準を持つこと」だと捉えています。
つまり、文化の改革とは「当たり前を変える」ということなのではないでしょうか。製品中心から顧客中心へのシフト、常に顧客を中心におけるかがキーとなるでしょう。これは単なるスローガンではなく、日々の業務における意思決定の基準を変えることを意味します。
継続的に学ぶ組織へ
変化に抵抗するのではなく、継続的に学ぶ集団へと変遷することも重要です。上段で述べた通り、製薬業界はいまだ保守的な文化が根づいています。変わらなくても大きなリスクに晒されることは考えにくいからです。
しかし、外部環境は確実に変化しつつあり、そのスピードも加速しています。
近い将来、劇的な変化が起こる可能性も考えられます。特にデジタル化の波の中では、失敗を恐れずに新しいアプローチを試行錯誤する姿勢を追及していく必要があるでしょう。
個人の行動が文化を変える。オープンコラボレーションの可能性
文化を変えるもう一つの鍵は、オープンコラボレーションです。
社内に閉じず、外部のパートナーや顧客とも積極的に協働することで、新しい視点や価値が生まれます。
たとえ最終的にコラボレーションが実現しなくとも、一歩を踏み出したことは個人として、組織としても何かしらの学びになるはずです。
1人でも多く、そうした行動を起こせる人材が育っていくことが、業界全体の前進につながっていくのではないでしょうか。

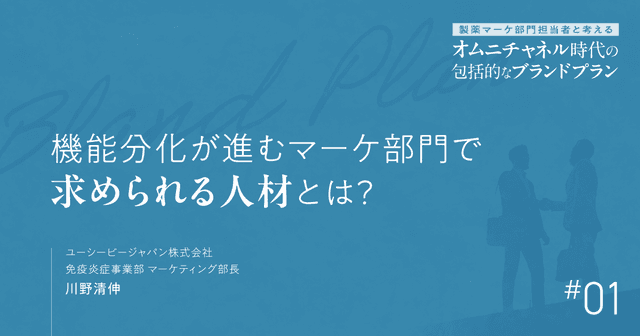

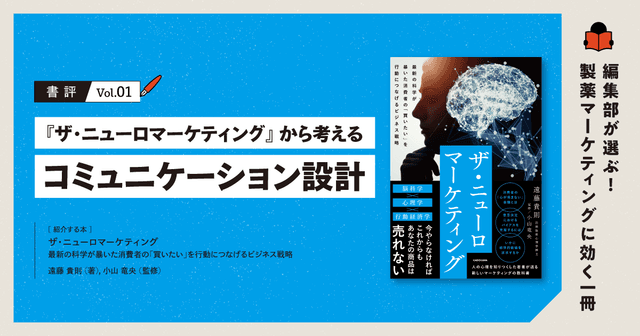
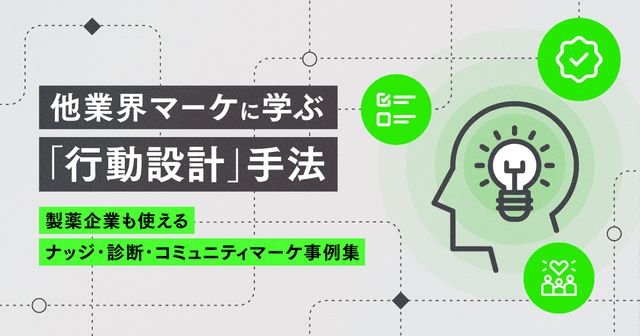



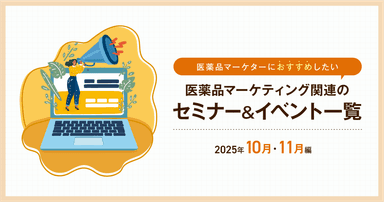
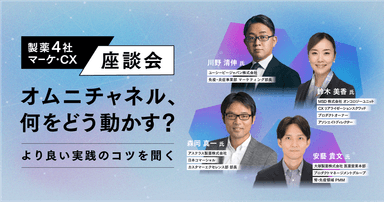




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



