#8 医師と製薬企業をつなぐ対話の場-必要なのは情報提供ではなくディスカッション|Dr.心拍の「製薬本社にちょっと言いたい」
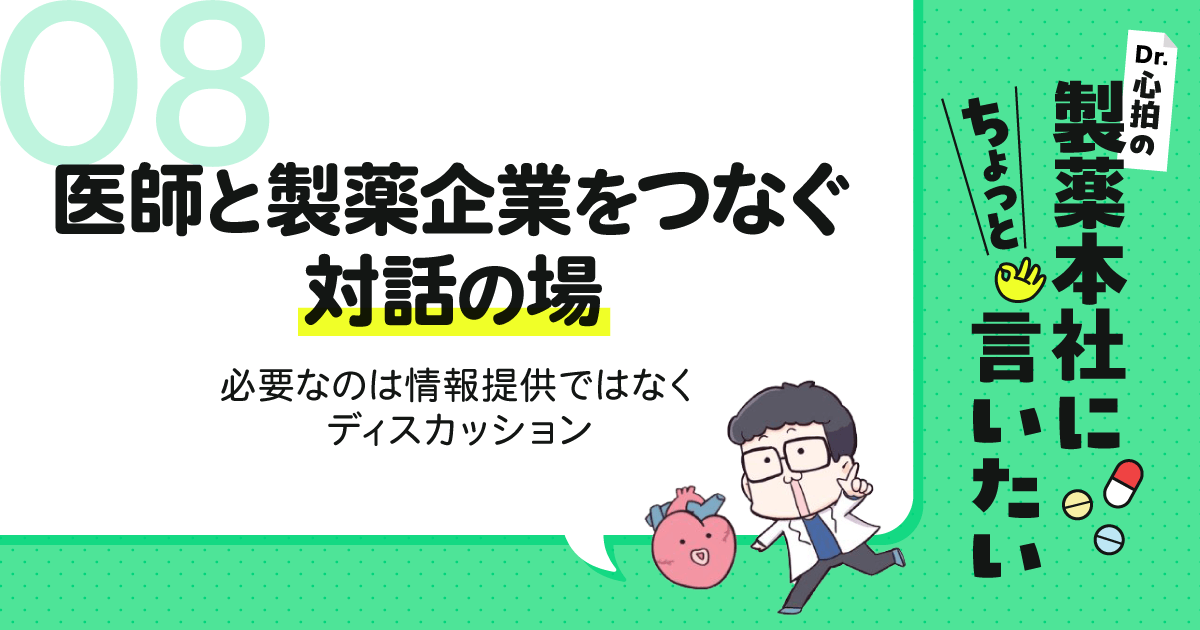
現在の情報提供に感じる課題
普段勤務医をしている私にとって、「製薬企業の方」と言えば、ほとんど「MRさん」を想像していました。通常の病院勤務医の大半も、同様の認識ではないかと推察します。
しかし、自身のビジネスを通して病院外でさまざまなヘルスケア領域の方とお会いするようになり、製薬企業には「MRさん」以外にも創薬や開発、マーケティング、メディカルアフェアーズなど多くの部門があることに視野が広がりました。私自身まだその全貌の一部を把握した程度で恐縮ですが、この気づきが今回のテーマにつながっています。
現在のMR活動は、情報提供という名目でありながら、実際は我々医師へのヒアリングが中心となっているように感じていることは先日の記事でお伝えしました。
レギュレーションによって本来製薬企業が提供したい情報、本来医師が求めている情報を十分に提供できない状況があるという点は理解しています。必要に応じて本社の学術担当の方が情報提供をしてくださることもありますが、MRさんを経由する必要があるなど手続きが煩雑で、結果的に「自分で調べるので大丈夫です」とお断りしてしまうケースもあります。
社内勉強会で感じた「対話の場」の必要性
私は時折、製薬企業の社内勉強会講師としてお声がけいただくことがあります。参加者にはMRさんもいらっしゃいますが、MR教育を担当する製薬企業本社の方も必ず参加されています。
製薬企業がスポンサーとなる医師の講演会では、適切なプロモーションコードの遵守により、情報提供の内容や形式に一定の制約があります。例えば講演スライドがまるっと削られてしまったり、薬剤や臨床研究のデータの比較が許されなかったりと、医師のニーズに相反する状況ではないかと感じる場面もあります。
一方、製薬企業の社内勉強会では、同様にプロモーションコードを遵守しながらも、教育・研修の文脈でより柔軟な情報交換が可能な場合もあり、率直なディスカッションができる機会となります。
ディスカッションがもたらす価値
具体的には、我々医師が日常診療で感じている課題や疑問などを製薬企業のさまざまな部署の方とディスカッションすることにより、視点がずれたMR活動を修正することに繋がります。
また、ガイドライン改訂などに際した薬剤の戦略会議に参加させていただいたこともありますが、製薬企業がイメージしたマーケティング戦略の課題と、我々臨床現場での課題感のずれが明らかとなり、直接ディスカッションすることで解決できた事例もありました。
製薬企業本社の方は、なかなか普段医療現場を見る機会はないからこそ、もっと現場に寄り添う「情報収集」を本社を含むさまざまな部署の方に行っていただきたいと思います。
臨床現場と製薬企業の「ずれ」の課題を解決するためには、製薬企業がより積極的に社内勉強会に医師を招いて臨床現場の実態とのすり合わせを行うことが重要ではないかと考え、少しずつですが個人的に活動しています。その際に、領域ベースあるいは薬剤ベースで行うだけでなく、縦割りとなっている製薬企業の部署を横断するような部署を交えた本社勉強会を行うのが効果的である印象を受けています。
限られた時間で行われるMR面談とは異なり、社内勉強会など十分な時間を確保した議論の場が設けられることで、医師としてもより前向きに、そしてしっかりと製薬企業に寄り添って対応できるのではないかと感じます。
さて、今回は医師と製薬本社との対話の必要性についてお話ししました。このような対話の機会が増えることで、より良い医療の実現につながることを期待しています。
【編集後記】
今回は医師と製薬企業との対話のあり方について、Dr.心拍氏に所感を伺いました。
データドリブンなマーケティングが重要視される一方で、「現場の医師との直接対話」の価値が改めて浮き彫りになったのではないでしょうか。
特に、Dr.心拍氏が実際に体験された「マーケティング戦略の課題と臨床現場での課題感のずれを直接ディスカッションすることで解決できた」という事例は、精緻なデータ分析を行った上でも、実際の医療現場の声を聞かなければ見えてこない盲点があることを示しています。
データとデジタルツールは確かに強力な武器ですが、それらを活かすためにも医療現場の生の声は不可欠です。Dr.心拍氏が提案する社内勉強会のような場を活用する際も、適切なコンプライアンスの確保は欠かせません。その上で、データドリブンなマーケティングと医師との直接対話を両輪として回していく姿勢が、今後の製薬マーケティングには求められそうです。
(Medinew編集部)



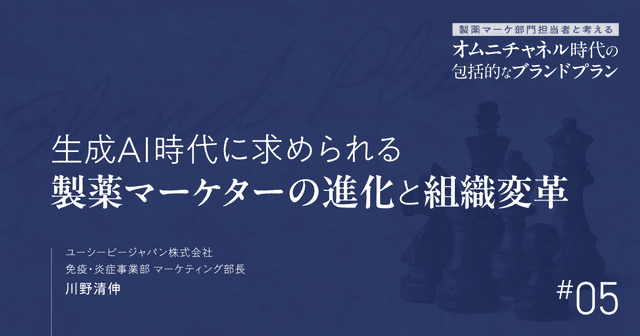
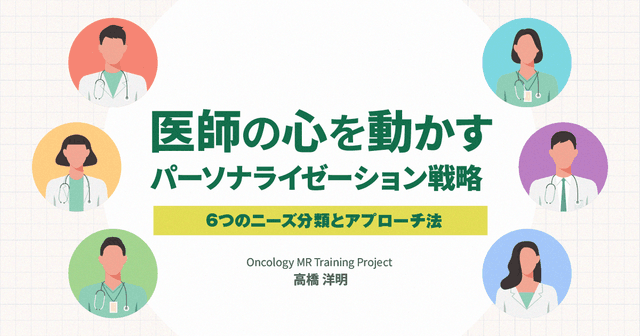
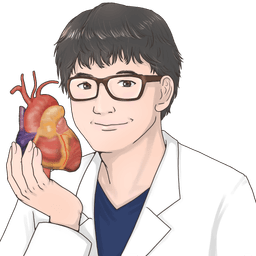

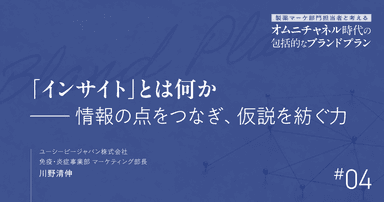



.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



