製薬業界マーケティング/DX最新動向まとめ 2024年総括版 〜製薬企業の1年間の動きを振り返る〜
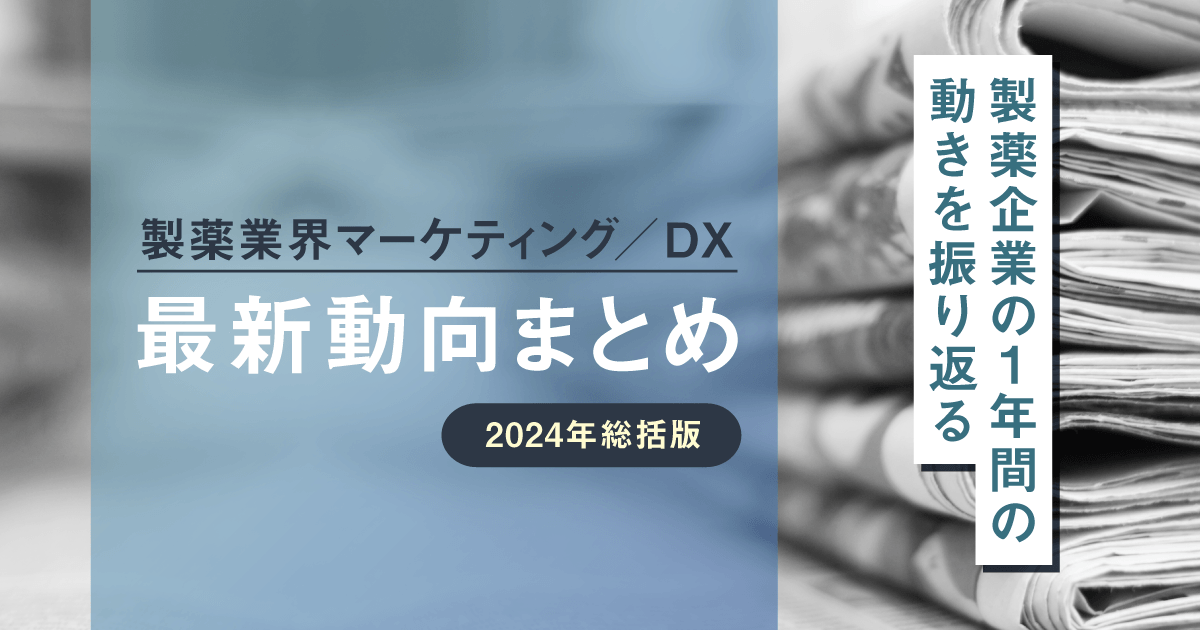
Medinewでは、2カ月に1回、各製薬企業のプレスリリースより、最新製薬マーケティングやDXの取り組みをピックアップしてお届けしています。今回は、2024年のプレスリリースを振り返り、マーケティング、プロモーション、DXについて、製薬企業の動向をまとめました。この1年間での業界全体のトレンドや、他社がどのような動きをしているのかを把握するためにぜひお役立てください。
※調査対象の企業は2024年5月にIQVIAより公開された23年度販売会社ベース企業売上ランキング(期間:2023年4月~2024年3月)より抜粋した19社。50音順にリストアップ
デジタル技術を活用した治療・支援ツールの実用化が加速
2024年は、デジタル技術を活用した治療・支援ツールの実用化が大きく進展した年となりました。
大塚製薬は、大うつ病用デジタル治療アプリ「Rejoyn™」が世界初のFDA認可を取得し、米国での販売を開始。また同社では、「感情認知トレーニングVR」や「認知症ケア支援VR」など、VR技術を活用した支援ツールの展開も積極的に進めています。「感情認知トレーニングVR」は、自閉スペクトラム症などの発達特性を持つ方を対象とした、感情の読み取りを学ぶ世界初のVRトレーニングプログラムで、相手の感情を推測し、それに合わせた対応方法をVRで学ぶことができます。「認知症ケア支援VR」は、認知症患者と介護者双方の視点に立った支援を目指し、介護者のストレス軽減と患者のQOL向上を同時に実現しようとする取り組みです。
(大塚製薬)デジタル治療アプリ「Rejoyn™」を米国で発売開始ーFDAで認可された世界初の大うつ病アプリー
(大塚製薬)FACEDUO「感情認知トレーニングVR」の提供を開始 ―感情の読み取りが難しい自閉スペクトラム症(ASD)などの発達特性をお持ちの方の支援として―
(大塚製薬)FACEDUO「認知症ケア支援VR」の提供を開始 - 認知症の人と介護者がともにいきいき暮らす「共生」社会の実現を目指して –
アストラゼネカと富士フイルムは、切除不能なステージIII非小細胞肺がん(NSCLC)の化学放射線療法に関する医療情報システムを共同開発しました。腫瘍の位置や条件を指定すると、データベースから類似の過去症例を検索し、その放射線治療計画情報を表示することができます。治療計画作成の難しさが医療現場の大きな負担となっていましたが、本システムによってより効率的な治療計画の立案が可能となり、患者に対する治療の最適化と予後改善への貢献が期待されています。
アストラゼネカと富士フイルム、肺がんの化学放射線療法の過去症例を検索できる医療情報システムを共同開発
パーソナルヘルスレコード(PHR)の活用で個別化医療が進む
パーソナルヘルスレコード(PHR)を活用した取り組みも注目を集めています。
沢井製薬は、福岡県飯塚市と連携し、PHRサービスを起点とした健康なまちづくり形成に関する実証事業を実施。同社が提供するPHR管理アプリ「SaluDi」を活用し、参加者の72.8%が「実証前と比べて健康に関して意識することが増えた」と回答するなど、健康意識の向上や体重減少といった具体的な成果が確認されています。さらに、同社はインテグリティ・ヘルスケアと共同で「生活習慣病管理 療養計画書作成支援プログラム」の提供を開始し、PHRを活用した医療機関での生活習慣病管理支援にも取り組んでいます。
(沢井製薬)飯塚市におけるPHRサービスを起点とした業種間連携型の健康なまちづくり形成に関する実証事業 結果のお知らせ
沢井製薬とインテグリティ・ヘルスケア 医療機関における生活習慣病管理を支援する「生活習慣病管理 療養計画書作成支援プログラム」をPHR管理プラットフォーム「Smart One Health」でサービス提供開始
第一三共は、早期乳がん患者を対象としたウェアラブルデバイス「Fitbit」によるPHR活用の臨床研究を開始。患者の身体活動量の変化と健康状態の関連性を評価し、将来的にはトータルケアプラットフォーム上でのデータ利活用を目指しています。この取り組みを通じて、患者の就労スケジュールやライフイベントの計画、仕事の配分、休息やサポート体制の確保など、より包括的な支援の実現を目指しています。
(第一三共)トータルケアエコシステムの構築に向けた、 早期乳がんを対象としたウェアラブルデバイスを用いた臨床研究の開始について
PHRの活用は、健康意識の向上から具体的な医療支援まで、幅広い領域で進展が見られました。今後は、蓄積されたデータの分析や活用を通じて、より個別化された医療サービスの提供や、予防医療の推進につながることが期待されます。
疾患啓発活動はより患者・生活者目線でアプローチが多様化
2024年の疾患啓発活動は、単なる情報提供の枠を超え、ゲーム、アート、体験型イベントなど多彩なアプローチを通じて、より深い理解と共感を促す取り組みが見られました。また、必要な情報へのアクセシビリティを向上させる実用的な取り組みも増えています。
GSKは日本での認知度が18%に留まるRSウイルス感染症について、世界初となる啓発週間を立ち上げ。また、帯状疱疹の啓発では異なる視点を持つ2名の俳優を起用し、基礎疾患のある患者や体験者など多様な立場からの理解促進を図りました。
RSウイルス感染症や予防法について正しく理解いただくための取り組み、GSK、世界で初めての「RSウイルス感染症啓発週間」
バイエル薬品は床一面に広がる特大ボードゲームで糖尿病を学ぶ体験型イベントを展開。ジョンソン・エンド・ジョンソンは20年以上続く「ハートアートプロジェクト」で統合失調症患者のアート作品を募集し、芸術を通じた相互理解を深めています。
糖尿病のキホンから合併症予防まで楽しく学ぼう:「体験型ボードゲームで学ぶ糖尿病と合併症 ~腎臓の声に耳を傾けよう~ in 丸の内」を11月7日(木)、8日(金)に開催
Johnson & Johnson、「第19回 ハートアートプロジェクト2024」を開催 統合失調症患者さんを支え、ノーマライゼーションを目指す
ファイザーは新型コロナワクチンに関する包括的な情報提供を展開しています。任意接種を希望する人向けに医療機関を検索できる情報サイトを開設したのに続き、各自治体から発信される定期接種に関する情報を一括で検索できるまとめサイト「新型コロナワクチン定期接種 自治体情報検索サイト」も立ち上げています。これまで自治体ごとに個別に探す必要があった接種時期、費用、接種可能な医療機関などの情報へのアクセスを効率化し、利用者の利便性向上を図っています。
新型コロナ感染状況を受け、ワクチン任意接種の医療機関情報検索サイトを開設 ~今、新型コロナワクチン接種を希望される方々を医療機関に繋ぎ、情報ニーズに対応~
ファイザー、新型コロナワクチン定期接種に関する自治体発信情報まとめサイト「新型コロナワクチン定期接種 自治体情報検索サイト」を開設 ~各地域のワクチン接種可能医療機関や接種費用などを簡易に検索できる情報ハブ~
顧客ニーズに対応した組織体制の改革とデジタル戦略の強化
製薬企業各社は、デジタル時代に対応した組織改革も積極的に進めています。
アステラス製薬は、「製品ごとの最適な営業モデルの構築」と「カスタマーエンゲージメントの強化」を目的とした新たな日本コマーシャルの組織体制を開始。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした新しい生活様式の浸透や医師の働き方改革など、環境変化に対応するため、6つのスタッフ機能と2つのセールス機能から構成される新体制を構築しました。
(アステラス製薬)新たな日本の営業組織について - 革新的な医薬品を待ち望む全ての患者さんに「価値」を提供し続けるために -
中外製薬は、PHC(個別化医療)ソリューションの開発から実用化戦略の立案および推進を目的に「PHCソリューションユニット」を新設。このユニットには、プログラム医療機器、体外診断用医薬品、コンパニオン診断、デジタルバイオマーカーなど、医薬品以外のソリューション開発機能を集約。また、デジタル戦略推進部のデジタルバイオマーカー開発に関する機能や、薬事部のデジタル・医療機器の薬事戦略に関する機能も統合し、ヘルスケアシステム全体における創出価値の最大化を目指しています。
(中外製薬)組織改正・人事のお知らせ
このような組織改革の背景には、医療のデジタル化の加速や、より個別化・高度化する医療ニーズへの対応、そして製薬企業の提供価値の変化があります。従来の医薬品提供中心のビジネスモデルから、デジタルソリューションを含む包括的な医療価値の提供へと転換を図る動きが、組織体制の面からも表れています。
製薬業界のDXは実用化フェーズへ
2024年の製薬業界は、デジタル技術を活用した医療支援の「実用化」が大きく進展した年となりました。デジタル治療アプリのFDA認可取得や、VR技術の医療現場での実践的な活用など、具体的な成果が表れ始めています。
また、PHRの活用やAI支援システムの開発など、データを活用した個別化医療への取り組みも本格化。疾患啓発においても、体験型コンテンツやアートなど多様なアプローチを通じて、より深い理解と共感を促す施策が展開されています。
さらに、製薬企業各社は組織改革を通じて、従来の医薬品提供中心のモデルから、デジタルソリューションを含む包括的な医療価値の提供へと転換を図っています。
2024年は製薬業界のDXが大きく前進した年と言えますが、今後は、これらの取り組みを通じて蓄積されたデータやノウハウを、いかに効果的に活用していくかが課題となっていきそうです。



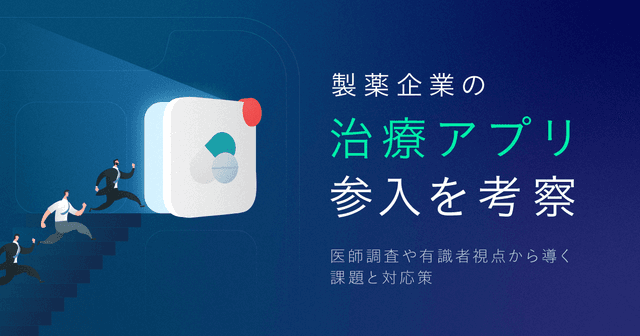
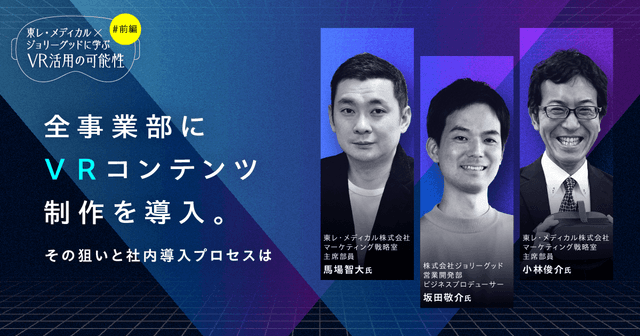


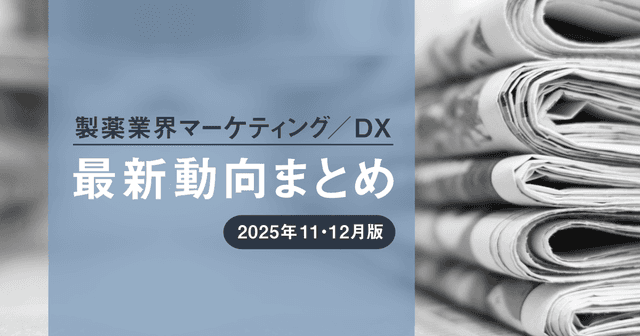
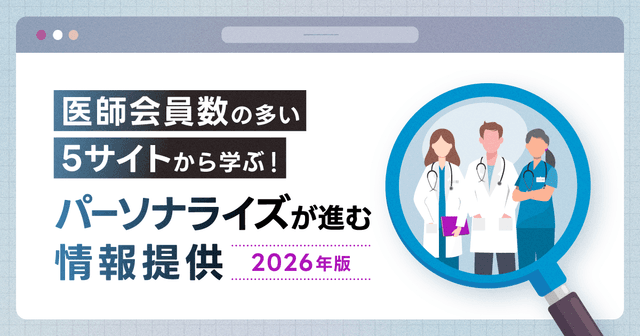

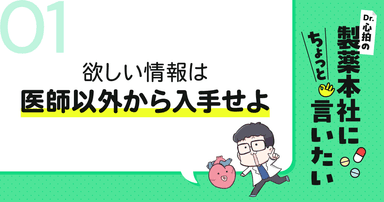
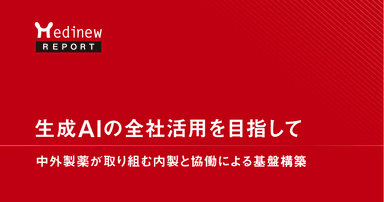




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



