約7割が「重要戦略」と回答。製薬企業オムニチャネル戦略の現在地

医師との接点が多様化する中、製薬企業ではオムニチャネル戦略が推進されています。その取り組みは実際にどの程度進展し、またどのような壁に直面しているのでしょうか。
製薬企業のオムニチャネル戦略の現在地を明らかにするべく、Medinewでは2025年2月、製薬企業のデジタルマーケティング部門や営業企画部門、プロダクト部門、メディカル部門などを対象に「製薬企業のオムニチャネル戦略に関する調査」を実施しました。
本記事ではその結果から、オムニチャネル戦略の推進状況と体制について概観します。
調査概要
- 調査期間:2025年2月20日~2月27日
- 調査対象:Medinew読者のうち、製薬企業に勤務するデジタルマーケティング部門、営業企画部門、プロダクト部門、メディカル部門など
- 回答者数:81名 ※途中離脱者も含む
- 調査方法:インターネット調査
▼調査結果の詳細レポートをダウンロードする
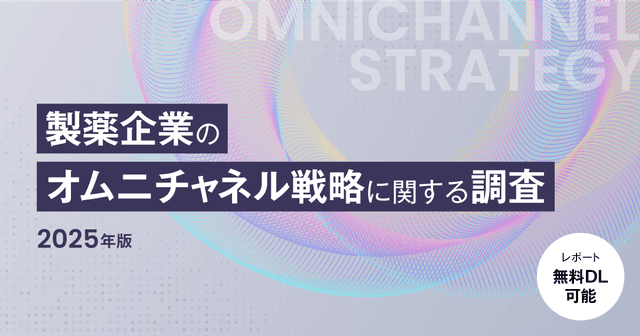
サマリー
- 全体の7割の企業がオムニチャネル戦略を重要戦略として推進しており、売上規模が大きい企業ほどその傾向が大きい
- 推進体制は最重要戦略とする企業の6割以上が専門部署やクロスファンクショナルチームを設置
- 主な目的は「MRがカバーできない医療関係者との接点作り」(66%)で、製薬業界におけるオムニチャネルはMR活動を補完・強化する位置づけとなっている
- 重視される成果は「営業生産性向上」(54%)が最多で、CX向上(51%)、データドリブンな意思決定(46%)が続く
約7割の企業が重要戦略として推進。大手企業ほど重要度が高い
製薬企業におけるオムニチャネル戦略の推進状況を調査したところ、全体の72%の企業が「重要戦略として推進している」と回答し、そのうち20%は「全社的な最重要戦略」として位置づけていることが明らかになりました。
企業規模別に見たところ、売上規模1,000億円以上の企業では約3割が「全社的な最重要戦略」としているのに対し、1,000億円未満の企業では約1割にとどまっており、大手企業ほどオムニチャネル戦略を重要視している傾向が浮き彫りになりました。
部門別では、デジタルマーケティング部門やプロダクトマーケティング部門において「最重要戦略」とする割合が高く、オムニチャネル戦略への意識・注力度が大きいことがうかがえます。
戦略の重要度の高い企業では組織体制の整備が進む
オムニチャネル戦略の推進体制については、戦略の重要度によって体制に明確な違いが見られます。
「全社的な最重要戦略」として推進している企業では、63%が専門部署やクロスファンクショナルチームを組織しており、戦略の重要度と組織体制の整備状況が連動していることが分かりました。一方、「重要戦略のひとつ」としている企業や導入初期の企業では主に既存組織で対応している傾向があります。
最重要戦略以外の企業では、「社内のリソースやスキル・知識の不足」を課題に感じている傾向が高く、人材不足が組織体制整備の障壁となっている可能性も考えられます。
目的はMR活動の補完・強化。部門ごとの認識の差も
オムニチャネル戦略の実施目的を調査したところ、「MR活動では十分にカバーできない医療関係者との接点を作る」(66%)が最も多く、次いで「医師のデジタル上での関心事項を把握し、MRの訪問活動に活かせる仕組みを構築する」(55%)、「医師が自身の働き方や好みに合わせて、使いやすいチャネルを選んで情報収集できる環境を実現する」(50%)となりました。
これらの結果から、オムニチャネル戦略はMR活動を代替するものではなく、MR活動をより効果的にするための補完・強化策として位置づけられていることが読み取れます。
主軸となる情報提供チャネルについても、全体の56%が「MR訪問」と回答しており、MRが依然として中核的な役割を担っていることが確認されました。ただし、デジタルマーケティング部門では「医療関係者向けWebサイト」(20%)や「Web講演会」(13%)を主軸とする割合も高く、部門による意識の差も見逃せないポイントです。
重視される成果は「営業生産性向上」
オムニチャネル戦略で重視される成果については、「営業生産性向上」(54%)が最多となり、「CX向上」(51%)、「データドリブンな意思決定」(46%)が続きました。
部門別に見ると、営業企画部門は営業生産性を、デジタルマーケティング部門はCX向上を、プロダクトマーケティング部門は両方を重視する傾向があり、各部門の役割や目標に応じて重視するポイントが異なることが分かりました。
オムニチャネル戦略を全社で推進するにあたり、部門ごとの認識のすり合わせが重要そうです。
領域別で異なる戦略の重点
領域別の分析では、各領域の傾向を比較するにあたりサンプル数の確保が難しかったため、領域の特性や対象となる医師層に共通点のある項目同士を統合し、3つのグループに分類して分析を行いました。
生活習慣病・感染症領域および中枢神経系・免疫炎症領域では、「MRのカバー」や「MR活動への活用」が主目的となっており、MRの補完機能を重視しています。
一方、希少疾患・オンコロジー領域では、「医師の情報収集体験の向上」への意識が強く、「チャネル選択の自由度」や「一貫したメッセージ提供」により重きが置かれています。また、この領域では主軸チャネルとしてMRを選択する割合が67%と他領域より高く、専門性の高い情報提供における対面コミュニケーションの重要性が示されています。
生活習慣病・感染症領域では比較的対象医師層が幅広い一方、希少疾患・オンコロジー領域では医師数は限定的で、かつより専門的かつ症例ベースでの情報提供が求められます。こうした違いが、オムニチャネル戦略に対する意識や重点の違いを生んでいると推測されます。
オムニチャネル戦略は一律ではなく、各領域の医師層や情報ニーズに応じてカスタマイズされたアプローチが重要となるでしょう。他社・他部門の成功例が自社・自部署にそのまま生かせるとも限らず、担当の製品特性、ターゲット医師の嗜好性や行動パターン、競合環境を十分に分析した上で、独自の戦略設計が求められます。
製薬企業のオムニチャネル戦略は、多くの企業で重要な戦略として位置づけられ、着実に推進されている一方、その実施にはまだ多くの課題が残されていることが明らかになりました。次回の記事では、オムニチャネル戦略推進における最大の課題の一つである「データ活用」の実態と、今後の取り組み課題について解説します。
「製薬企業のオムニチャネル戦略に関する調査 2025年版」のレポート資料をダウンロード
本記事で紹介したデータを含む資料「製薬企業のオムニチャネル戦略に関する調査 2025年版」は、以下ページより無料でダウンロードいただけます。
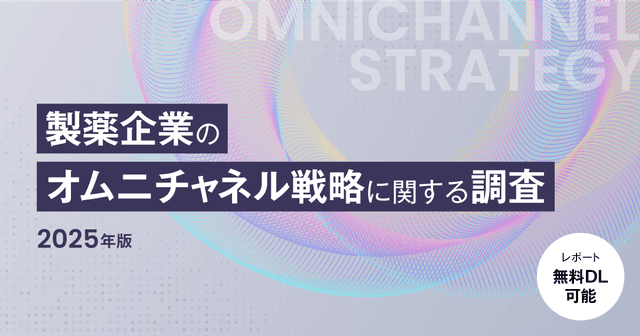


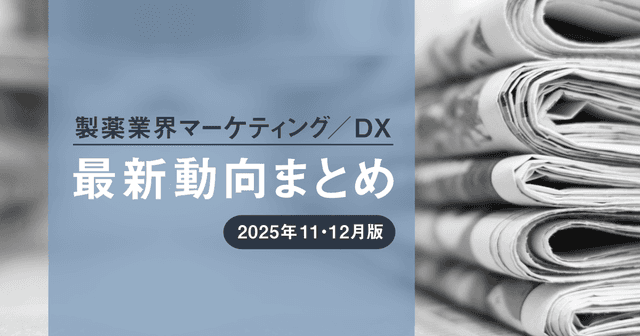
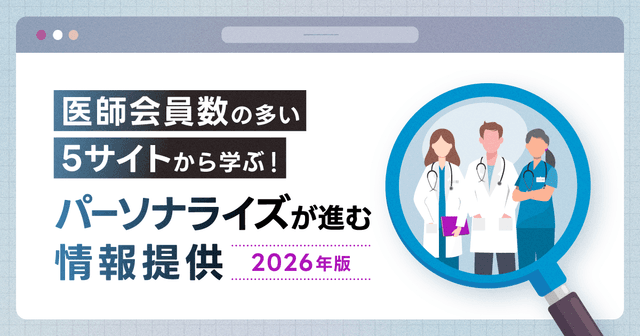


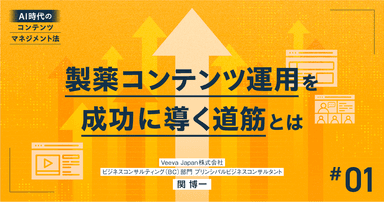




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



