医薬品市場でのCX創造のためのソーシャルリスニングとデザイン思考の応用|#1 ペイシェントセントリシティが改めて叫ばれる時代背景

この連載では、ソーシャルリスニングとデザインシンキングの思考法を繋ぎ合わせたプログラム「ペイシェント・リーダー®」を活用して製薬企業のマーケティングサポートに携わってきた経験をもとに、ペイシェント・セントリックな顧客体験(CX)を創造するための重要なプロセスを解説します。第1回は「ペイシェントセントリシティが改めて叫ばれる時代背景」がテーマです。
(トランサージュ株式会社 代表取締役 瀧口 慎太郎)
はじめに
製薬企業の方々に向け「ソーシャルリスニングとは…」とお話しすると「聴いたことはあるけど使ったことはない」という方がまだかなり多いのが事実です。「デザインシンキングでは…」とお話しすると「このあいだ会社で研修を受けました」という反応が少し増えています。しかし、まだ実務に活用している方は少ないという印象です。弊社では、ソーシャルリスニングとデザインシンキングの両方を繋ぎ合わせたプログラムとして『ペイシェント・リーダー®』を開発し、この2つを積極的に利用しています。今回の連載では、このペイシェントリーダー®での数々のプロジェクト経験を元に、ソーシャルリスニングとデザイン思考で“ペイシェントセントリシティ”な顧客体験(CX)にどう繋げられるのか、ブランド戦略にどう活用できるのか、などについてお話ししたいと思います。
【連載第1回】 ペイシェントセントリシティが改めて叫ばれる時代背景
医療の世界において、医師は確たる医療倫理を持って患者に接するべきという考え方は、洋の東西を問わず存在します。最も古くはヒポクラテスの誓い、そしてわが国では緒方洪庵や杉田玄白といった医学の先達の著書にも描かれています。
とはいえ現代の医療ではそうした先達が活躍した時代と大きく異なり、ひとりの医師がひとりの患者を見る時間は限られ、手で患部付近に触れて治す手当て(ハンドヒーリング)のような、一面からは非科学的で時間のかかる医療や個々の医師の経験に基づく属人的医療は敬遠され、EBMを基本とする標準的な治療が最も客観的で賢明な治療法として用いられるように変遷しました。こうした変遷はもちろん医療の高品質化に役立ったことは間違いありませんが、一方で患者視点からは現代の医療の持つ課題にも繋がっています。だからこそ患者中心の医療が改めて脚光を浴び、いかに実現するかが模索されるようになったと考えられます。
そこで、第1回の今回はまず「患者中心の医療」が再び脚光を浴びている背景のいくつかについて触れ、その意味を探ってみたいと思います。
製薬産業の領域シフトとEvidence Based Medicineの限界
1991年にカナダのガイアット医師が提唱した根拠に基づく医療(EBM:Evidence Based Medicine)は、質の高い医療を求める社会的な意識の高まりとともに普及しました1)。EBMはそれまでの主観的で経験的な医療から客観的で論理的な医療への大転換をもたらしましたが、必ずしも「完璧」と言えない部分もあります。例えば、EBMのベースとなる疫学スタディの組み入れ症例はプロトコールで決められているため、実臨床上の患者像と異なる場合も少なくありません。
また製薬企業の開発品に目を転じると、循環器など慢性疾患のブロックバスターが絢爛と輝いていた1990年代や2000年代から時を経たいま、その興味はオンコロジーや免疫疾患などのより難治性が高く、相対的に限られた患者数の領域に向かっています。この製品開発領域のシフトは、科学的根拠にしたがって綿密に組み立てられた標準的治療による個々の患者の治療成果の違いをクローズアップします。言い換えると、従来のEBMの考え方だけでは解決し得ない症例との遭遇事例が増えることになります。
例えば、あるがん治療のための化学療法の選択肢は、標準的なレジメンや標準薬のブランドを合わせると数十種類以上に及ぶことは少なくありません。これは、そのがん患者の遺伝子や育成環境や治療経過などさまざまな背景要因によって、同じレジメンあるいは薬剤でも治療効果が異なるからに違いありません。こうした事実から、EBMによる医療をもとに、さらに高みを目指した「個別医療」あるいは「プレシジョンメディスン」と言われる、患者個々を見つめる医療にシフトを図ろうとしています。
元ハーバード大学医学部教授のグループマン博士はその著書で「医薬品や治療に関する医師個人の経験に基づく知恵 - 臨床試験の成績から得られたベストの治療法が、その患者のニーズや価値観に適合するかどうかを判断する医師個人の知識 - に対し、数字は補足的な役割でしかない」と著書で述べています2)。つまり、EBMのような客観的な事実に基づくベストな治療法から患者をこぼれ落とさないためには、患者のニーズや価値観も含めて治療法を考えることが重要になる時代に足を踏み入れている、と考えることができます。
インターネットとSNSの登場で医療情報の偏在性が解消
2000年代に入ってインターネットが急速に普及するにつれ、医療従事者だけが入手できていたような詳細な医療関連情報を一般人も簡単に入手できるようになりました。もちろん入手した情報を料理するためにはそれ相応の知識(ナレッジ)が必要になるため、同量の情報を入手できても一般人である患者が医師と同様に理解して判断材料に利用することは難しいですが、少なくとも両者が同量の情報に時を同じくして触れることができるようになったことで、医師が患者に対して情報の有無を偽ることはできません。
また、インターネットに遅れて登場したソーシャルメディアでは、あることに興味を持つもの同士を惹きつけると同時に、ひとつのトピックスについてさまざまな人たちの意見が境界を超えて同時代的に交わすことができるようになりました。医療のような難しいトピックスでもその情報に非常に詳しい人による分かりやすい解説が共有される機会も増え、ソーシャルメディア利用者の誰しもがそれなりに理解することができるようになりました。こうした動向により、ソーシャルメディアは、それまではある意味で蚊帳の外だった患者にも、専門的なナレッジ習得の後押しとなっている面があります。
生成AIなどのテクノロジーのさらなる進歩により、さまざまな自覚症状から考えられる疾患候補名が分かるアプリはすでに登場しています。この先、洗面所の鏡に毎朝写る自分の顔や舌の色や便尿の成分の変化などで「病院へ行きましょう」とウォーニングが言い渡される、といったSF小説風な未来がきても不思議ではなく、これからますます医師と患者の間の情報格差を狭める方向に働くことは明らかです。
こうした医療情報の偏在性の解消は、旧来的なパターナリズムからシェアード・ディシジョン・メイキングのような医師と患者が同列に判断を下すプロセスへの移行と相まって、患者中心主義を促進する要素に他なりません。
ウェルビーイングへの認識のシフトと医師患者間の病気への認識ギャップ
今世紀に入って注目され始めた概念に「ウェルビーイング」というものがあります。WHO憲章前文に『健康とは病気ではないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも、そして社会的にもすべてが満たされた状態にあることをいう』と記載があり、一般にはこの状態、つまり幸福で肉体的、精神的、社会的すべてにおいて満たされた状態がウェルビーングであると理解されています。
ウェルビーングと対比すると医療が取り扱う範囲の限定性に気付かされます。つまり、医療の対象は肉体(身体)の健康が中心で、精神の健康がその対象に少し入る程度に限定されます。ここで「精神が少し」というのは、疾患としての精神的な障害だけが医療の対象で、ウェルビーングで取り上げる精神はより広義なためです。
2021年に政府が発表した成長戦略実行計画でも「国民がWell-beingを実感できる社会の実現」を目指すことが明記されたほか、世界の共通運動であるSDGsでのゴールの一つに「すべての人に健康とウェルビーングを(GOOD HEALTH AND WELL-BEING)」とされています。このウェルビーングに注目が集まってきた背景には、大量消費時代の終焉による「モノから心の豊かさ」への価値観の移行や、コロナ禍を経たことによる「自分らしさ」や「働き方」への関心の高まりなどがあると言われます3)。
ただ、世の中でいかにこうした認識へ注目が集まろうとも、医療は身体が中心であり、精神や社会をも含む痛みに対応する方向に船首を向けることは易々とはできません。ここに医療人類学が提起した医師と患者の病気に対する捉え方の差異を当てはめると合点がいきます。それによれば、人間が経験する病気は「病い(illness)」「疾病(disease)」「病気(sickness)」の3つの類型があり、病気の認識に対しては必ず医師と患者の間にズレがあるのです。「病い」とは患者が経験する病気に関連するすべての物語(ナラティブ)、「疾病」は医師がその責任範囲として興味の対象とする生物学的実体としての病苦、「病気」は病いと疾病をともに含む包括的な概念という考え方です4)。
この医療人類学で語る病気の類型を頭に入れると、昔ながらの赤髭先生ならまだしも、多忙を極める現代の医師が患者の考える「病い」の側面に立ち入る事は相当難しそうなことは容易に想像できます。
ただ、だからこそウェルビーングが求められる現代において、あえて患者中心主義を唱え、より幅広い視野で患者を理解することが求められているとも考えられます。
決して目を背けることができないペイシェントセントリシティへの趨勢
上記の3点以外にも、ペイシェントセントリシティがいま改めて脚光を浴びている理由は存在するでしょう。ただ、これらの背景を振り返るだけでも「患者中心主義は単なる掛け声では終わらないであろうこと」そして「これからは従来から慣れ親しんだプロセスや手順を繰り返すことで持続的な成長や高品質化を得られるわけではなく、新しい視点や考え方による実践が必要だ」ということを十分に理解できるのではないでしょうか。
こうして医療が患者中心主義にシフトしているという現実は、医薬品産業においても絶対に目を逸らすことができない現実です。「医薬品産業が医師と手を携えてペイシェントセントリシティをしっかりと実現するために新しい歩みを進めることが必要だ」ということは決して忘れてはならない事実だと考えます。
参照文献
1) 福井次矢, 日本内科学会雑誌 Vol.99 No.12 Editorial 2010年刊, 『エビデンスに基づく診療ガイドライン』
2) ジェローム・グループマン, 石風社, 2011年刊, 『医師は現場でどう考えるか』
3) 講談社, SDGsウェブ版, 2023年6月30日, 【2023年版】ウェルビーイングとは?いま注目される理由と、SDGsや経営の視点からみた重要性|SDGsにまつわる重要キーワード解説
(https://sdgs.kodansha.co.jp/news/knowledge/40247/)
4) アーサー・クライマン, 誠信書房, 1996年刊, 『病いの語り:慢性の病いをめぐる臨床人類学』
トランサージュ株式会社
『Patient Centricを礎に“マーケティング・エクセレンス”をデザインし、より高品質なヘルスケアの実現に寄与する』をモットーとして、ヘルスケア企業向けにコンサルティング/ビジネスリサーチ/トレーニングを提供。

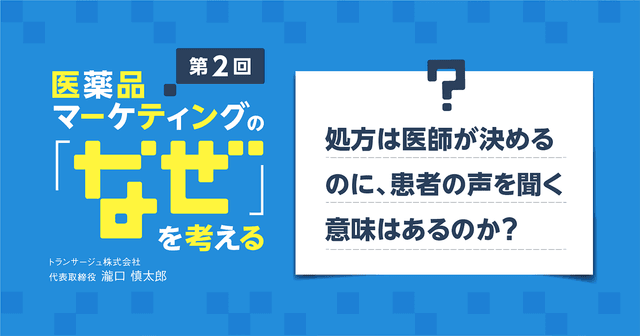



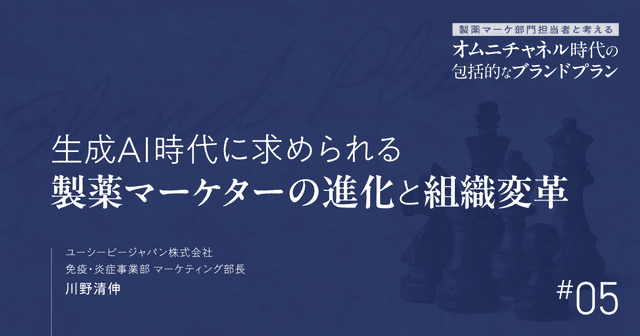
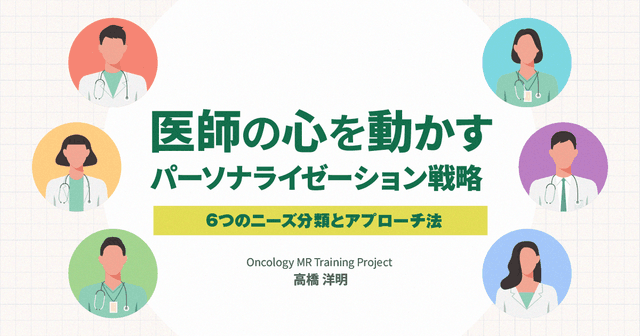







.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



