新薬処方「積極派」医師は2割。その特徴は?
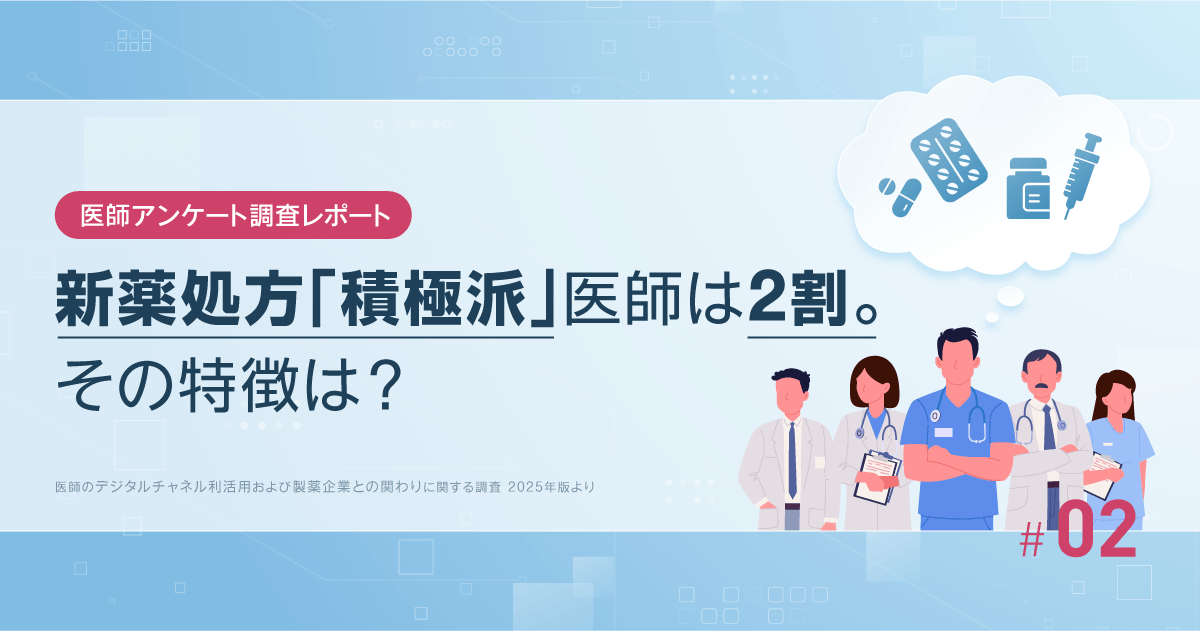
医師の勤怠管理の厳格化が進み、勤務時間を何のために使うのかの取捨選択を迫られる中で、診療、会議、雑務、情報収集、自己研鑽-何を選び取るかは、医師の診療のスタンスによっても変わると考えられます。
Medinewでは2025年2月、医師を対象として、医師の働き方改革に伴う勤務環境や情報収集行動の変化に関するアンケート調査を実施しました。
本記事ではその結果の中から、新薬処方への積極性で医師をタイプ分類し、各タイプの情報収集行動や情報提供ニーズの違いを分析した結果について紹介します。
調査概要
医師250名を対象に実施した本アンケートでは、医師の働き方改革後の業務時間の実態および情報収集行動の変化、情報収集チャネル、特に製薬企業チャネルやデジタルチャネルの利用実態、製薬企業からの情報提供へのニーズなどについて調査を行いました。
サマリー
- 新薬が出たら早期から処方採用を考える”積極派”は、医師の約2割。勤務時間が長く、400床以上の大規模病院勤務が多い傾向。学会や勉強会、MRとの面会などの自己研鑽の時間を確保する意識が比較的高い
- 新薬処方”積極派”の医師は、製薬企業チャネルをより重視する傾向があり、MRに対し処方経験のない薬剤の情報ニーズが高いことが特徴。医療関係者向けサイトには広範囲な情報を求めるほか、機能充実によるシームレスな情報収集を望んでいる
- 新薬はある程度の情報が出てくるのを待ってから処方したい“準積極派”は、医師の4割超を占める多数派。自己研鑽の時間減少が顕著
- 新薬処方”準積極派”の医師は、書籍などのニュートラルな情報源をより重視する傾向。MRに対し安全性情報を求めるなど、情報に対しても慎重な姿勢
医師の新薬処方態度をタイプ分類
Medinewでは今回の医師アンケート調査で、新薬処方の積極性に基づいて医師をタイプ分類することを試みました。
エベレット・ロジャーズが提唱したマーケティング理論である「イノベーション普及理論(Diffusion of Innovations)」では、新しい製品やアイディアが社会に広まる過程において、それらを採用しようとする人の態度は以下の5タイプに分類できるとされています。
- イノベーター:革新に敏感な最初の2.5%。リスクを恐れず新しいものを試す層
- アーリーアダプター:13.5%。流行に敏感で他者に影響を与える層
- アーリーマジョリティ:34%。周囲の評判を見て採用を決める層
- レイトマジョリティ:34%。大勢が使っていれば導入を考える層
- ラガード:最後の16%。新しいものには消極的な層
また、同理論から派生して、「アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には普及の溝(キャズム)があり、ここを超えられるか否かが新しい製品の普及の分水嶺になる」というキャズム理論も知られています。
そこで、医師の新薬処方の積極性についても同様のタイプ分類を行うべく、アンケート調査の最終設問で「先生の専門領域の新薬が発売される際、先生が最もよくとる行動を教えてください」との設問に対し5段階の回答選択肢を提示したところ、以下のような結果が得られました。
これらの選択肢は本調査のために考案したものであり、質問票としての精度には検証の余地もありますが、その分布は、イノベーション普及理論で提唱された分布と概ね一致していました。
そこで、これらの新薬処方態度に関する回答から、新薬の上市直後からの局面で重要なターゲットになるであろう処方”積極派”(イノベーター+アーリーアダプター)22%、後々の追い上げに寄与するであろう処方”準積極派”(アーリーマジョリティ)42%、薬剤がポジションを確保してからでなければ処方しないであろう”消極派”(レイトマジョリティ+ラガード)36%に医師をタイプ分類し、各タイプの特徴を分析しました。
新薬処方“積極派”は大規模病医院勤務、中堅・若手が多い
製薬企業にとって、積極的にアプローチしていきたいターゲットだと考えられる新薬処方”積極派”の医師の特性を紹介します。
勤務時間は、医師全体では働き方改革の前後ともに平均47時間台/週でしたが、”積極派”の勤務時間はそれよりも約5時間長く、平均52時間台/週に達しました。一方、”準積極派”は47時間台/週、”消極派”では43時間台/週と、新薬に積極的な医師ほど勤務時間が長い傾向が見られました。
また、400床以上の大規模病院勤務の割合も、新薬に積極的な医師ほど高い傾向が見られました。
年代の分析では、50代以下の中堅・若手の割合が、”積極派”(85%)で”準積極派”(70%)よりも高い傾向が見られました。一方で、”消極派”でも中堅・若手の割合は82%と比較的高く、新薬処方への積極性と年齢層には、必ずしも一貫した傾向は見られないことも分かりました。
新薬処方“積極派”は自己研鑽の時間減少が少なく、製薬チャネルを重視
新薬処方態度のタイプ別に、情報収集行動の特徴を調べた分析の結果は以下の通りです。
今回の医師アンケート調査では、全体的に「勉強会」「学会」に参加する時間が減少したと答えた医師が多かったものの、新薬”積極派”ではそうした医師が比較的少なく、一方で”準積極派”では医師平均以上に勉強会や学会への参加が減っていることが明らかになりました。加えて、「MR/MSL面談」の時間が減った医師の割合も、”準積極派”(40%)は”積極派”(24%)より高いという違いが見られました。
新薬に対し、情報がある程度出てきたら使ってみたいと考えている”準積極派”の医師は、働き方改革によって学習や情報収集にかける時間が顕著に減少しているグループといえるでしょう。本当はもっと自己研鑽に時間をかけたいが、やむを得ず減らしており、課題感を抱えている医師もいるかもしれません。
他方で、新薬処方”積極派”の医師は、勤務時間に制約を設けられる時代の潮流の中でも、MR面談を含め、自己研鑽の時間を確保したい意識があると伺えます。ただ、”積極派”では、総勤務時間の平均値は増えていないにもかかわらず、全体的に各業務の時間が増えた医師の割合が比較的高くなっています。一部の医師ではより多くの業務を勤務時間内に詰め込み、主観的な業務負荷が高まっている印象も見受けられました。
情報チャネル別の重視度を尋ねた設問では、医師全体の結果として、他の医師との情報交換などのDtoDチャネルや、書籍・学会などのニュートラルなチャネルを重視するという傾向が見られました。
しかしその中でも、新薬処方”積極派”は、他のタイプの医師に比べると、「MR」「製薬企業医療関係者向けサイト」などの製薬企業チャネルを突出して重用している傾向が明らかになりました。新薬処方”積極派”に占めるMR重視は67%、製薬企業講演会重視は65%で、医師向けメディアの73%に追随しています。新薬に積極的であることから、薬剤の最新情報の入手先として重視していると考えられます。
一方、準積極派は「書籍、専門誌」「学会」「論文情報」などのニュートラルな情報源をより好んでいました。
新薬処方“積極派”と“準積極派”ではMRに求める薬剤情報の焦点が異なる
製薬企業チャネルに求める情報ニーズにも、新薬処方態度のタイプによって一部明確な違いが見られました。
医師全体の傾向として、製薬企業チャネルに対しては「薬剤情報」を、ニュートラルな情報源や医師向けメディアに対しては「診療の最新トレンド」を主に求めており、これは”積極派”でも”準積極派”でも変わらず認められる傾向でした。
ただ、それに加えて、MRに対する情報ニーズとして、”積極派”は「処方経験のない薬剤の情報」を、”準積極派”は「新薬情報」「安全性情報」を求めていました。これは、”積極派”と”準積極派”の薬剤へのスタンスの差、そこから来る興味関心の焦点の違いがくっきりと出た結果と言えそうです。
製薬企業の医療関係者向けサイトが提供すべきことを尋ねた設問では、半数を超える医師が求めている、いわば「必須」のコンテンツ・機能については、”積極派””準積極派”問わず同様に票が集まっており、その順位・割合にほとんど差はありませんでした。
一方、医師全体では求めている人が半数未満であるコンテンツ・機能については、”積極派”の方が”準積極派”よりも求めている人の割合がそれぞれ1割以上多いという結果になりました。
例えば、「動画コンテンツの充実」を望む人は”積極派”55%に対し”準積極派”42%であり、「Web講演会カレンダーの設置」は同44%、31%、「サイト経由でMRと連絡」は38%、29%、「サイト経由でメディカル担当者と連絡」は40%、27%。新薬”積極派”の医師は平均的な医師に比べて、情報や機能の拡充によるチャネル間のシームレスな情報収集を望んでいるようです。
「医師のデジタルチャネル利活用および製薬企業との関わりに関する調査 2025年版」レポート資料をダウンロード
本記事で紹介したデータを含む「医師のデジタルチャネル利活用および製薬企業との関わりに関する調査 2025年版」のフルレポートは、以下ページより無料でダウンロードいただけます。医師全体の調査結果はもちろん、新薬処方“積極派”“準積極派”それぞれの製薬企業チャネルに対するニーズの詳細な分析や、外科内科それぞれの製薬企業チャネルの選好・ニーズも掲載しています。ぜひご覧ください。
※資料の無断引用・転載はお断りいたします。
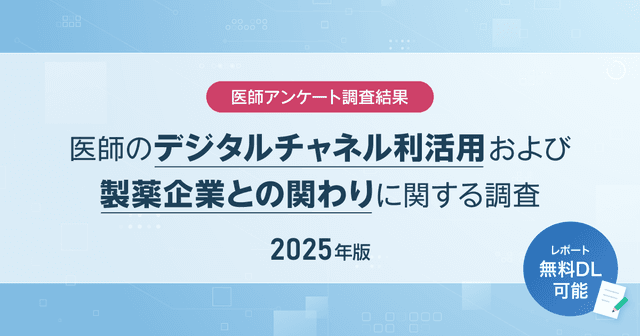
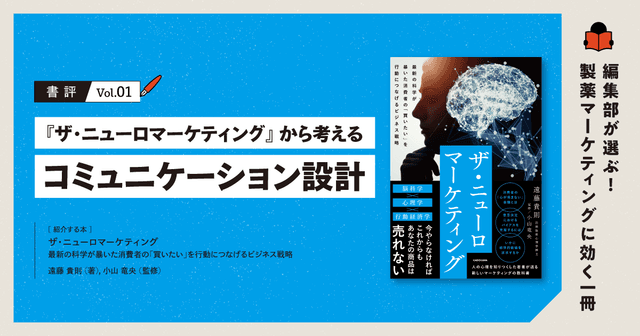
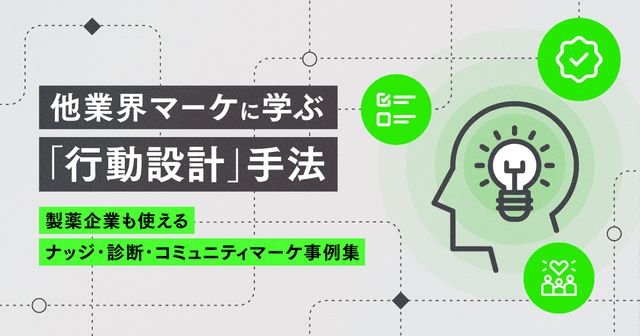




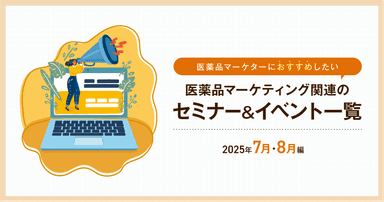




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



