登壇医師に聞く、「良い講演会」の作り方|医師の本音を聞く2025
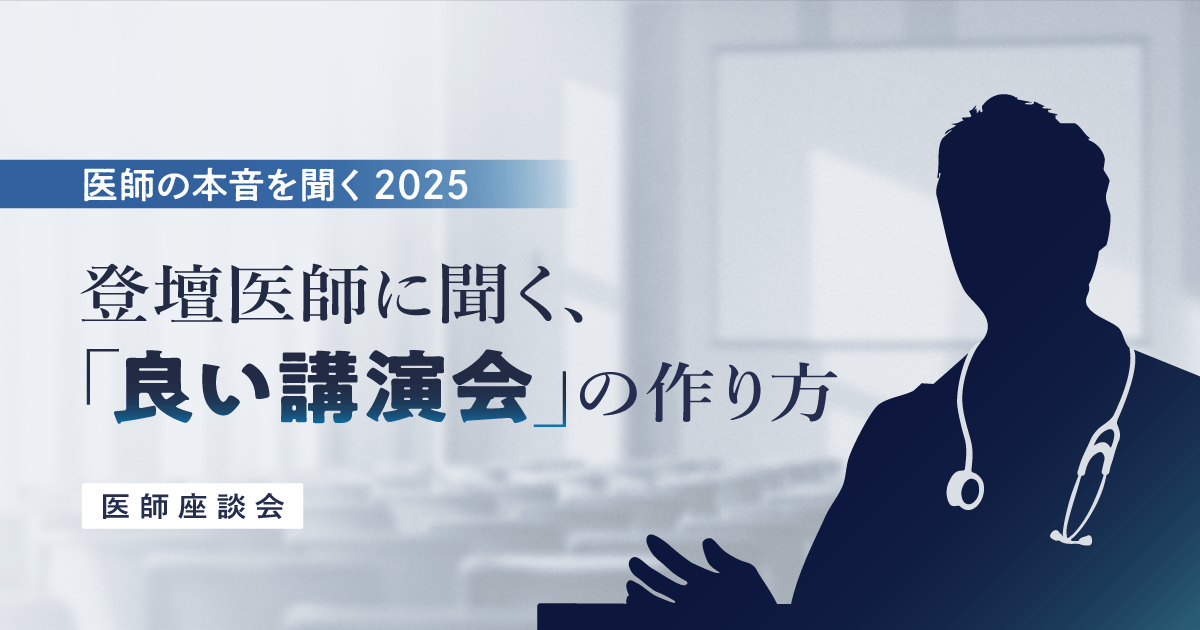
製薬企業の講演会は、テーマや設計の切り口が年々多様化し、開催形式もリアル・オンライン・ハイブリッドと選択肢が広がっています。このような変化の中で講演会の質を高めるためには、登壇医師を単なる「話し手」ではなく「講演会を共につくるパートナー」と捉え、話しやすい環境を整えることが重要となります。そこで本記事では、登壇経験豊富な3名の医師に、主催者に求める工夫や理想の講演会のあり方を聞きました。
座談会参加医師
A医師:関西圏の大学病院に勤務。50代。呼吸器外科に所属。主な所属学会は日本外科学会、日本小児外科学会、日本呼吸器外科学会、日本肺癌学会。製薬企業主催の講演会には年間3、4回程度登壇。
B医師:関東圏の大学病院に勤務。30代。リウマチ・膠原病内科、感染症科に所属。主な所属学会は、日本リウマチ学会、日本感染症学会。製薬企業主催の講演会には年間3、4回程度登壇。
C医師:関東圏の市中病院(地域の基幹病院)に勤務。40代。呼吸器内科に所属。所属学会は日本内科学会、日本呼吸器学会、日本感染症学会、日本アレルギー学会、日本肺癌学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本結核・非結核性抗酸菌症学会など。製薬企業主催の講演会には年間3、4回程度登壇。
登壇して良かったのは、「自らの学び」につながる講演会
――これまでさまざまな講演会に登壇されてきたとのことですが、「登壇して良かったと感じた講演会」の特徴を教えてください。
A医師:自分以外に複数の登壇者がいる講演会ですね。特に隣接領域の医師と登壇できると新たな視点を得られて自分の学びも深まり、「お得感」があります。たとえば、自分は呼吸器外科ですが、呼吸器内科の医師と登壇すると非常に勉強になりますね。
B医師:私も、他診療科の医師との講演会に大きな意義を感じます。たとえば、自分はリウマチ・膠原病内科ですが、皮膚科や整形外科の医師と登壇できた際、とある疾患の薬剤選択について「関節のことを考えるとこの薬がいいけど、皮膚のことを考えるとこの薬が良いかもしれない」というような議論ができました。また、多様な診療科の登壇医師が集まれば、おのずと参加医師の診療科も多様になり、診療科同士のシナジーが生まれやすいと考えています。
C医師:私は、話し上手な医師が登壇する講演会に好印象を持っています。切り口が多様化する中、レクチャーが得意な医師はどのテーマでも深い話を展開してくれるので、そのような医師と登壇できる機会は前向きに検討します。また、互いに自由にディスカッションしながら、教科書に載っていない実践の工夫を知れる「症例勉強会」のような場も貴重ですね。
――逆に登壇する意味をあまり感じられなかったものはありますか。
A医師:先ほどの裏返しですが、自分一人の登壇だと一方通行になりがちで、純粋な「仕事」として終わってしまう印象があります。特に平日の昼や夜に行われる講演会は、質疑応答があまり盛り上がりません。自分より年下の医師たちは、立場的に質問が難しいと感じているのかもしれませんが、講演の手応えや新たな学びがなかなか得られないのが残念です。
B医師:私は登壇を通じて自分も学べると考えているので、「登壇する意味がなかった」と感じたことはありませんね。疾患や治療、研究内容について、人に伝える準備をする中で、自分の学びも整理できています。
C医師:製薬企業の広告塔のような医師が登壇する講演会には、それほど惹かれません。内容や切り口が月並みになりがちですし、学びが少ないと感じます。
――講演会を聴くときと同じように、「自らの学びにつながるか」という観点を重視して登壇していらっしゃるのですね。
良い講演会にするために、企画趣旨を事前に明示してほしい
――講演会を良いものにするために、製薬企業にはどのようなことを期待していますか。
A医師:登壇医師や座長の座組みを予め知らせてほしいです。折り合いの合わない医師と登壇する場合、たとえ喧嘩はせずとも、議論がほとんど盛り上がらないという結果になりかねません。登壇メンバーだけでも、講演依頼の前に教えてもらえると助かります。
また、講演会を聴く側の満足度を上げるには、講演会の焦点や切り口を明示して集客すべきだと考えます。「〇〇について解説」という包括的な説明だけで多くの参加者を集めても、結局は「想像していた内容と違った」とがっかりさせてしまいかねません。登壇する側としては、あまり早い段階での抄録提出は負担にはなるのですが。
B医師:講演会に参加する医師層を事前に教えてほしいですね。自分と同じ専門領域の医師だけなのか、他診療科の医師も含まれるのか。病院に勤務する医師なのか、クリニックを開業している医師なのか。それによって講演の内容や深さを調整する必要があるからです。
もう一つお願いしたいのが、やり取りの効率化です。綿密な打ち合わせは大切ですが、時間がなく、アポイントを取って話すのが難しいこともあります。要件はまとめて相談する、内容によってはメールで済ませるといった柔軟な対応をしてもらえると助かります。
C医師:ターゲットの医師層と、彼らの情報ニーズを教えてほしいです。先ほど言及したように、今では各製薬企業が工夫してさまざまな切り口の講演会を企画しているように思いますが、前例がない場合、どのようなレベル感でどのように話せばいいのか判断が難しい。ターゲットにより響く講演内容にするために、サポートしてくれると嬉しいですね。
また、条件面も事前に明示してもらいたいです。以前、断りづらいタイミングで予想より大幅に低い報酬を提示されたことがあり、それ以来、その製薬企業からの依頼は受けていません。条件面の話はしづらい雰囲気がありますが、私はあえて自分から聞くようにしています。製薬企業側も、最初の段階で条件を提示する姿勢を持ってほしいですね。
――登壇医師として「自分だけでなく他人にとっても学びのある講演会にしたい」という思いがあるからこそ、製薬企業には登壇の座組みやターゲット層、情報ニーズの共有が求められるのですね。同時に、双方が気持ちよく仕事をするためには、効率的なやり取りや条件の明示が不可欠だとわかりました。
登壇医師にとってのリアルとオンラインの違い。リアルでは関係構築重視
――近年、講演会の形態も多様化していますが、登壇するにあたり意識するポイントに違いはありますか。
A医師:リアルかオンラインかで、講演内容、緊張度合いやプレッシャーなど、いずれもそれほど変わりませんね。
B医師:同じく私も、発表内容自体はほとんど変えていませんが、スライドの作り方は変えた方がいいかもしれないと考えています。オンラインでは情報量の多いスライドでも許容されますが、対面であれば遠くから見る人がいることも想定し、字を大きくしたり、図やイラストを多く使ったりした方が分かりやすいはずです。
C医師:製薬企業主催のオンライン講演会の経験はほぼないのですが、オンラインで学会発表を行う際は、時間通りの進行をいつも以上に心がけていますね。
――登壇医師としての、リアル・オンライン講演会のメリット・デメリットを教えてください。
A医師:時間的制約という観点でいうと、オンライン講演会の方がメリットが大きいです。リアルの場合、会場への移動時間などを含めると拘束時間は長くなりますし、タクシー移動がほとんどなので、とにかく遅刻が心配です。その点、自宅や勤務先などから参加できるオンライン講演会の場合は、移動時間もかかりませんし、遅刻のリスクも低いと感じます。
ただ、オンライン講演会には、他の登壇医師や座長との交流という「プラスアルファ」のメリットがありません。タイミングや相手の反応を図りにくいためか、質問が出にくく、質疑応答もなかなか盛り上がらない。そのため、講演会の内容が自分の興味に明らかに沿っている場合や、知り合いの医師が登壇したり座長を務めたりする場合は、たとえ時間的制約があってもリアル講演会を選びます。
B医師:私は、オンライン講演会でも、自宅や勤務先ではなく特定の会場から配信するものしか参加したことがないので、時間的制約の違いを意識したことはほとんどありません。
他の医師との交流面については、むしろオンラインだからこそ、リアルでは関わりを持てない医師とやり取りできる側面もあると考えています。たとえば、オンラインなら遠方の医師と同じ講演会に登壇できますし、匿名だからこそ参加医師が鋭い質問を投げかけてくれるのも事実。リアル講演会の質疑応答では生まれない、新たな知見を提供できる可能性があると感じます。
とはいえ、オンラインの講演会だと画面オフで参加している医師が多く、反応がわからないので登壇医師としては不安になります。その点、リアルの講演会は参加医師の反応がわかりやすいですし、懇親会があるのも大きなメリットです。講演では話しづらいリアルな診療チップスを得られますし、私自身、懇親会で得たつながりが共同研究につながったこともあります。
C医師:先ほどお話ししたように、私は製薬企業主催のオンライン講演会への登壇経験はほぼありませんが、オンラインだと時間や場所に縛られず、柔軟に聴いてもらいやすいのがメリットだと考えています。参加医師にとっては、全編に出席せずとも必要な部分だけスポットで聴くことができますし、別の作業をしながら情報収集することも可能ですから。
一方、オンラインの講演会だと気軽に質問がしづらいためか、盛り上がらないまま淡々と終わっていくイメージがあります。たとえチャット上の質問からやり取りが始まっても、そのチャットルームは時間が来れば閉じられるので、その場限りの関わりになってしまうでしょう。リアル講演会では、著名な医師ともざっくばらんに話す機会が得られ、継続的な関係を構築できる可能性があるのが大きなメリットだと考えています。
――発表姿勢に大きな違いはないものの、それぞれにメリット・デメリットがあり、目的に応じた使い分けが求められるということですね。特に他の医師との関係構築においては、リアル講演会に価値を感じていらっしゃることがわかりました。
登壇医師と参加医師、双方にとって「学び」のある講演会にするために
今回の座談会を通じて、登壇医師が重視するのは「自らの学びにつながる」講演会であることが明らかになりました。
具体的には、隣接領域や異なる診療科の医師との登壇により新たな視点が得られること、症例勉強会など実践的な議論ができることに価値を感じていました。一方で、一人での登壇や画一的な内容の講演会では、学びが限定的になることも指摘されました。
同時に、登壇医師には「他人にとっても学びになる講演会にしたい」という思いもあり、製薬企業にはその実現を支えるサポートが期待されています。講演会の趣旨やターゲットを明確に伝え、フィードバックすることで信頼構築につながるでしょう。
開催形式だけで登壇意欲が左右されるわけではなさそうですが、リアル講演会は医師同士の交流や関係構築に、オンライン講演会は時間的制約の軽減や地理的制約の解消に、それぞれ強みがあります。講演会の目的に応じた最適な形式選択が重要です。
医師が「登壇してよかった」と感じる講演会は、参加医師の満足度にもつながるはずです。登壇医師の声に耳を傾け、これらの要素を取り入れることで、より価値のある講演会を実現していきましょう。
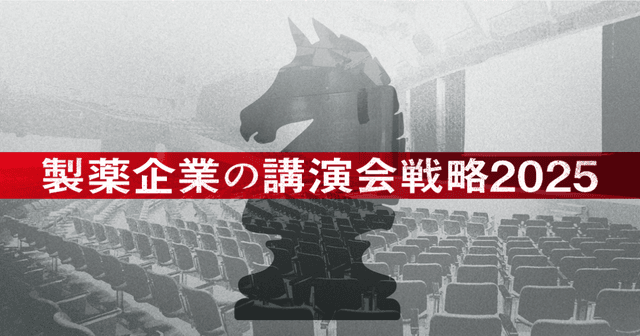
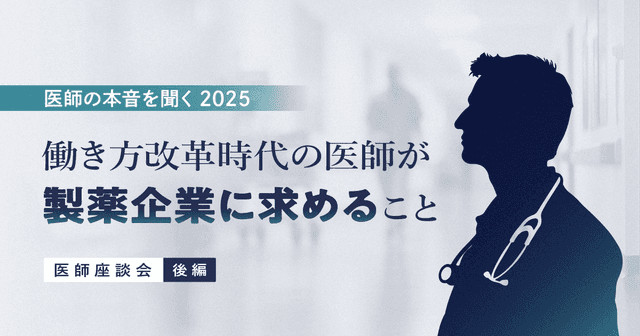
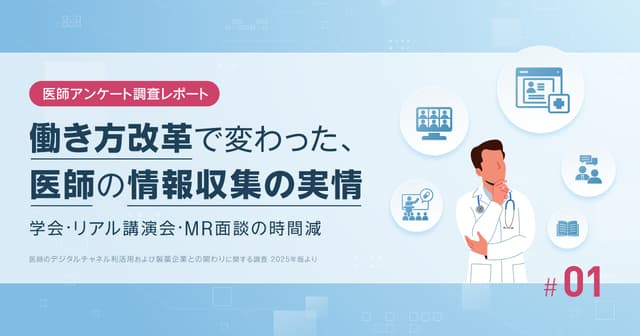
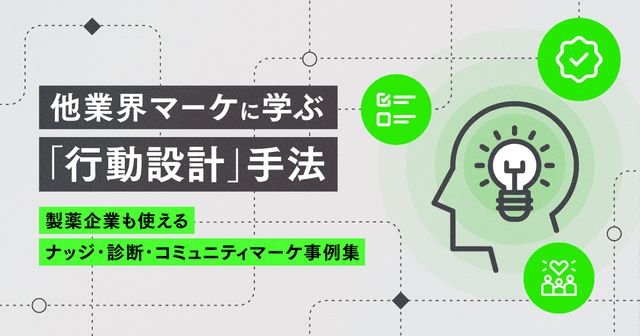


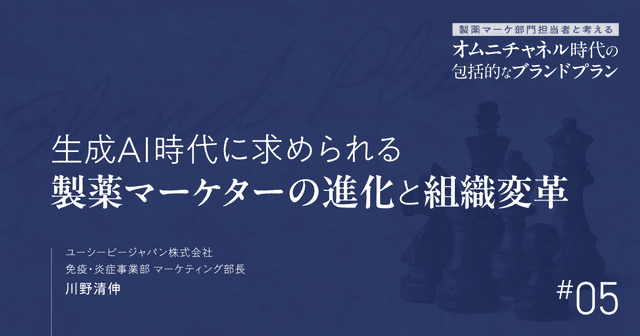

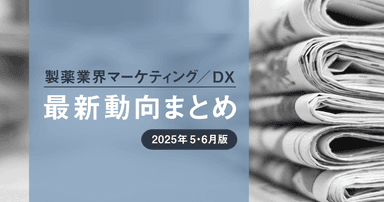
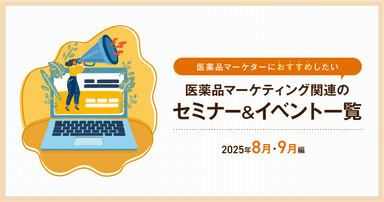




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



