働き方改革時代の医師が製薬企業に求めること|医師の本音を聞く2025(後編)

働き方改革の影響で医師の業務時間や診療スタイルに変化が生じる中、限られた時間の中で「いかに効率よく情報を得るか」が焦点になっています。それに伴い、製薬企業からの情報提供に対するニーズも少しずつ変わってきているようです。後編では、求める情報の内容や受け取り方の変化、取捨選択の基準、さらには製薬企業への具体的な要望を、医師3名の声を通じて明らかにしていきます。
座談会参加医師
A医師:関東の250床規模の総合病院に呼吸器内科医として勤務。主な所属学会は日本呼吸器学会、日本内科学会、日本肺癌学会、日本アレルギー学会、日本結核・非結核性抗酸菌症学会など。製薬企業からの依頼で定期的に講演を行っている。
B医師:関東の大学病院に呼吸器外科医として勤務。肺癌、気胸、膿胸、縦隔腫瘍などの手術に従事。主な所属学会は日本外科学会、日本呼吸器外科学会、日本肺癌学会、日本内視鏡外科学会など。製薬企業から定期的に座長、講演やディスカッサントの依頼を受けている。
C医師:地方の60床規模の肛門外科専門病院に消化器外科医として勤務。肛門疾患に加え鼠径ヘルニアや大腸癌手術、内視鏡検査に従事。主な所属学会は日本外科学会、日本消化器外科学会、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会など。講演経験などはない。
製薬企業からの情報収集スタイルの変化
情報提供は「業務内」で完結が基本に。夜の講演会は自己研鑽扱い
――司会:製薬企業の情報提供にかかる時間は業務時間に含まれていますか、それとも自己研鑽として扱われていますか。
A医師:当院では製薬企業との面談や講演会の院内視聴は基本的に業務内として行っていますが、夜間のWeb講演会は個人的に視聴しています。
B医師:私の施設でも面談は業務内ですが、講演会は昼夜どちらもあり、夜間の講演会は自己研鑽と位置付けられています。自宅視聴もあれば、病院の会議室に集合して視聴することもありますが、自主的に学びたいという意識が前提で自己研鑽に相当すると思います。
C医師:面談は業務内でお願いしています。業務外だと製薬企業の方も時間外労働となってしまい、お互いに疲弊しますからね。
デジタルコンテンツの活用が進む。面談実施方法は好みが分かれる
――司会:よく利用する製薬企業からの情報提供にはどんなものがありますか?
A医師:Web講演会を頻繁に視聴し、新薬や適応追加、臨床試験結果の発表などに関してはテキストベースの要約資料も活用しています。ただし、各製薬企業のサイトで登録を求められるなか、登録IDを忘れてしまうこともあり、行程が面倒なサイトからは足が遠のきます。動画コンテンツも見ますがm3.comから視聴することが多く、製薬企業のサイトを訪問しての視聴は少ないです。
B医師:副作用情報を調べるために特定の製薬企業のサイトを見に行くことはありますが、その他の製薬企業のサイトは色々と登録しているものの、あまり訪問することはありません。いつでも見られると思うと、あまり見なくなってしまいます。
C医師:手術動画以外はあまり見ていない状況です。講演会は多すぎて、取捨選択が大変だと感じています。所属施設の特性上、そこまで先進的な薬剤や治療を求められていないことから興味がないという点もあるかと思います。
――司会:働き方改革施行前後で、製薬企業からの情報収集の方法に変化はありましたか?
A医師:コロナ禍以降に増加したWeb面談移行の流れが、現在も継続しています。緊急対応や外来診療が延びてしまい、MRを長時間待たせしてしまうことやキャンセルせざるを得ないケースもあり、申し訳なさを感じることがありました。Web面談であれば、そうしたストレスも減り、調整しやすくなります。
B医師:Web面談はコロナ禍中に少し実施した程度で、ほとんど対面での面談で現在も変わっていません。面談はアポイント制ですが、講演会の日程や書類、新薬承認など簡単な内容に関しては医局前での立ち話程度で済ませられる方がありがたいと感じます。
C医師:私も基本的にアポをいただいてからの面談です。お互いの時間の無駄を防ぐためにも重要だと思います。
「短く」「要点を絞った」動画での効率的な情報収集が好まれる
――司会:現在の働き方において、どのような形式での情報提供が効率的だと感じますか?
A医師:薬の作用機序はテキストではなかなか理解しにくい場合もありますので、面談時も含め、動画コンテンツによる説明は概要を理解するのに役立ちます。
B医師:同じく、3分程度で内容が把握できる動画やスライドセットがWebサイトから閲覧できると助かります。
C医師:要点をまとめた3分動画はありがたいですね。私もビジュアルで把握できる方がインプットしやすいと感じるので、短時間の動画コンテンツをよく見ます。作用機序や手術器具の使用方法の情報が、外来や手術の合間など好きなタイミングでクイックに視聴できれば大変有用だと感じます。
医師が求める情報の質と新たに生まれたニーズ
Web検索では得られにくい実臨床ベースの情報にニーズ。チーム医療全体の理解を深める工夫を
――司会:内容面で充実させてほしい点はありますか?
A医師:既存薬剤の一般的な情報は他サイトで十分です。実臨床での使用例や他施設での導入状況・工夫、地域性や施設特性を踏まえた情報など、自分で調べにくい内容について情報提供をお願いしたいです。珍しい有害事象に関しては製薬企業にも確認して情報を得たく、的確な内容がすぐに得られると助かります。
B医師:「投与翌日に発熱する可能性が高いため金曜投与は推奨しない」といった運用上の問題点や、治験に入らないようなハイリスク患者への留意点が得られると導入時の不安が軽減されます。
例えば呼吸器領域であれば、Infusion reactionの出やすい薬剤について投与時の対応を病棟スタッフとどのように共有すべきかといった情報提供があるとありがたいと感じます。
C医師:私はすぐ臨床で試したいため、想定症例など実践的なフォーカスがあると良いです。
――司会:一般的な情報よりも、実際の使用感や問題点に対する対策や工夫など実務的な情報や、論文だけでは得にくい情報提供が好まれるようです。そのような情報提供の内容面への要望について、働き方改革対応に伴い変化などありましたか?
A医師:タスクシェアが進む中、コメディカルにも薬剤に関する知識を理解してもらうことが重要だと考えています。例えば薬剤関連の教育資料や短いワンポイント解説動画があれば、新規採用や導入もスムーズになるように感じます。
B医師:私もコメディカル向けの資材の拡充の重要性を感じています。ある程度知識・業務内容を共有できるようになれば、「とりあえず医師を呼んでおこう」という空気感もなくなるのではと思います。
C医師:コメディカルの教育は重要課題ですね。コメディカルの知識の底上げにより、医師だけでは見落としてしまうような変化に気づいてもらえるなど、医療の質にも貢献するでしょう。
情報の取捨選択の判断基準は「MRへの信頼」と「実臨床での有用性」
――司会:時間的制約がある中で、実際に製薬企業からの情報提供を内容により取捨選択する場面はありますか?その基準や優先順位があれば教えてください。
B医師:国際学会のまとめ情報は優先的に受けるようにしています。MRは自社製品のメリットだけでなくデメリットも含めて話せる方を信頼します。
A医師:同感です。また、自施設での導入可能性や実臨床に活かせるかを判断基準にしています。
C医師:自分の専門科で頻用するかどうかで優先順位を決めています。例えば私は消化器外科なので、消化器官に関する薬剤や器具などです。必要時指示に使用する薬剤(睡眠薬、不整脈薬など)の情報提供も受けますが、それ以外の専門科であまり使わないものは優先度が低くなります。
――司会:新薬採用や薬剤切り替え検討時など重要な意思決定の場面においてはいかがでしょうか。また、限られた時間で効率的に情報収集するために、MRに対してどのような工夫を求めますか?
C医師:新薬についてはMRからの説明会を重視しています。臨床における小さな疑問点にすぐ質問できるからです。説明会に際しては、我々が何を求めているかをヒアリングし、ニーズに応じた内容で、病院全体ではなく診療科ごとに開催いただければと思います。
B医師:私も重要な意思決定に際してはMRからの情報収集を重視します。例えば希少がんの分子標的薬が3種類横並びになった時、MRがどれだけ頻繁に情報提供に来ているかで採用薬を決めたこともあります。情報提供の工夫としては、10~15分程度の短時間のWeb講演会を複数回開催するなどしてもらえると、昼にタイミングが合わなくてもどこかで参加しやすいのでいいのではと思います。
A医師:同意です。使用経験が乏しい薬剤や新薬に関しては、MRからの薬剤情報のみならず、近隣の医療機関での使用経験に関する情報などが得られれば参考にすることもあります。情報提供の際は、科別・施設別にニーズを整理した上で不要な情報は省いてほしいです。事前ヒアリングが鍵だと思います。
医療の質向上に向けた現場の課題と期待
働き方改革は医療の質向上につながると考える一方、現場の負担分散とコストを懸念
――司会:医師の働き方改革は、今後の医療の質にどのような影響を与えると予想されますか?
B医師:長期的には医療のクオリティは向上すると考えます。一方で働き方改革は「形だけ」と批判される側面もありますね。医療へのアクセスや外科医不足など他の要因も絡むため、どうなるかは不透明だと感じています。
C医師:従来の「医師を定額で働かせ放題」の文化がなくなるのは歓迎すべきですが、その分コメディカルへしわ寄せが行きやすく、個々の業務効率と能力向上が必須だと思います。夜間の救急医療維持のために人件費が増加し、トータルのコスト抑制から賃金が上げづらくなる懸念もあると思いますが、全体としては無駄が削減されて良い方向に向かっている印象です。
A医師:私も、医師だけの環境改善ではコメディカルの負担が増加して全体の業務効率、ひいては医療の質が下がると思います。そのためコメディカルの労働環境の改善にも介入する必要がありますが、人件費の課題が伴い、最終的には医療制度全体への見直しに関わる話となるため、簡単に結論は出せないと感じています。
働き方改革を契機に、製薬企業にも現場目線の情報提供と柔軟な対応が求められている
――司会:労働環境改善が医療の質向上につながるという意見が多い一方で、医療アクセス低下やコメディカルの負担増への懸念も挙がっており、制度運用と提供体制のバランスが鍵になりそうです。そのような働き方改革に伴う変化の中で、今後製薬企業に期待することは何ですか?
A医師:要点をまとめた動画やコメディカル用の資材、勉強会の拡充です。薬剤概要の繰り返しになる説明会やアポイントは不要なことが多いため、そのような一方的な情報提供ではなく、実臨床に則したコンテンツや他施設の取り組みなど、現場視点のニーズを反映した双方向のコミュニケーションを重視してほしいです。
B医師:同意見です。また、最近肺癌学会が対話型AIを使用した副作用検索アプリを開発したかと思いますが、そのようにスマホで即調べられるオフィシャルツールがあると時短になると思います。
A医師:学会提供のアプリは良いですね。とはいえ、各製薬企業が作成に取り組むことで数だけ増えても大変なので、1つのアプリに情報をまとめていただき閲覧できるようになれば便利ですね。また、院内は電波が届きにくい場所もあるため、オフラインでも使用できれば使い勝手が良さそうです。
C医師:同感です。時短を叶えるためにはAIを活用したアプリがスマホで使えれば有用です。繰り返しになりますが、今後はコメディカル教育への重要性を感じているため、教育アプリや勉強会用スライドなどのツール提供があると嬉しいですね。
――司会:製薬企業の情報提供に関して意見や要望、伝えたいメッセージがあればお願いします。
A医師:今後も医師のニーズに即した情報提供と、現場の課題解決に貢献する取り組みを期待しています。
既知の内容の説明は不要と感じる場面もあり、内容が明確でないまま強引な対面のアポイント設定を求める対応は避けてほしいと思います。面会形式も状況に応じて柔軟に対応いただきたく、事前に相談してもらえると助かります。
B医師:コロナ禍の時期には「MRはオワコン」などと聞くこともありましたが、我々のニーズを汲み取り、距離感を把握しながら適切なタイミングで声を掛けてくれるMRの方々に、AIはまだ勝てません。今後も必要な情報を適切なタイミングで提供していただきたいです。
また、個人的には事前登録したWeb講演会は、前日にリマインドメールを受け取っても、忘れてしまうことや、直前にメールを探す手間により視聴しないことがよくあるので、開催5分前にもリマインドを送っていただけると助かります。
C医師:説明会開催にあたっては、参加医師のニーズを予めヒアリングしていただきたいです。また、私の場合はメールでの連絡は手間や作業が増えるため、電話や対面が楽で好ましいと感じます。
医師と製薬企業との新たな関係性に向けて
働き方改革によって、医師を取り巻く環境は大きく変化しています。その中で、製薬企業に求められる役割もまた、変わりつつあるようです。限られた時間で有用な情報を得たいというニーズに応えるためには、短時間・要点整理された動画や資料、実臨床に即した使用例の共有がより一層重要となります。また、医師個人だけでなく、医療チーム全体の理解を促すコメディカル向け資材や教育ツールへの期待も高まりも明らかになりました。
情報提供の形式や手段についても、現場の状況に応じた柔軟な対応、ニーズの事前ヒアリング、適切なタイミングでの案内・リマインドなど、工夫が求められています。
これからの製薬企業の情報提供は、「医師にとって役立つ」だけでなく、「現場の課題をともに解決するパートナー」としての視点が、より一層求められる時代になっているようです。
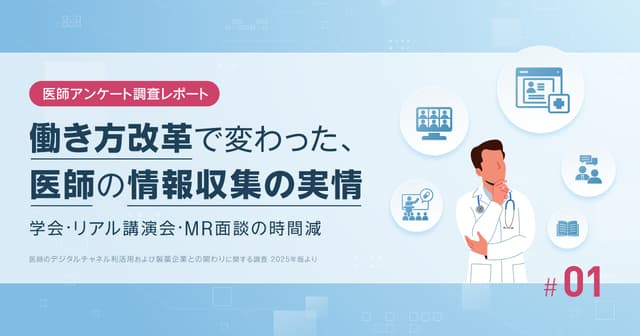
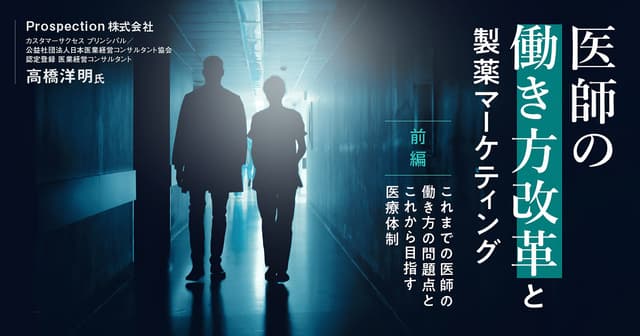
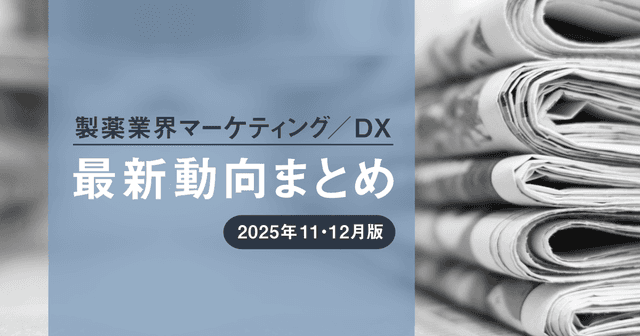
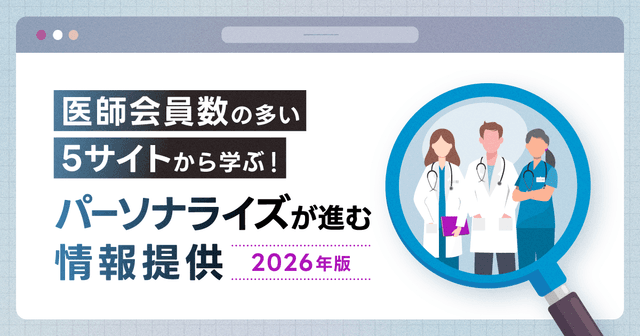

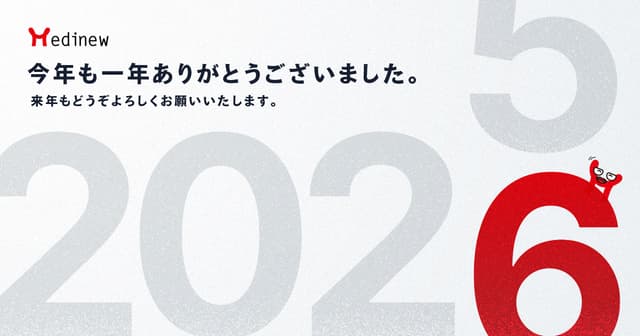

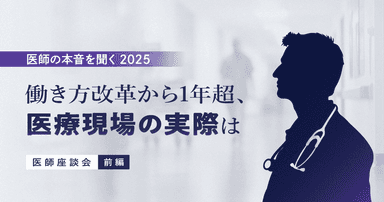




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



