働き方改革から1年超、医療現場の実際は|医師の本音を聞く2025(前編)
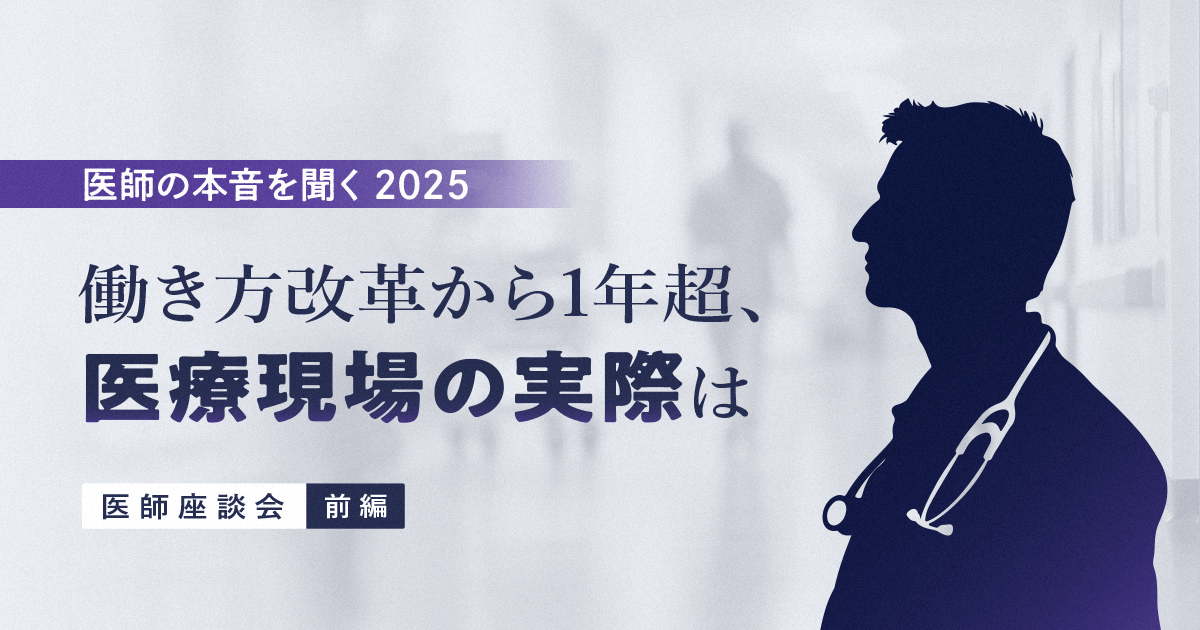
医師の働き方改革は、医療現場に勤務時間の短縮やタスクシフトといった変化をもたらしました。本座談会では、働き方改革から1年が過ぎた現場の実情や課題、チーム医療の変化、自己研鑽の方法などについて、現役の勤務医3名に本音で語り合ってもらいました。
座談会参加医師
A医師:関東の250床規模の総合病院に呼吸器内科医として勤務。主な所属学会は日本呼吸器学会、日本内科学会、日本肺癌学会、日本アレルギー学会、日本結核・非結核性抗酸菌症学会など。製薬企業からの依頼で定期的に講演を行っている。
B医師:関東の大学病院に呼吸器外科医として勤務。肺癌、気胸、膿胸、縦隔腫瘍などの手術に従事。主な所属学会は日本外科学会、日本呼吸器外科学会、日本肺癌学会、日本内視鏡外科学会など。製薬企業から定期的に座長、講演やディスカッサントの依頼を受けている。
C医師:地方の60床規模の肛門外科専門病院に消化器外科医として勤務。肛門疾患に加え鼠径ヘルニアや大腸癌手術、内視鏡検査に従事。主な所属学会は日本外科学会、日本消化器外科学会、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会など。講演経験などはない。
医療現場に起きた「働き方改革」の波
取組状況に施設差はあるものの、おおむね好意的に評価される改革進展
――司会:働き方改革の施行前後で、勤務時間や当直回数などは変化しましたか?また、勤務先の働き方改革への取り組みについて、どのように評価していますか?
A医師:現職に就いたのは働き方改革が正式に始まる前でしたが、既に対策が進められていたため制度開始前後で大きな変化は感じませんでした。医療クラークによる文書作成・入力代行が進み、当直は月1~2回、外部雇用で連休取得も可能になった点は恩恵です。
B医師:働き方改革は概ね好意的に見ています。不満もありますが、全体的に良い方向に向かっていると感じます。院内カンファレンスも勤務時間内に行うようになり、勤務時間は以前より短くなりました。当院も施行前の準備段階で大きく変化しました。例えば、ビーコンを名札に付けることで位置情報を管理して、時間外業務を正確に把握し、当直明けの帰宅や代休取得を厳格化した点が大きな変化です。
C医師:まだ転職して間もないですが、現職では緊急疾患は少なくほぼ定時に業務終了できます。一方、前職では宿日直許可の申請に関して制度を逆手に取ったブラックな運用がありました。労働基準監督署への相談を試みたこともありますが、その際は具体的な対応は得られませんでした。
A医師:私の近辺地域でも同様の話を耳にすることがあり、宿日直許可の申請に関しては厳格化したほうがいいと常々思っています。
会議時間の短縮やタスクシフトなど工夫がみられる
――司会:先ほどカンファレンス実施時間などの話が出ましたが、他に時間配分が大きく変化した業務はありますか?
C医師:前職ではカンファレンスは少なく、その代わりにアンガーマネジメントや感染対策などの教育動画の聴講が義務付けられていました。紹介状、返書、サマリーの仮作成、指示入力など事務作業のほとんどを医療クラークが代行してくれていたので、診察や処置に集中できる環境でした。
一方で、現職では医療クラークがいないため事務作業が大幅に増えましたが、カンファレンスがしっかりあるために教育的な環境だと感じています。
A医師:医療クラークによる業務代行に加えて、院内会議は不要なものが最低限に割愛され、なるべく夕方にかからないよう調整されています。
B医師:カンファレンスや院内会議の時間は前倒しになり、医療クラークの拡充で書類作成代行が進みました。また、看護師の行える手技範囲が拡大し、末梢確保や血培採取も任せられるようになりました。市中病院に比べると小さな一歩かもしれませんが、我々大学病院勤めからすると大きな一歩です。
A医師:確かに、市中病院では看護師ができる手技が大学病院では行われていないというのはありますね。大きな一歩です。
働き方改革による新たな手間は限定的であるものの、デジタル化に改善余地
――司会:タスクシフトや会議時間調整の影響は大きいようです。逆に、働き方改革対応で増えた手間はありますか?
A医師:特にありません。
B医師:勤怠管理アプリへの入力が必要になりました。入力と申請が同時にできるため大きな手間ではないですが、締め切りを守らない医師も少なからずいます。
C医師:以前と比べてタスクシフトが進んでいるため、業務量は格段に減りました。一方で、時間外手当申請は依然手書きなので、電子化ができるとなお良いと思います。
患者対応にも変化。診療時間確保のための時間管理術
――司会:勤務時間が制限される中、患者との面談時間や診療時間に影響はありますか?
A医師:インフォームドコンセント(IC)はほぼ勤務時間内に実施しています。外来は時間との戦いですので、検査案内は事務に依頼して、待合時間中に定期診察のスコア評価(ACTなど)をつけてもらうことで診察時間を確保するなど、効率化を図っています。
B医師:私もICは勤務時間内に行うようにしたのが大きな変化です。外来は、可能であれば検査日と結果説明日を分けています。待ち時間が減り、患者満足度も向上しています。
C医師:同様にICは基本勤務内に設定し、土日や夜は不可としています(緊急時のみは例外対応)。私も外来では検査日と説明日を基本分けています。
チーム医療が推進される一方、コメディカル人員不足の課題も
――司会:コメディカルとのチーム医療や業務分担での工夫や人員確保状況はいかがでしょうか?
C医師:今まで医師が負担していた業務をコメディカルに対応してもらえるようになったことで、医師側で見逃していたミスに気付いてもらうことが多々あります。例えば、患者への禁忌薬の処方や、紹介状の漏れなどへの指摘です。ひとりの患者に多くの目が届くようになったことで、ミスが生じてもヒヤリハットで済むため心強いです。当院は病床数が少なく、ベテラン層の看護師で占められているからか、コメディカルの人員不足はあまり感じません。
B医師:若手看護師はタスクシフトに前向きですが、従来の慣習に染まったスタッフには受容に時間がかかる場面もあります。また、コメディカルの人員は十分ではなく、大学病院の外来では医師が一番多いのではと感じることすらあります。
A医師:業務の一部がコメディカルに移行する中、医療クラークやリハビリ、看護師の負担増が懸念されます。それぞれ協力的に向き合っており良い空気感ができていますが、人手不足は否めません。当院も特に外来看護師は不足感が強く、コメディカルの配置は喫緊の課題です。C医師の施設のように不足していないとのご意見は新鮮でした。
限られた時間での自己研鑽-どうやって学ぶか
定義の明確化は各施設の裁量。位置情報管理導入でも残る自己研鑽の境界線問題
――司会:それではテーマを変えて、自己研鑽についての定義明確化や取り組みについてはいかがでしょうか?
C医師:自己研鑽の定義は明確にされていません。年配の医師は定時終了後から手術記録や動画を視聴し始める方が多く、定時で帰宅する方は多くありません。当院は年俸制で、見込み残業が含まれているからでしょうか。私は隙間時間に自己研鑽し、子育てがあるためほぼ定時で帰宅しています。
A医師:私の職場でも自己研鑽の定義は明確にされていません。見込み残業で時間外も発生しにくいので定時で帰宅しています。
B医師:論文執筆・学会発表準備、手術動画の視聴などが自己研鑽に該当します。また、位置情報で管理されているため医局にいる間は自己研鑽、病院にいる間は残業と自動で振り分けられます。手動で修正可能ではありますが、手間がかかることや、カンファレンスくらいしか明確に残業と呼べるものがないため、あまり皆付けていないようです。
A医師:ビーコンによる位置情報管理があると、自己研鑽の明確化もしやすくなりそうですね。医局にいる間は全て自己研鑽になるのはどうかとは思いますが。
情報収集にかける時間やタイミングの変化は経験値的な要素が大きい
――司会:働き方改革施行前後で、情報収集にかける時間やタイミングは変化しましたか?
A医師:以前は勤務後しか時間が取れなかったため夜にまとめて行っていましたが、通勤時間や昼休み、待ち時間などの隙間時間に分散するスタイルに変わりました。
C医師:同じく、専攻医時代は夜しか時間が取れませんでしたが、最近は日中の隙間時間で済ませるようになりました。経験年数を経るにつれ業務に余裕が出てきたからかと思います。
A医師:そうですね。また、情報収集の効率性も年次を重ねるごとに上がってきている点もあるかと思います。今でも専攻医や特に若手の医師は業務を覚えてこなすことで日中は手一杯で、情報収集は夜になりがちかもしれませんね。
B医師:元から手が空いたときに必要な情報を調べるスタイルは変わらず、働き方改革の影響はほとんど感じていません。
情報収集手段に大きな影響はなく、目的に合ったチャネルを広く使い分け、効率的な情報収集を図る
――司会:情報収集の手段や活用方法に変化はありましたか?また、目的に応じた手段(雑誌、m3.comなどの医療プラットフォーム、SNSなど)の使い分けはありますか?
A医師:MRとの対面での面談数は減り、Web講演会やm3.comの利用は増加しました。他科領域の薬剤情報をコンパクトに学べる動画は重宝しています。診療に関する情報は変わらずガイドラインを主軸にしつつ、新薬や使い慣れない薬剤を採用する場合はMRからの説明や資料、実臨床トレンドのキャッチアップにはWeb講演会でエキスパートの意見を参考にするなど、使い分けています。
B医師:最近X(旧Twitter)から情報を得る頻度は増えましたが、働き方改革とは関係ありません。手術手技動画はYouTubeやメーカーのWebサイトなどで視聴しますが、新薬情報に関しては私もMRからの情報提供を重視しています。
A医師:Xは学会公式のアカウントもありますから情報が得られますよね。
C医師:情報収集手段は特に大きな変化はないです。m3.comは頻繁に閲覧し、新薬情報はMRの情報提供を重視します。説明会を通じて名刺交換をしたMRには、必要であれば直接連絡を取ることもあります。
――司会:情報収集する際、どの情報から優先的にチェックしていますか?
C医師:まずガイドラインを確認し、最新の症例報告も参照します。病棟や外来でふと確認したいことが出た場合は、スマホでアプリやネットから検索します。
B医師:論文ならElicitやPerplexityなどの検索ツールを、各症例についてはガイドラインを参照します。病棟や外来では私もスマホ一択です。
A医師:私もガイドラインをまず確認します。紙媒体を持ち歩くのは重いので、スマホの活用は不可欠ですね。
――司会:学会や研究会への参加方法は変化しましたか?
A医師:オンラインやオンデマンド視聴の頻度が増えましたが、学会は現地参加を好みます。
B医師:研究会はオンライン開催が増え、学会は現地参加派で聞き逃した演題をオンデマンドで視聴しています。
C医師:私もオンライン視聴が増えました。遠方の学会には年2回の病院持ち参加枠を活用して参加し、専門医更新のための単位取得はオンデマンドで済ませています。
――司会:働き方改革の導入により、医療現場では診療の効率化やタスクシフト推進が進展しました。一方で、人員不足などの課題も残されているようですね。また、限られた時間の中でもさまざまなツールを用いて自己研鑽や情報収集の工夫がなされています。
後編では、製薬企業からの情報収集に焦点を当て、製薬企業との関わり方の変化や期待する情報提供の在り方について話し合っていきます。
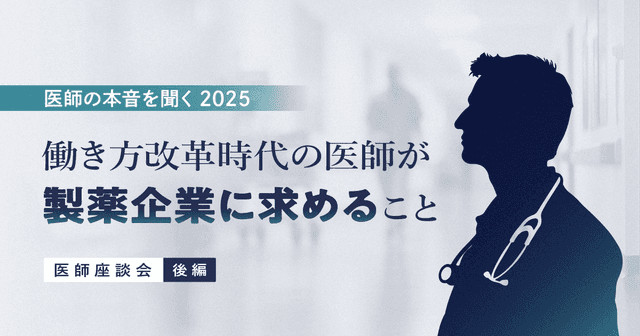
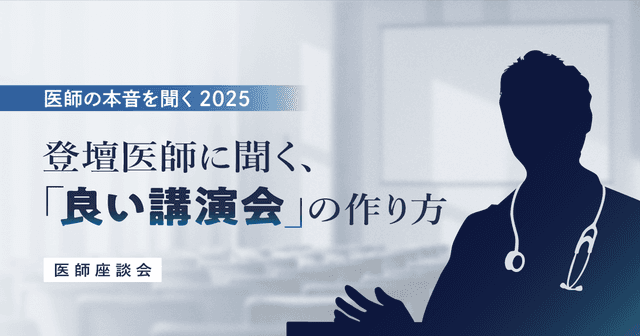
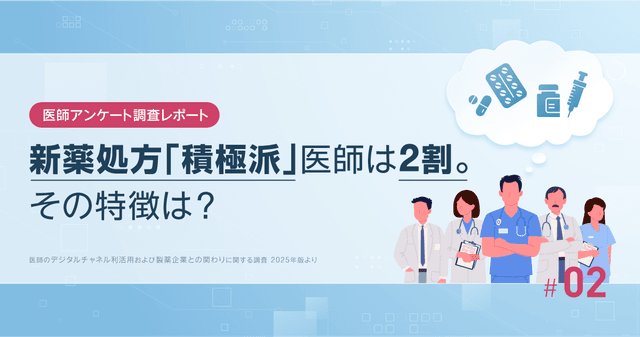

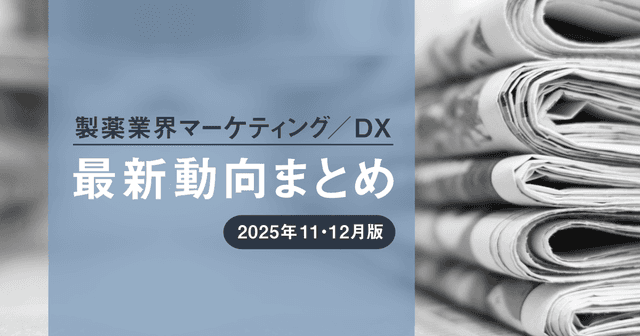
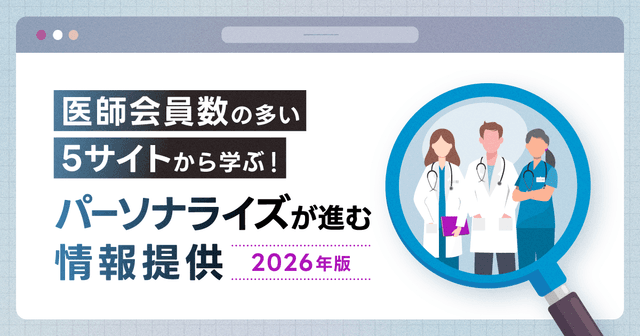

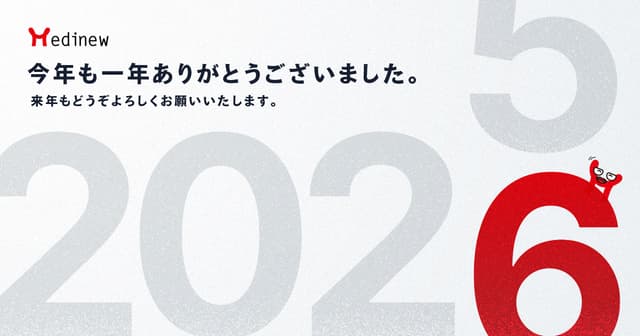

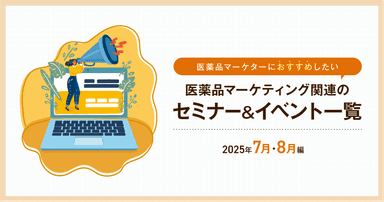
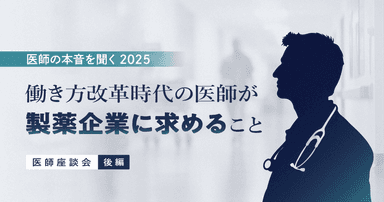



.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



