製薬マーケターのためのペルソナ設計【入門編】基本の作成プロセスと切り口を解説
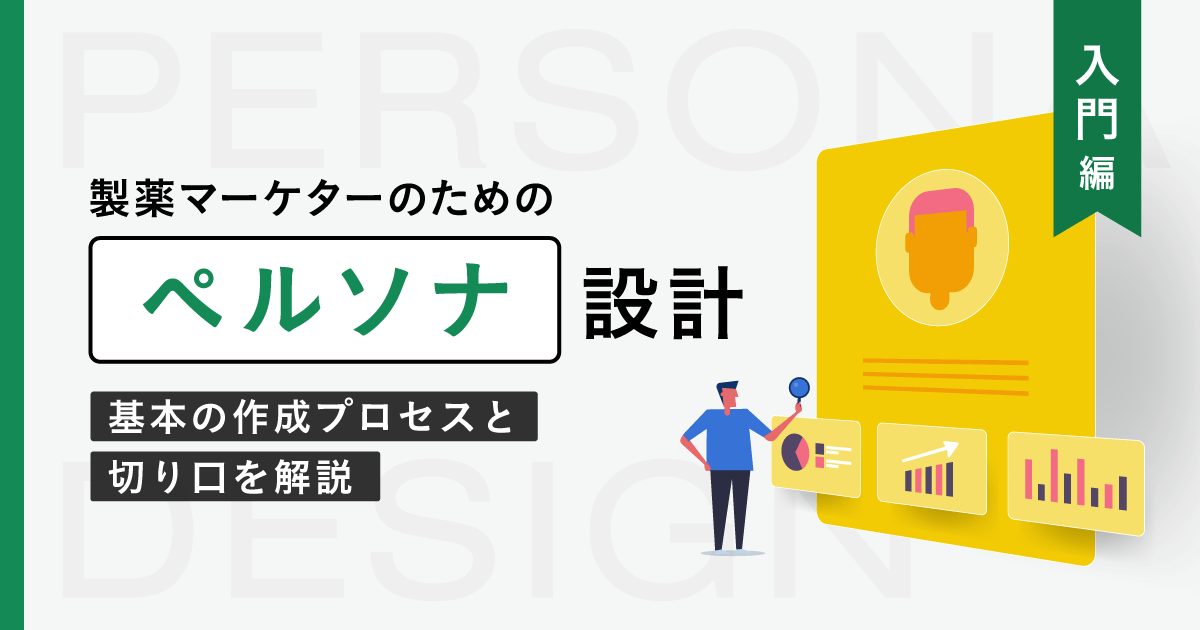
医薬品のシェア拡大のためには、実効性が高いマーケティングプランを策定することが不可欠です。その土台となるのが患者への深い理解と、そこから導き出される自社医薬品の適格例を具体的に明示するペルソナです。
一見簡単に作成できるように思えるペルソナ設計ですが、実は奥が深いものです。患者の理解が深まるほど、ペルソナはより精緻になり、マーケティング戦略の効果も高まります。本記事では、製薬マーケターが知っておくべきペルソナの基本と、作成プロセスを改めて解説します。
ペルソナとは
マーケティングにおけるペルソナとは、ターゲットオーディエンスを具体的に表現した架空の人物像のことです。この概念は、マーケティング戦略や商品開発において、顧客のニーズや行動を深く理解するために用いられます。ペルソナは、実際の顧客データや市場調査などに基づいて作成され、実在する人物のように具体的な属性や行動パターンを持つキャラクターとして描かれます。
例えば製薬マーケティングにおける患者のペルソナであれば、背景には実際の患者データや臨床経験、市場調査から得られた洞察が反映され、年齢・性別・症状の進行度といった基本情報だけでなく、生活習慣、価値観、治療に対する姿勢、情報収集方法など、多角的な視点から設計します。
これにより、抽象的な「患者セグメント」が、具体的な人物像となり、マーケティング戦略の立案やコミュニケーション設計において、より実践的で効果的な意思決定が可能になるのです。
マーケティングにおけるペルソナの重要性
マーケティングにおいてペルソナの作成は、顧客のニーズを的確に把握し戦略的な意思決定を行う上で非常に重要です。以下にその重要性を詳しく説明します。
1. 顧客理解の深化
ペルソナを作成することで、企業は顧客のニーズや行動パターンをより深く理解できます。具体的な顧客像を設定することで、どのような商品やサービスが求められているのか、またどのようなコミュニケーションが効果的かを明確にすることができます。
2. マーケティング施策の効果向上
具体的なペルソナを設定することで、広告やコンテンツの内容、配信タイミングを最適化し、顧客の反応を高めることが可能になります。例えば、情報収集に積極的な患者と消極的な患者では、アプローチ方法を変える必要があります。ペルソナごとに響くメッセージを設計することで、コミュニケーション効果を最大化できます。
3. チーム内の認識共有
社内の異なる部門(製薬企業であればマーケティング、メディカルアフェアーズ、営業、開発部門など)の間で統一されたペルソナを共有することで、部門間での認識のズレを防ぎ、一貫した顧客対応が可能になります。これにより、プロジェクトの進行がスムーズになり、業務の効率化が図れます。
4. 競合との差別化
ペルソナを通じて顧客の特性を理解することで、特定のニーズセグメントを深く理解することで、競合が見落としている顧客の課題や期待を特定できます。これらのインサイトに基づいたポジショニングとメッセージングにより、市場での差別化を図ることが可能になります。
5. 製品開発の精度向上(主に一般消費財向け)
ペルソナを活用することで、製品やサービスの開発段階で顧客の具体的なニーズを反映させることができます。これにより、実際の市場で求められる製品を開発することができ、競争力を高めることができます。
とはいえ、医薬品ではすでに開発段階から処方対象が設定されますので、前述の内容は一般消費財などでのペルソナ設定の重要性と覚えておけば良いでしょう。
このように、ペルソナ設計はマーケティング戦略の成功に不可欠な要素であり、顧客視点でのアプローチを実現するための強力なツールといえます。
ペルソナ作成のプロセス
続いて、ペルソナを作成するためのプロセスについて詳しく説明します。
- データ収集
- セグメンテーション
- ペルソナの具現化
- ぺイシェントジャーニーの作成
- フィードバックと修正
1.データ収集
まず対象となる患者群に関するデータを収集します。これには、年齢・性別・病歴・生活習慣・社会経済的背景などが含まれます。
理想的には、KOLなどの協力のもと、医療機関での患者の診療記録に基づいて、できる限り実際の患者像に近い情報が得られれば、患者への理解がますます深まるでしょう。
また、プライマリーリサーチなどのアンケート調査も実施します。この時、リサーチ会社に質問表の作成を完全に委託するのではなく、プロダクトマネージャー自身が持っている情報やデータ、知見も加味して、アンケートの内容を深掘りする質問を作成すると、より一層深いインサイトが得られます。
このようにして、丹念に患者に関するさまざまな情報を集めることが重要です。
2.セグメンテーション
収集したデータを基に、患者をいくつかのセグメントに分けていきましょう。
例えば、以下のような医薬品の適応症に関連するさまざまな基準で分類していきます。
- 性別
- 年齢(年代)
- 職業
- 病気の進行度
- 臨床検査値
- 治療に対する反応の度合い
- 医療へのアクセスのしやすさ
- 都道府県といった地域性
など
これにより、異なるニーズや行動パターンを持つ患者群を特定できるようになります。
また、この時に患者が受診前にどのようなソース(スマートフォン/パソコン/友人からの助言/テレビなど)から疾患関連情報を得たのか?何が決め手になって受診したのか?なども分かると、この後の「ペルソナの具体化」や「ペイシェントジャーニーの作成」のステップで役立ちます。
3.ペルソナの具体化
次に、前述の各セグメント別に、具体的なプロフィールを作成します。
ペルソナには、患者の性別、年齢、職業、趣味、医療に対する態度、情報収集の方法などを含め、集めた情報をもとに実在の患者のように具体的に描写していきます。
ここで重要なことは、単なる属性だけでなく、より詳細な悩みや生活まで描くことです。例えば、「58歳の糖尿病患者」ではなく、「健康診断で糖尿病と診断された58歳の中小企業経営者。多忙な日々で食事や運動の管理が難しく、薬の服用も時々忘れてしまう。治療よりも仕事を優先しがちだが、最近の体調不良で家族に心配される中、真剣に治療に向き合い始めている」といった具体的な描写です。
これにより、皆さんの担当製品のマーケティング施策が、よりターゲットとなる患者に合ったものになります。
4.ペイシェントジャーニーの作成
完成したペルソナを基に患者の行動と感情をマッピングします。セグメンテーションで明確化した患者の受診前の行動をもとに、患者の受診前の行動や感情の流れを時系列で整理(=ペイシェントジャーニーマップを作成)しましょう。
患者がどのように情報を得て、どのように意思決定を行うかを可視化することができます。
製薬企業のペイシェントジャーニーマップは、病院受診後のトリートメントフローに焦点をあてていることが多いですが、それは患者の受診前の行動データが不足しているからです。そのため、新薬の上市前にペルソナを作成する際、前述の「データ収集」の時点で、KOLなどから患者の受診前の行動をヒアリングしておくことが重要です。そこでの情報収集が充実していれば、その後のマーケティングプランの作成やプロモーションプランの作成が容易になる、実効性が高まるといったさまざまな影響が出ます。
5.フィードバックと修正
ペルソナとペイシェントジャーニーは、一度作成して終わりではなく、継続的に検証・更新します。作成したペルソナに基づいてマーケティングプランを実行した後は、実際の処方動向や患者の反応を分析し、当初のペルソナとの整合性を評価します。この時、もしペルソナが実際の患者像とズレているなら、必要に応じて修正を行います。
一般消費財のペルソナと異なり、医薬品マーケティングにおける患者のペルソナは、医薬品の適応症が変わらない限り、大きく変わることはありません。
しかし、先般の高額療養費制度の見直しや選定療養の導入で話題になったように、医療制度の変更に伴って患者の受療行動が変わることはあります。そのため、医療業界や製薬業界の変化を適切に踏まえて、定期的にペルソナを見直し、最新の情報を反映させることも重要です。
製薬企業でのペルソナ設計の切り口
ペルソナの数は、対象とする患者群の多様性や、マーケティング戦略の目的によって異なります。一般的には、以下のような切り口でペルソナを作成することが可能と考えられるでしょう。
病気の種類
例えば、糖尿病、高血圧、がんなど、異なる病気ごとにペルソナを設定することが可能です。
この時、高齢の患者であれば、複数の疾患を併発していることもあるため、一人のペルソナに複数の疾患のプロファイルが織り込まれたペルソナを作成することになるでしょう。高血圧症と脂質異常症と糖尿病を合併した患者を対象とした医薬品のペルソナが必要になることも考えられます。
治療の段階
初期治療中、維持療法中、再発後の治療など、治療の段階によって異なるペルソナも作成可能です。
多発性骨髄腫やALK融合遺伝子陽性非小細胞肺がんなどのように、治療レジメンや治療薬が何度も変更される疾患もあります。その場合は、1st Line、2nd Line、3rd Lineなどのライン別にペルソナを作成し、それぞれのラインごとに製品メッセージが検討されることが望ましいでしょう。
患者のライフスタイル
健康意識が高い患者、医療に対して消極的な患者など、ライフスタイルや価値観に基づくペルソナも検討すべきです。
例えば「仕事第一で健康管理を後回しにしがちな40代男性」と「健康情報に敏感で積極的に自己管理する50代女性」では、同じ疾患でも治療への姿勢や情報ニーズが根本的に異なります。この違いを反映したペルソナ設計により、患者タイプに応じた効果的な介入戦略が立案可能です。
この切り口のペルソナは、患者指導箋やPSP(ペイシェントサポートプログラム)の作成の必要性を検討する際に役立ちます。
治療から脱落しやすい患者層の特性を深く理解することで、脱落防止のための効果的な支援プログラムを設計できます。
社会的・人口統計学的特性
年齢、性別、社会経済的背景に基づくペルソナは、患者の医療アクセスや治療決定に大きな影響を与えます。その年齢やご家庭の状況などで受診しやすいかどうかが大いに異なるためです。
例えば、仕事や育児が多忙で受診が難しい患者もいらっしゃいます。このような患者に対しては、オンライン診療などでの受診を促すなど患者の生活を踏まえた最適な医療へのアクセスの情報提供が必要です。
この切り口のペルソナは、疾患啓発サイトなどでの情報発信、早期受診促進などに貢献するでしょう。
このように、ペルソナはいくつかの切り口で数種類作成可能であり、具体的なニーズに応じて柔軟に設定することが求められます。製薬業界では通常3〜5種類程度のペルソナを検討、設定することが多いようです。ただし、生活環境、医療制度の変化など、PESTLE分析で扱うようなさまざまな観点を踏まえれば、特定のプロジェクトや製品に応じてさらに多くのペルソナを作成することが望ましいでしょう。
ペルソナを設定し、効果的な製薬マーケティングを
ペルソナ設定は、その後のマーケティングプランの作成やメッセージング、患者サポートプログラムの検討など、多くの場面で役に立ちます。
ペルソナの精緻さは、その後のメッセージングや患者サポートも検討のしやすさに影響します。患者の実態に即した精緻なペルソナほど、ターゲットに響くコミュニケーションが可能になり、上市後の売り上げの伸びやシェアの獲得に至るまで密接に関わってくるのです。
また、すでに作成済みのペルソナであっても、適宜更新する必要があります。自社医薬品を取り巻く環境が変化したなら(例えば競合品が後から上市した、新たな治療法が開発された、など)、そのタイミングで再度最新のペルソナを検討しましょう。こうした地道ではあるものの患者の理解を深める活動を継続することは、結果的に競合品よりも深い患者理解に基づく最適なメッセージングや施策の検討と実施を可能にします。
医師と患者の心を掴み、製品価値の最大化につなげるために、ぜひ本記事を参考にペルソナ設定の基本から実践してみてください。



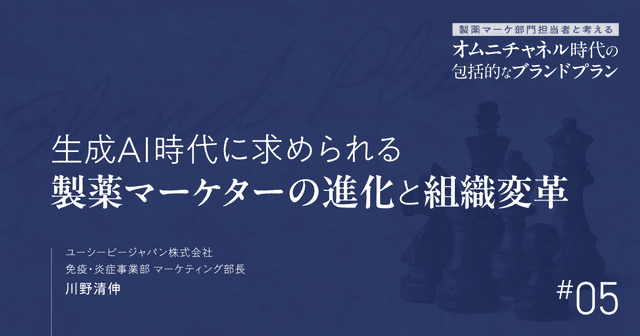
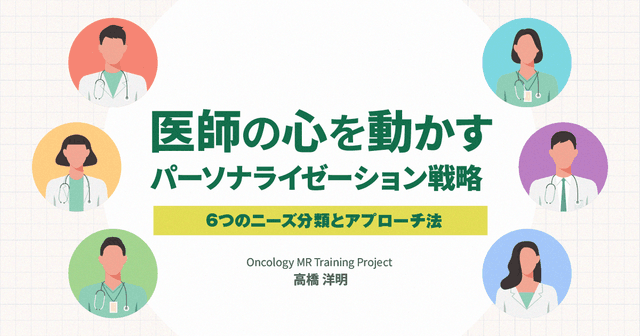
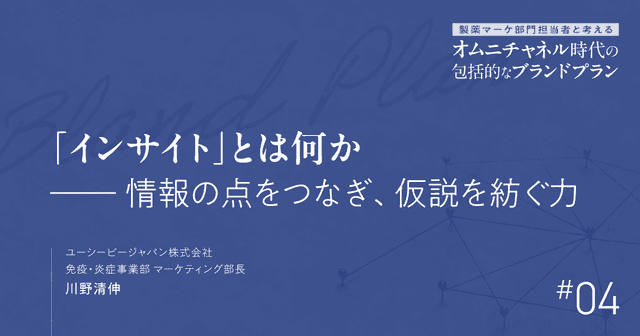

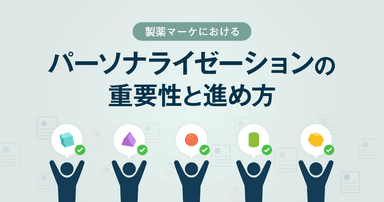
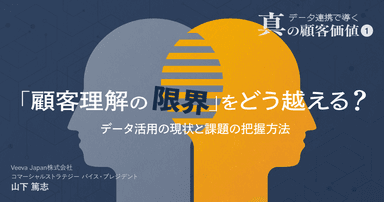



.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



