アステラス製薬、MAとコマーシャルを統合。ブランド主軸のチームで価値最大化と「チャンピオン」を目指す-社員1,200名が集う全体会議レポート
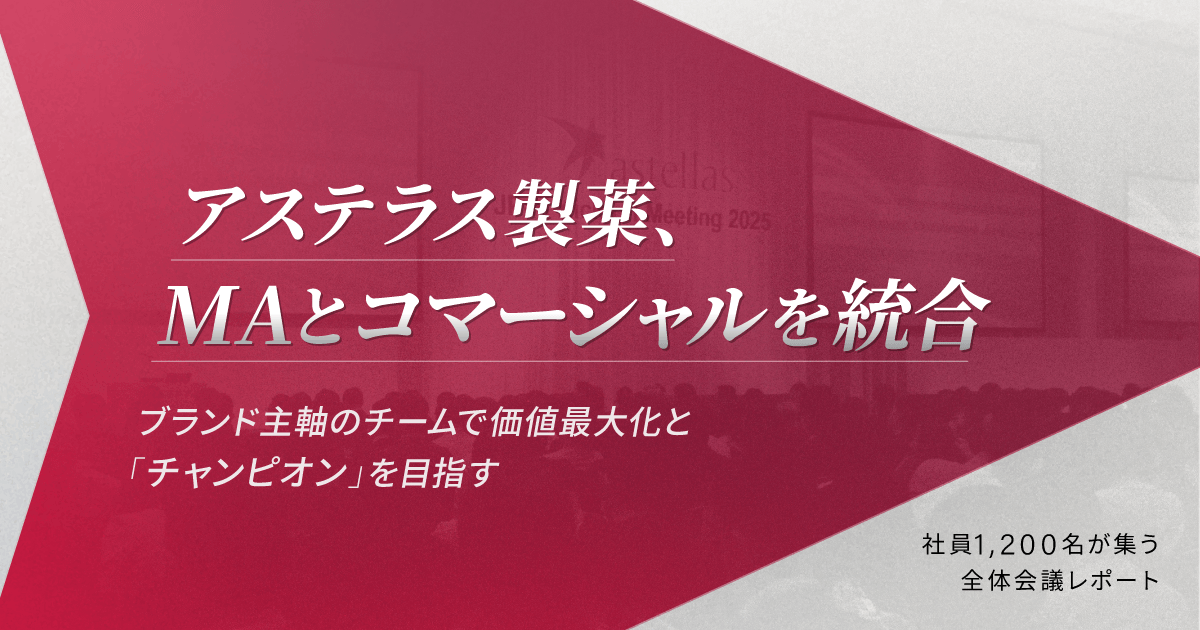
アステラス製薬株式会社は2025年4月1日、メディカルアフェアーズ(MA)部門とコマーシャル部門を、それぞれの機能の独立性を維持しながら統合しました1)。そして4月8〜10日、統合後の新たなる日本マーケット部門は、新年度のキックオフとなる全体会議を開催。約1,200名が一堂に集い、新体制でのブランド価値最大化に向けた取り組みのスタートを切りました。
本記事では、MA部門とコマーシャル部門の統合までの取り組みの経緯を解説し、統合後初となる全体会議の様子をレポートします。
さらに、両部門のトップである日本コマーシャルヘッド 河野順氏、メディカルアフェアーズ(MA)ジャパンヘッド 藤田修平氏の両名にインタビュー。今回の部門統合の背景、これまでの取り組み、そして今後の展望について伺いました。
部門統合はブランド価値最大化に向けた戦略の一環
アステラス製薬の日本マーケット(MA、コマーシャル)は、2021年頃からMAとコマーシャルの連携を強化してきました。

同社は顧客エンゲージメントの向上を図るため、MAとコマーシャルの協働体制を構築し、連携強化とブランド戦略の共有を促進。2024年度には、「ブランドチームが顧客ニーズに即してより機動的に対応できること」を目的として、MA・コマーシャル双方で組織再編を実施しています。
▼関連コンテンツ

そうした中で、昨年度から特に注力しているのが、部門を超えたブランド価値最大化のオペレーティングモデルである「Brands@Center(ブランズアットザセンター)」の推進です。
Brands@Centerでは、製品ごとの「ローカルブランドチーム」の機能とコラボレーションを強化し、それぞれのチームが製品ブランド価値最大化を目標としてより機動的(アジャイル)な活動を行います。各チームには、MAからはMAリードやMSL、HEOR(医療経済・アウトカムリサーチ)など、コマーシャルからはマーケティングリードやセールス、 マーケットアクセスなどがメンバーとして参画。
こうした取り組みを通じて、MA部門とコマーシャル部門の連携はさらに進み、さまざまな成果が得られました。そして満を持して、25年4月に両部門が統合したのです。2025年度のキックオフとなる全体会議は、これまでの取り組みの具体的な成果と、今後の活動の方向性を共有する場となりました。
全体会議で1,200名がチャンピオンへの道筋を共有
4月8日、アステラス製薬の日本マーケット全体会議の初日には、東京都内の会場にMAとコマーシャルの社員約1,200名が集結しました。

会議の冒頭では、コマーシャルのトップである日本コマーシャルヘッドの河野氏、MAのトップであるMAジャパンヘッドの藤田氏がともに登壇。それぞれ講演を行いました。
日本コマーシャルヘッド「顧客からの信頼のチャンピオンへ」
河野氏は、2024年度の進捗と2025年度の展望について話しました。
2025年度は、「チャンピオン」をスローガンに掲げ、2024年度からの変革ビジョンを継続します。「チャンピオンになるとは、すなわち勝利する、ビジネスで成功すること。製品の価値を患者さんに届ける役割を持つ我々にとって、ビジネスの成功とは、ブランド価値の最大化だと言えるでしょう」という認識を示した河野氏は、そのために以下が重要だと訴えました。
①エビデンスとデータ創出(育薬)
②競争優位性のあるブランド戦略
③MRの力
④MSL(メディカルサイエンスリエゾン)の力
⑤顧客ニーズに即したオムニチャネル活用
そして河野氏は、チャンピオンとなるためのカギは「顧客からの信頼」だと訴えます。つまり、アステラス製薬という企業が、そして担当者個人が、顧客から信頼を獲得することで、チャンピオンを目指します。

今日の全体会議をきっかけに、自分ができることを考え始めてほしい。そう述べた河野氏は、「みんなでチャンピオンになりましょう」と拳を掲げました。
MAジャパンヘッド「サイエンスに基づいた活動で信頼を得る」
続けて登壇したMAジャパンヘッドの藤田氏は、「顧客からの信頼」と部門統合後の活動について、MAの視点から語りました。
エビデンスベースドメディシン(EBM)が定着した現代の医療現場では、サイエンスに基づいて意思決定を行うこと(サイエンスドリブン)が徹底されるようになっています。特に抗がん剤などの重篤疾患の治療薬はエビデンスをもとに選択されていると、藤田氏は自身の医師としての経験からも確信しています。そうした重篤疾患の製品ポートフォリオを持つ会社にとっては、サイエンスに基づいた活動で信頼を得ることが極めて重要です。
藤田氏は、医師が製薬企業に対して抱くニーズのうちおよそ半分は、以下のような科学的なものだと分析します。
- 疾患領域におけるより専門的・補完的な情報
- 共同研究への興味関心
- 最新論文に基づく併用療法や治療法のデータ
MAだけではこれらの科学的ニーズ全てを拾うことはできず、コマーシャルからの情報連携が必要だと藤田氏は訴えました。今回の部門統合を通して連携を深めることで、顧客からの信頼の獲得へつなげることを目指します。
また、Brands@Centerでは、ブランドチームへの情報の集約や権限の移譲を行い、より自律性を持たせることで、医療関係者からのリクエストに組織の縦割りの力学を越えて対応していきます。その本質は「ヒエラルキーからの脱却」です。

MAとコマーシャルが共奏して顧客との信頼を築いていくことが、顧客から最も信頼される会社への道であると語り、藤田氏は講演を締めくくりました。
ブランドチームの取り組みの共有──変革の最前線
さらに全体会議では、Brands@Centerの推進の共有として、リーダーシップチームメンバーの紹介や、ローカルブランドチームの2024年度の取り組みに関するパネルディスカッションが行われました。
医師との関係性の醸成から成果につながったエピソードや、その裏にあったMR・MSL間の連携、フロントラインを支援するための機能の開発などが共有され、そのときの思考の流れや普段からの心がけなどについて、活発な議論がかわされました。

また、フロントライン、バックオフィスでのさまざまな活動が表彰され、その活動の内容の共有も行われました。
患者支援のボランティア活動も
会議の中では患者支援のボランティア活動も行われました。
その一つが、東京都内の病院で治療を受ける子どもとその家族のための滞在施設を提供・運営している認定特定非営利活動法人ファミリーハウスと協働した、季節を感じられるガーラントの制作です。ハウスの利用者に応援の気持ちを届けるために、社員らがそれぞれのテーブルを囲み、活動しました。また、米国のがん患者さんへの応援メッセージカード作りも行いました。


日本マーケットトップインタビュー:統合の所感と展望
全体会議で日本マーケットの全社員へ激励を送った、日本コマーシャルヘッドの河野氏とMAジャパンヘッドの藤田氏。
初日の登壇後にインタビューし、両部門統合の背景と経緯、今後の取り組みと展望について伺いました。

―アステラス製薬では、2025年4月から、MAとコマーシャルが部門統合しました。その背景と現状について、あらためて教えてください。
藤田氏:本日の全体会議でも話したように、我々は「チャンピオン」というスローガンのもと、顧客に最も信頼される企業となり、適正使用のもとで全ての患者さんに製品の価値を届けたい、という思いを持っています。そのために、MAとコマーシャルの連携に向けたマインドセットの醸成を進めてきました。

ただ、それでも、やはり部門の壁というのは大きかった。最後にそれを取り除いたことは、会社としても大きな決断だったのではないかと思います。
私がMAの本部長になった4年前には、営業本部長とのコミュニケーションはほとんどなく、年に1、2回会う程度でした。でも、今は毎日会うほどです。そうした変化の中で、リーダーシップのマインドセットが変わってきて、そこから社内にも浸透していきました。
1年前からは、ブランドチームで一緒に活動するようになり、ブランド戦略も統合しました。それまで、メディカルの戦略は私が承認し、コマーシャルの戦略は営業本部長が承認していたのですが、合同でブランド戦略ミーティングを開催し、我々が同席して一緒に戦略を決めるようになりました。
そして最後に、MAとコマーシャルが、それぞれの独立性を保ちつつ統合するという形になりました。一つひとつの積み重ねの結果、そこに行き着いたように思います。
組織再編というと、先行きへの不安や精神的なショックを感じるのでは、と思われるでしょうが、弊社の社員は当然のことのように受け取ってくれました。自然に移行を進められたのは最も良かったことでした。会社が最後の一押しをしてくれた、というのが実感ですね。
河野氏:この3年間で、ブランドチームは本当に部門横断的に活躍するようになりました。特に1年前からは、フロントラインでもMSLとMRが適切に連携し、顧客に対応できる流れができています。
ですから、今回の統合は自然な流れだと考えています。
他の先進国も含めた課題として、MAとコマーシャルが顧客対応の機能として一緒に対応しなければ、顧客のニーズに応えられず、製品の価値が届かないことがあります。
そこで、一緒の傘の中に入りましょうということになったのです。もちろん、MAの独立性を維持するフレームワークも維持した上でですが、日本においては比較的、MAとコマーシャルが一緒に働ける状況になっていたので、組織変更に至りました。
―両者の融合をさらに促進するための戦略はありますか。
河野氏:この4月から、特にヒエラルキーから脱却し、ローカルブランドチームへさらに権限を委譲します。
ローカルブランドチームは、MAだけでなく、データ分析やオムニチャネルの担当者などさまざまなメンバーが集まっています。そのチームに権限を与え、目標と予算を管理させます。今までは、チームのメンバーにそれぞれ上司がいて、毎回報告しないとならない状態でした。そうしたヒエラルキーを脱却し、ローカルブランドチームとして顧客ニーズに迅速に応えていく、という仕組みを進めます。

クロスファンクショナルのチームで重要なのは、コ・リーダーシップチームであることだと考えています。コマーシャルのリーダー(多くの場合、マーケティングのリーダー)とMAのリーダーのコ・リーダーシップが、このモデルを上手く回すためのカギになります。
ですから、コ・リードのリーダーとしてのケイパビリティを高めることも重要なテーマです。その方法として、グローバル全体でトレーニングプログラムが提供されています。また、我々は、チームリーダーたちを育てるコーチングを行います。それに加え、ブランドチームにもよりますが、ベストプラクティスをお互い共有する仕組みもあります。例えば、このブランドで部門横断でのコラボレーションが上手くいった、という事例の共有などですね。
藤田氏:組織文化の変革というのは大変な仕事です。時間もかかるし、自分の固執する思いやしがらみもあります。地道な取り組みの繰り返しです。でも本当に、この1年でずいぶん変わったと実感しています。
―統合は自然に受け入れられたということですが、部門間での摩擦などを防ぐ工夫をされましたか。
藤田氏:2年前に検討された営業本部の組織改編のときに、MA、コマーシャル各組織の役割と業務を半年以上かけて洗い出しました。「この業務は本来的にはMAがするべきではないのか?」「今はどちらがしているのか?」など、かなり大規模な組織の見直しを実施しました。そういう作業を通して、マインドが変わったのが大きかったと考えています。
河野氏:あのプロジェクトを通じて、変革を受け容れよう、皆で頑張ろうという変化がありましたね。それが今のBrands@Centerの土台になっています。2023年には、プロジェクトに100名、200名とかなり多くの人が参加し取り組んでいました。
藤田氏:日本でそうしたアプローチを進めていて、グローバルの組織改編が後から付いてきた、という感じですね。
―Medinewの読者である他の製薬企業の方に向けて、今回の取り組みから得た気づきをメッセージとしてお願いいたします。
藤田氏:MAとコマーシャルの連携は、業界的な課題です。各社各様に課題を抱えていると思いますが、今回の統合の過程の中では、「アステラスとしての答え」を見つける気持ちでやってきました。
各企業がそれぞれに考えなければならない課題だと思います。我々はアステラス独自の回答を見つけました。社員がそれに付いてきてくれて、手応えを感じているところです。

河野氏:アステラスオリジナルソリューション、という感じで出していったのが良かったのかもしれませんね。
他の会社がそのまま転用できるような話ではないと思いますが、一番のカギは、やはり価値観とその下にあるマインドセットを変えていくことですね。
従来の日本のアステラス営業本部は、非常に階層的な組織でした。指示の実行には適していましたが、今はそういう製品ポートフォリオではありません。
一人ひとりのMRが、一人ひとりの顧客のニーズを把握する。それをMSLやバックオフィスが支援し、適切に対処していく。そのように取り組み方が大きく変わり、社員もそれに付いてきているところです。まだまだ足りていない部分もありますが、組織、社員のマインドが、昔のアステラスと比べて大きく変わってきたと感じています。
さらなる連携と変革で次のステップへ
アステラス製薬におけるMAとコマーシャルの部門統合は、単なる組織再編にとどまらず、ブランド価値最大化に向けた戦略的な転換点となりました。
ブランドを主軸に置き、フロントラインからバックオフィスまでが一体となって連携するBrands@Centerのオペレーティングモデルは、社員一人ひとりの意識変革を促しながら、顧客との信頼関係をより強固に築くことを目指しています。統合後初となる全体会議では、その進捗と次の行動への第一歩が示されました。
今後、この変革がどのように進んでいくのか、引き続き注目されます。
〈参考文献〉
1)経営体制の変更に関するお知らせ
https://www.astellas.com/jp/news/29716(2025年4月18日最終閲覧)
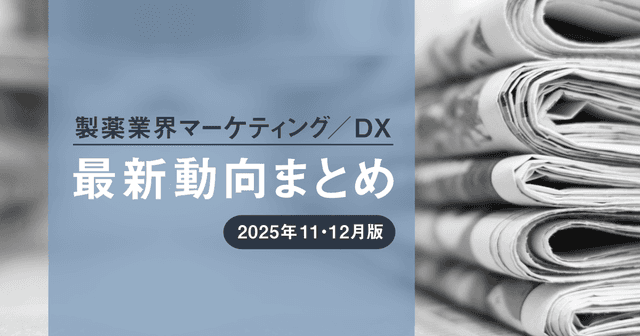
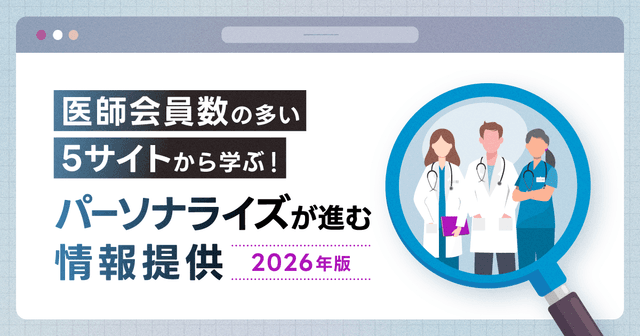

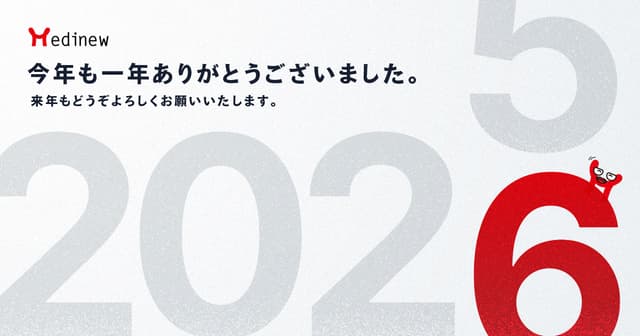

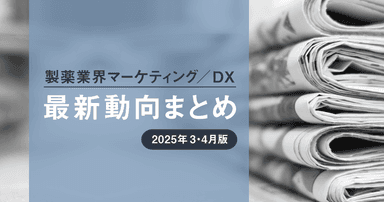




.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



