RWDが導く、疾患啓発から行動変容への道筋| MDMD2025 Summerレポート
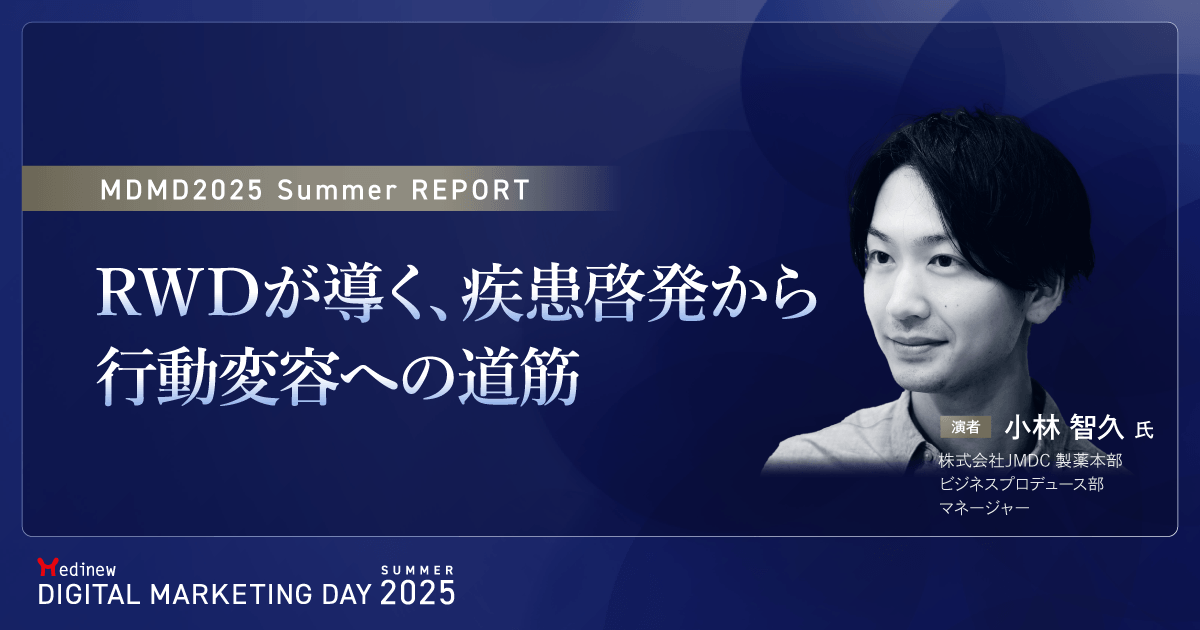
製薬企業の患者向け施策としてのパーソナルヘルスレコード(PHR)に注目が集まっています。しかし、その開発・運用では、使用促進や効果測定が課題と考えられます。
2025年6月に開催されたMedinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summerでは、「RWDが切り拓く製薬マーケティング〜疾患啓発から治療体験向上の最前線〜」と題し、株式会社JMDC製薬本部ビジネスプロデュース部マネージャーの小林智久氏が登壇。PHRを活用することで、疾患啓発から受診勧奨、よりよい治療へとつなげる一連のアプローチについて紹介されました。
「作ったけど使われない」PHRの課題
近年、疾患啓発や受診勧奨の一環として、PHRアプリを製薬企業がベンダーと組んで独自に開発・運用するケースが増えています。
PHR(Personal Health Record)アプリとは、患者個人が自身の医療・健康情報を一元的に管理できる機能を有するアプリのことです。患者は自身の診療記録、服薬履歴、検査結果、バイタルデータ、日々の体調などを記録でき、製薬企業は疾患に特化したサポートを行えるほか、患者の服薬アドヒアランス向上なども期待できます。
しかし、現場では「PHRを作ったが、あまり使われない」「どの程度の効果があったのか分からない」といった声がしばしば聞かれます。小林氏は、これらの課題の背景として、PHR導入自体が目的化してしまっているケースがあることに加え、以下のような要因があると分析します。
患者はそれぞれ疾患への理解度が異なり、またPHRの利用中にも受診・診断・治療と多様なフェーズを経験します。しかし疾患啓発WebサイトとPHRによる記録、その後の治療や生活習慣改善の支援などの施策が分断されているといった理由から、PHRの使用シーンが限定されている可能性があります。
また、連続したトラッキングデータが取れないために、本当に受診・診断につながったかどうかが分からない、といったことも発生しています。
こうした課題を解決するためには、患者理解を深め、PHR利用から行動変容へと至る連続的なジャーニー設計、一人ひとりの状況にあわせた個別化、確実なトラッキングによるデータ把握が不可欠だと、小林氏は強調。そのアプローチとして、JMDCが提供するRWDデータとPHRサービスである「Pep Up」を活用した手法を紹介しました。
PHRアプリ「Pep Up」の機能とユーザー像
Pep Upは、健康保険組合や自治体などの保険者を通じて、企業の従業員やその家族に提供されるPHRサービスです。
健診結果の閲覧や健康年齢の表示といった基本機能に加えて、記事やクイズの配信、ウォーキングラリーや改善チャレンジなど、行動を促すさまざまな機能が用意されています。健康行動に応じてポイントが付与され、ギフト券などと交換できるインセンティブ機能もあり、継続的な活用を後押しします。
各機能が単体で存在するのではなく、「健康への関心を高める」「知識を深める」「行動を起こす」「継続する」といった一連の流れが設計されていることが特徴です。
2024年時点で、Pep Upの契約保険者数は226、ID発行数は700万人を超えています。ユーザーは男性が6割とやや多く、40~50代の働く世代が中心です。一部の自治体とも契約が進んでおり、高齢者層にも利用されています。
Pep Upユーザー約700万人のPHRデータは、JMDCが保有する約2,000万人の健診・レセプトデータ、約15万人のウェアラブルデバイスデータと一意に紐づけられています。そのため、確実にトラッキングし、多角的なデータ分析やメッセージの個別化、介入スキームの設計を行うことが可能です。
PHR活用による疾患啓発・受診勧奨のPDCAサイクル
PHRを活用した疾患啓発・受診勧奨の施策実行をPDCAサイクルに当てはめると、最初のPlanの段階で行うのは、患者理解に基づくコンセプト作成です。どのような層にアプローチしたいのか、それぞれの患者がどのようなペインポイントを持っているのかを考えてから、実際のコンテンツの作成に進みます。
コンテンツは、疾患リスクの高低や行動の有無などでセグメントを分けて配信します。その上で、トラッキングにより効果測定を行い、PDCAサイクルを回します。
RWDのN=1ジャーニー活用で深い患者理解を
最初のコンセプト作成で最も重要となるのは、ユーザーの深い理解です。「患者にとってリアリティのある、手触り感のある強いペインポイントや、欲しい機能・メッセージを把握することが重要」と小林氏は話します。
製薬企業でも従来、インタビュー調査の実施や既存調査のリサーチをもとに患者理解の取り組みが行われてきましたが、限界もありました。
例えば患者インタビューでは、本人が自身の疾患状況や受けている治療を正確に把握していない場合も多く、得られる情報には曖昧さが残ります。また、そうしたN=1のデータを数人~十数人分集積して得た仮説が、どの程度患者全体を代表すのかは不明瞭です。
こうした問題を踏まえ、JMDCではRWDを活用し、より定量的かつ継続的に治療実態を把握するアプローチを採用していると、小林氏は説明します。
保険者のデータベースを用いれば、患者が初めて受診したタイミングから、どのような医療機関で診断され、どの薬剤をいつ処方されたかといった情報を、個人単位で時系列に沿って追うことができます。例えば精神疾患領域などでは、インタビューが難しい患者層もあると考えられますが、バイアスなく全体的にデータを取得でき、さらに薬剤の切り替えや受診間隔の変化、合併症の発症タイミングなどを可視化することができます。
そうしたRWDを活用したN=1ジャーニーの積み重ねから、定量化・モデル化することにより、ペインポイントや課題感、行動を把握することができます。理解を深めた上で、このターゲット層にこういった機能やメッセージを届けたい、というコンセプトが見えてきたら、コンテンツの作成、セグメントの割当・配信につなげます。
多様なコンテンツで健康意識の向上と行動変容を支援
Pep Upでは、健康意識の醸成から具体的な行動変容までを一連の流れとして支援するため、さまざまなコンテンツが提供されています。
・eラーニング機能
eラーニングは、プレテスト、教材閲覧、確認テストの3ステップで構成されており、ユーザーがどの程度疾患理解を深めたかを可視化できます。
・記事配信
健保を横断した記事配信により、高いエンゲージメントが得られます。参考になった・ならなかったのボタンを押すと、インセンティブのポイントを獲得でき、ユーザーが健康や疾患に関する知識を継続的に学ぶことができます。
・受診勧奨アラート
Pep upは健診結果やレセプトデータと紐づいているため、ハイリスク者を判断し、リスク別に通知を送ることもできます。例えば、腎機能の低下しているユーザーに対し、低下スピードなどの個々の状況にあわせて数字を盛り込んだメッセージを送付しています。
・チャレンジ企画
生活習慣改善を促すために、ウォーキングラリーや体重管理といったチャレンジ企画も展開。例えば、慢性腎臓病(CKD)に関連した減塩プログラムでは、ユーザーが記録する食事データや、歩数や血圧などのウェアラブルデバイスのデータを可視化する仕組みが用意されており、行動結果に応じてポイントが付与されるような取り組みも検討が可能です。
予測モデルを活用したセグメント配信
疾患啓発・受診勧奨のコンテンツは、画一的に提供するのではなく、患者の状況に応じて個別化できることが理想です。Pep Upでは、個別の健康状態やリスクに応じたセグメント配信が可能になっています。
先述の腎機能低下に関する受診勧奨アラートのセグメント割当では、JMDCが特許を取得したリスク予測モデルを活用しています。このモデルでは、eGFR低下速度を、健診データ、既往症や治療歴、合併症の有無などのさまざまな特徴量を活用して予測。数年の短期間の検査値だけでは捉えにくい変化も予測し、早期の介入につなげることができます。
JMDCでは他にも心疾患や睡眠など多様なリスク・傷病・行動のAIモデルを開発しており、通知手段も、アプリのプッシュ通知に加え、メール送付や圧着はがきの郵送など、多様なチャネルを用意しています。
定量・定性データのトラッキングでPDCAを深化
Pep Upユーザーのデータは、健診・レセプトデータ、ウェアラブルデバイスのバイタルデータ、アプリ上での行動データなどと一意に紐づけられており、統合して施策の効果をトラッキング可能です。小林氏は、「PHR上でアプローチしたユーザーが実際に受診したのか、診断されたのか、治療につながったのか。つながらなかったのはどのようなユーザーなのか。ペイシェントジャーニーを深く追跡できることが特徴」と説明します。
さらに、アプリ上で実施するアンケートを通じて、レセプトデータからは見えない背景要因も把握できます。定量データと定性データを紐づけることにより、より深いインサイト構築と改善施策の立案が可能となることが、Pep Upの特徴といえます。
「使われる」PHRで真の患者理解に基づく疾患啓発を
小林氏の講演では、PHRを活用した疾患啓発や受診勧奨の成功の要として、以下が強調されました。
- RWDを活用した真の患者理解に基づくコンセプト設計
- セグメントに最適化されたコンテンツ配信
- 定量・定性データに裏付けられたトラッキングと施策評価サイクル
健診・受診などの医療データと、日々の活動やバイタル、行動データが一元的に蓄積されるPHRは、製薬企業にとってもこれまでにない粒度で患者理解を深められる基盤となり得ます。「疾患の認知・学習から行動変容、トラッキングまでは連続的なジャーニーであり、同じプラットフォーム上で施策を打つことで、より適切なメッセージ、患者の状態に合った施策を打てる」と小林氏は締めくくりました。
PHRはもはや「作って終わり」ではなく、継続的に患者とつながるタッチポイントです。上手く活用し、患者中心のアプローチを設計していくことが、今後の製薬マーケティングの質を左右するといえるでしょう。

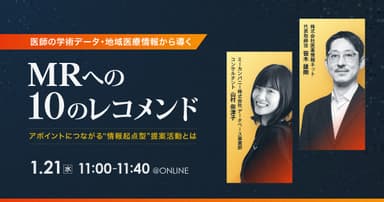





.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)


