日本型GTMの強みと限界を、グローバル比較から見直す|2025 Veeva Japan Commercial & Medical Summit
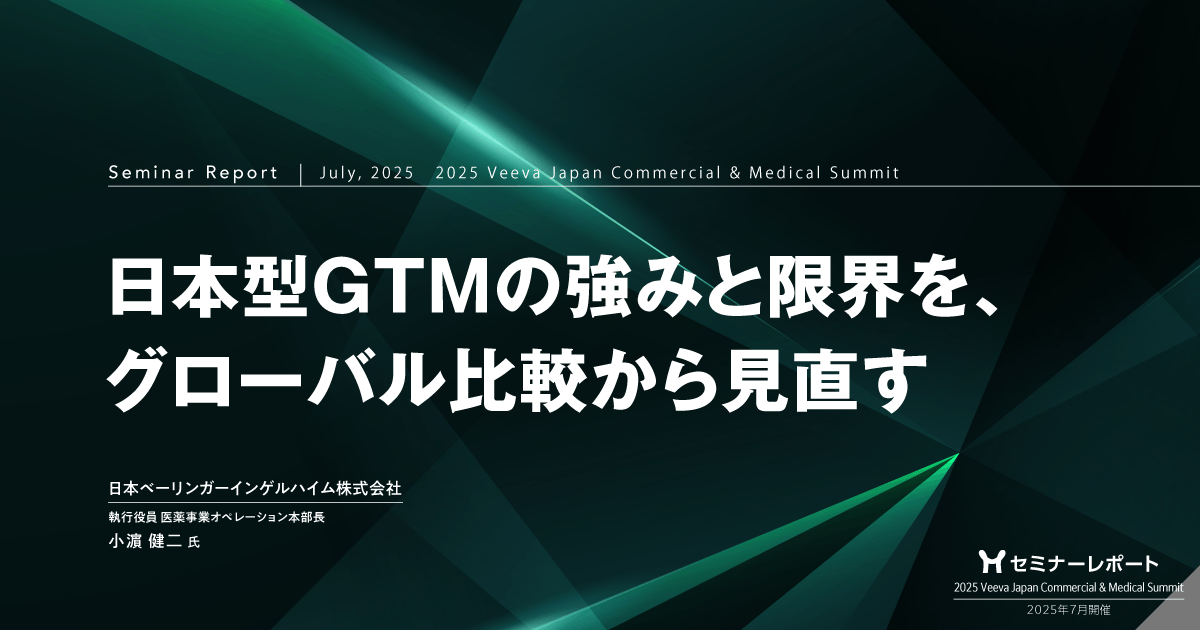
グローバルで共有されるチャネル戦略や評価の枠組みがある一方で、日本の製薬ビジネスモデルは制度やMR活動のスタイル、医師との関係構築のあり方において独自の構造を持ち続けています。
2025年7月に開催された2025 Veeva Japan Commercial & Medical Summitの基調講演では、日本ベーリンガーインゲルハイムの小濱健二氏が登壇。MRの再評価、コマーシャルエクセレンス部門(ComEx部門)の全社的な役割、そしてAI時代に求められる人材像までを考察しました。グローバルとの比較から見えてくる、日本型Go-to-Market(GTM)モデル*の再設計のヒントを探ります。
*Go-to-Marketモデル:製品をどのように顧客に届けるかの手順を設計したモデル
MR再評価から始まる、日本の製薬企業の現実的なチャネル設計
日本の製薬業界におけるマーケティングは、現在もMRを中心としたチャネル戦略が根強く残っています。実際、医師が新薬を認識する初期段階において最も参考にする情報源として、MRとの面談が挙げられます1)。講演会やWebセミナーといったチャネルの選択肢が広がっている中でも、MRは“最初の接点”としての優位性を保ち続けているのが実情です。
日本市場のMRの活動モデルには独自性があり、特に「短時間×頻回」の訪問スタイルは、他国と大きく異なる点です。例えばアメリカやヨーロッパでは、医師との面談は3カ月に1回、30分程度であることが主流です。一方、日本では月に複数回の訪問が可能なことも多く、1回あたりの面談時間はごく短時間にとどまります。
【関連記事】
「対面回帰」だけでは語れない、製薬企業の情報提供戦略の現在地/ファーマIT&デジタルヘルス エキスポ 2025

見かけの数字に惑わされないチャネル評価を
こうした違いは、チャネル評価にも影響を与えています。例えば、ディテーリング時にCLM*資材を使用した割合2)は日本では約30%とされており、ヨーロッパ(約40%)、アメリカ(約50%)と比較すると低く見られがちです。
*CLM(Closed Loop Marketing):MRが医療関係者との面談でタブレットなどを使用し、視覚的なコンテンツを表示して説明する営業手法およびそのシステム
しかし、小濱氏はこの数字の単純比較に疑問を呈します。日本は欧米諸国に比べて、短時間の面談が繰り返される構造であるため、訪問頻度を加味すれば、実際に資材が「医師に触れられている量」は同等かそれ以上とも考えられます。
このように、表層的なKPIにとらわれず、日本の営業モデルに即した評価軸を持つことが、グローバルとのコミュニケーションにおいても重要になるといえるでしょう。そうした評価軸を基盤として、真に日本市場に適したGTMモデルの構築が可能になるのではないでしょうか。
全社視点の「仕掛ける組織」となる。コマーシャルエクセレンスの役割
MRの特性を踏まえた上で、企業全体としてどうチャネルを最適化し、GTM戦略を再構築していくか。その鍵を握るのが、横串組織であるコマーシャルエクセレンス部門(ComEx部門)の存在です。
強いチャネル戦略やGTMモデルは、現場だけでも、本社だけでも成立しません。小濱氏は、組織に対して「提案責任」を担うべき存在がComEx部門であると言います。 これは、事業部が担う「実行責任」と対になるものであり、両者が噛み合ってこそ強いマーケティング・営業組織が実現します。
全社俯瞰で「標準化」と「個別最適」を見極める
ComEx部門は、事業部横断で会社全体を俯瞰できるポジションにあります。各ブランドの戦略やチャネル設計に関与しつつも、特定の製品に偏らず、全社としての投資配分やリソース最適化を提言できます。だからこそ、全体のバランスを見ながら、「どこを標準化し、どこに差異化を設けるか」を設計する立場として機能することが期待されます。
小濱氏は、ComEx部門には「仕掛ける組織」としての機能が必要だと説きます。単に現場の支援にとどまらず、戦略的にチャネルや施策のあり方を問い直し、変革を促す役割です。例えば、各事業部で異なる定義で運用されているチャネル指標やデータの使い方に対し、標準化を促すのもその一つです。対して、全社的に共通化すべきでない領域においては、個別最適の推進を担うことも求められます。
提案を機能させる心理的安全性の重要性
しかし、どれほど良質な提案を持っていても、意見が言い出しにくい組織文化の中では、その価値は生かされません。特に縦割り構造が強い組織においては、横断的な組織が物申すには一定の関係構築と信頼が必要になります。
だからこそ、現場との対話を重ね、建設的な関係性を築いていく姿勢が、仕掛ける組織としての実効性を支える基盤となります。
AI×データ時代の“新しいGTMモデル”に求められるスキルとは
新しいGTMモデルを考える上では、チャネルの構成や投資判断において「何を軸に評価するか」、つまり、各チャネルのROI設計が問われるようになっています。
講演では、AIによってROI評価が高度化する可能性にも言及されました。資材レビューや競合分析、ターゲティング、営業活動の最適化、さらには研修プログラムまで、AIの活用領域はますます広がっています。最近では、仮想の医師とのロールプレイを通じて実践的なコミュニケーションを学べるMR研修ツールも登場しており、一定の成果が報告されているようです。こうした取り組みは、単一チャネルのパフォーマンスを底上げするだけでなく、オムニチャネルエンゲージメントの全体最適化の観点からも有効だといえます。
これからの時代に求められる人材像として、小濱氏は3つのスキルを提示しました。
1つは、英語力に代わるものとしての「コミュニケーション力」です。これは語学の習熟ではなく、異なる価値観や文化背景を持つ相手と対話し、理解を深める力を指しています。
次に「数字で物事を見る力」、すなわち会計的な視点が重要であるとされました。数値は最も普遍的なビジネス言語であり、論理的な判断を支える基盤になります。
最後は「AIを使いこなす力」です。情報処理にとどまらず、AIを活用して分析・判断・設計を行う力こそが、今後の差別化要素になるという見解が示されました。
【関連記事】
製薬企業が目指すべき一歩先のオムニチャネル戦略-3つの課題と実現への道|MDMD2024Autumnレポート
チャネル戦略の未来を担う、組織的アップデート
これらのスキルは、もはや個人だけのものではなく、組織として備えていくべき基盤となりつつあります。特にComEx部門のようにチャネル構造を横断的に見渡す部門においては、ROIを可視化し、AIやデータを踏まえて戦略を構築する力が問われています。
現場チャネルの再評価、デジタルの位置づけの再設計、そしてチャネル全体の投資対効果の可視化。それらを実現するうえで、データを読み解き、AIを使いこなす組織づくりが、今後のGTM戦略の成否を分ける鍵になるのではないでしょうか。
【関連記事】
#3 エンゲージメントを加速するAIと連携基盤|データ連携で導く真の顧客価値
<出典>
1)ミクスOnline, 2022.05.10, 新薬処方 “積極派”の医師は「MR」と「Web講演会」で情報収集 “慎重派”はオムニチャネルが効果的(https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=73008)
2)Veeva Pulseデータより引用
【関連コンテンツ】
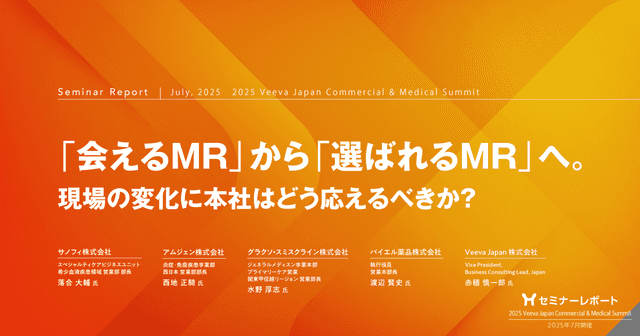

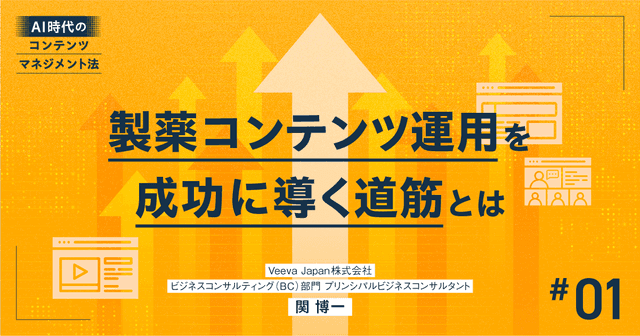
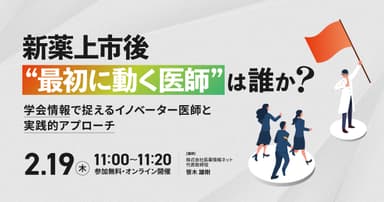





.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)


