製薬マーケターのためのペルソナ設計【発展編】UX時代に求められるペルソナの進化と状況ターゲティング
.jpg&w=1920&q=100)
近年、ユーザーエクスペリエンス(UX)の重要性が高まる中、製薬業界においても患者や医療関係者のニーズを理解する取り組みが進んでいます。顧客理解を深めるためにペルソナが活用されていますが、その活用は属性情報にとどまってしまうことが少なくありません。
マーケティング施策の実効性を高めるには、ユーザーの「状況」に踏み込んだ理解が不可欠です。そこで本記事では、従来のペルソナ活用の課題を整理し、他業界でも成果を上げている「状況ターゲティング」の視点を取り入れる方法について解説します。
ペルソナ活用の限界とUXの視点
ペルソナは、特定のユーザー像を明確にするための有効な手法です。年齢、性別、職業、趣味などの属性情報を基に作成することで、チーム内で共通のユーザー像を持つことができ、マーケティングやUXデザインの指針となります。プロジェクト推進時、メンバーがユーザー像を思い起こす際に、ペルソナを想起することで、メンバー同士の目線合わせができることは大きなメリットです。
製薬業界でも多くの企業がペルソナを用いてターゲットとなる医師や患者を定義し、マーケティング戦略を立てています。しかし実際には、医師や患者の具体的な行動やニーズを反映しきれていないことが多いのではないでしょうか。
ペルソナの限界は、『具体的な行動を考慮しない』こと
従来のペルソナは、年齢・性別などの基本属性や、過去の行動データから導いた傾向などに基づいて作成されています。しかし、これらの情報から作られたペルソナはあくまで「どんな人か」という静的な人物像を描写するだけで、実際の行動や状況を精密に考慮したものではありません。これが、ペルソナを作成しても得られる結果が限定的である理由です。
対象となる属性が、「どのような行動を取るか」「何を感じ、どのような意思決定に至るのか」といった情報がないため、特定の状況下でのユーザーの反応や行動を予測することが難しいのです。
UX(ユーザーエクスペリエンス)の重要性を再確認する
デジタルサービスが普及する現代において、UXの質は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。
製薬業界においても、医師にとって利便性の高い情報提供のあり方や、あらゆる情報提供の場面での優れたUX追求がますます重要になっています。ユーザーのニーズを正確に理解し、それに応える体験を提供できるかどうかが、今後の事業成功を大きく左右するでしょう。
UXと状況ターゲティングによるペルソナの進化が求められる時代に
現在、他の業界では従来のペルソナの弱点を補う取り組みとして「状況ターゲティング」という新しいアプローチを取る企業が増えてきました。
UXとCX(カスタマーエクスペリエンス)を向上させるためには、ユーザーやカスタマーの具体的な状況を理解し、それに基づいた情報、財、サービスを提供する設計が求められます。
この仕組みを検討し実装した企業、例えばLIONやDeNAといった企業では、顧客の獲得やロイヤルカスタマー化に成功しているといった事例が多数見られます1)。これらの企業は、ペルソナを作成するだけでなく、実際の顧客がどのように意思決定をするのか、その背景にある感情や思考などにも踏み込んで顧客を理解したことで、ビジネスで結果を出したということです。
製薬業界においても、このアプローチにより効果的なマーケティング戦略を構築することが可能になると考えられます。
状況ターゲティングのメリットとは?
状況ターゲティングは、ユーザーの行動や意思決定を単なる属性情報ではなく、実際の生活環境や心理的状況に基づいて理解しようとする考え方です。これにより、ユーザーがどのような状況で製品やサービスを利用するのかを深く掘り下げることができます。その結果、ユーザーにとって最も利便性が高く、必要性を感じられるように情報提供することが可能になります。
状況ターゲティングによって得られるベネフィットとして、「具体的な状況の理解」と「行動の共通性」が挙げられます。
1. 具体的な状況の理解
ユーザーが直面する具体的な状況や課題を把握することで、UXデザインはよりユーザー中心になります。例えば、共働き家庭における料理の負担や、老夫婦の医療管理の難しさなど、特定の状況におけるユーザーのニーズを理解しやすくなります。
2. 行動の共通性
同じ状況に置かれたユーザーは、異なる背景を持っていても共通の行動パターンを示すことが多いです。これにより、特定の状況におけるユーザーの行動を予測しやすくなります。
ユーザー行動を理解するための新しいアプローチ
状況ターゲティングは、従来のペルソナ作成とは異なり、ユーザーの具体的な行動やニーズを重視します。
例えば、以下のような方法でユーザーの行動を理解することができます。
1. 行動観察
ユーザーが製品やサービスをどのように利用しているかを観察することで、実際の行動を把握します。これにより、ユーザーが直面するペインポイントを明確にすることができます。
2. 定性調査
インタビューやフォーカスグループを通じて、ユーザーの思考や感情を深く理解します。これにより、ユーザーがどのような状況で製品を利用するのか、またその背景にある心理を把握することができます。
ここで重要なことは、
- ユーザーがなぜその製品を利用するのか?
- なぜそのような意思決定をしたのか?
- その時何を実現したかったのか?
- その意思決定の結果、得られたベネフィットは何だったのか?
- そのベネフィットに満足しているか?
などを徹底して深掘りして、ユーザーが気づいていない深層心理や価値観にまで迫ることです。
3. データ分析
前述の1.と2. から得られたデータを分析することで、ユーザーの行動パターンを把握します。その上で、ユーザーはどのような状況でどのような行動をとるかを予測します。
このアプローチを実践することによって、製薬企業は医師や患者について従来以上に深いインサイトを得られ、そのインサイトによってペルソナを補強することができます。よりリアルな医師・患者像を作りやすくなり、そのペルソナや医師・患者の状況に応じた最適なメッセージングや情報提供の手段などを、精度高く検討しやすくなるでしょう。
【事例】老夫婦の生活における薬物療法
ここで、1つの事例をもとに考えてみたいと思います。例えば、年金生活を送る老夫婦が複数の慢性疾患を抱え、日々の薬を管理している状況を想像してみましょう。
薬物療法は健康維持に欠かせない要素ですが、実際には、その治療には以下のような多くの負担が伴います。年齢を重ねるにつれて慢性疾患や複数の病気を抱えることが一般的なため、薬の管理が大きな課題となります。
1. 経済的負担
年金収入は限られているため、医療費や薬代が家計に与える影響は大きい。特に、複数の薬を服用する場合、月々の医療費がかさむことが多く、経済的なストレスを感じることがある。
2. 服用スケジュールの管理
複数の薬を服用する場合、服用スケジュールの管理が難しくなる。特に、異なる時間帯に服用する必要がある薬がある場合、混乱が生じやすく、誤った服用のリスクも高まる。
3. 医療機関へのアクセス
高齢者にとって、医療機関へのアクセスは大きな課題。移動が困難な場合や、交通手段が限られている場合、定期的な診察や薬の受け取りが難しくなる。
想定されるペインポイント
これらを踏まえると、老夫婦の生活と薬物療法のペインポイントが浮き彫りになってきます。例えば、以下のようなペインポイントが想定されるかもしれません。
1. 服用スケジュールの複雑さ
複数の薬を服用する場合、それぞれの薬の服用時間や量を正確に把握する必要がある。医薬品の用法・用量上いたし方ないものの、患者にとってはこれがストレスとなり、時には服用を忘れてしまうこともある。
医師もこのようなケースを多数経験しており、1日の服薬タイミングを揃えたいというニーズはあるが、その医薬品の薬理上どうしてもそれが実現できないことも起こり得る。
2. 副作用への不安
薬の副作用についての情報が不足している場合、老夫婦は不安を感じることがある。特に、初めて服用する薬に対しては、どのような副作用があるのかを知りたい。
3. 医療情報の不足
医療機関での説明が不十分な場合、老夫婦は自分の病状や治療方針について理解できず、結果として適切な判断ができなくなることがある。このような状況によって、治療から患者が脱落するリスクが高まることが考えられる。
そのような事態を避けるべく医師は服薬指導を行うが、患者にとっては「わからないことを質問しにくい」といった悩みが起こり得る。
4. 家族のサポート不足
子供たちが独立している場合、薬の管理や医療機関への付き添いができないことが多く、老夫婦自身で全てを管理しなければならない状況が生まれる。このような事例は、大都市圏や地方を問わず考えられる。
ユーザー理解とマーケティングの新しいアプローチ
このような状況ターゲティングを通じて得られた具体的な状況理解は、UXデザインにおいて以下のような影響を与えます。
1. ユーザー中心のデザイン
ユーザーの具体的なニーズや行動に基づいたデザインが可能になり、より良い体験を提供できます。
2. マーケティング戦略の最適化
ユーザーの行動パターンを理解することで、マーケティング施策をより効果的に展開できます。特定の状況におけるユーザーの反応を予測し、適切なメッセージを届けることができます。
3. サービスの改善
ユーザーのペインポイントを明確にすることで、サービスの改善点を特定し、継続的な改善が可能になります。
このアプローチを先ほどの事例に応用してみましょう。
状況を理解することによって、製薬企業や医療機関は、老夫婦に対してより共感が得られやすいサービスを提供できるようになります。以下のような改善点が考えられます。
1. 服用管理アプリの提供
薬の服用スケジュールを管理するためのアプリを提供することで、老夫婦が自分の薬を簡単に管理できるようになる。リマインダー機能を搭載することで、服用を忘れるリスクを減少させることができる。
2. 副作用情報の提供
薬の副作用についての情報をわかりやすく提供することで、老夫婦の不安を軽減できる。特に、視覚的な情報(イラストや動画など)を用いることで、理解を深めることが可能。
3. 患者向けのサポートプログラム
Patient Support Program(PSP)に取り組む製薬企業は、状況ターゲティングに取り組むことによって、患者の治療への自発的な参画意欲の創出や疾患の理解の深化などが実現できる。患者の治療からの脱落防止や、医療機関への定期的な受診といった、患者の行動変容・思考変容に効果があると考えられる。
4. 家族向けのサポートプログラム
老夫婦の子供たちに向けたサポートプログラムを提供することで、家族が薬の管理や医療機関への付き添いを手助けできるようになる。これにより、老夫婦だけで抱えていた負担を軽減することが実現できるかもしれない。
5. 医療機関との連携強化
医療機関と連携し、老夫婦が必要な情報を簡単に得られるようにすることで、治療に対する理解を深めることができる。
定期的なフォローアップや相談窓口を設けることで、老夫婦が安心して治療を受けられる環境を整えることが重要。
このように、老夫婦の薬物療法における負担を適切に把握し、具体的なペインポイントを理解することで、企業や医療機関はより共感的なサービスを提供できるようになります。これがまさに状況ターゲティングです。
このアプローチで得られた患者のインサイトを、再度ペルソナのブラッシュアップに用いれば、従来以上に現実に即したペルソナを作成することができるようになります。ここまで検討を深めたペルソナならば、医師に対して自社医薬品のメッセージがより伝わりやすくなるでしょう。また、そのメッセージを理解した医師は、患者に対してより説得力のある治療や薬物療法の指導を実施でき、医師・患者の両者にとってメリットが生まれます。
このように、状況理解を基にした改善策を講じることで、患者が安心して治療を受けられる環境を整えることができ、ひいては生活の質を向上させることができるでしょう。
そしてこれこそが、医師が患者に対して提供したい価値の一つでもあります。
ペルソナを「作って終わり」にしないために
これまでのペルソナが「作って終わり」になってしまっていたなら、今後はペルソナを踏まえて医師や患者がどのように考え、どのように振る舞うのかまで踏み込んで理解することにチャレンジしてみましょう。その取り組みによって、医師や患者の意思決定を、最適な医療の提供・享受のための思考変容・行動変容を促せるようになります。これがペルソナを作って終わりにしないための、最も重要なポイントです。
<出典>
1)beBit, 支援事例, https://www.bebit.co.jp/services/


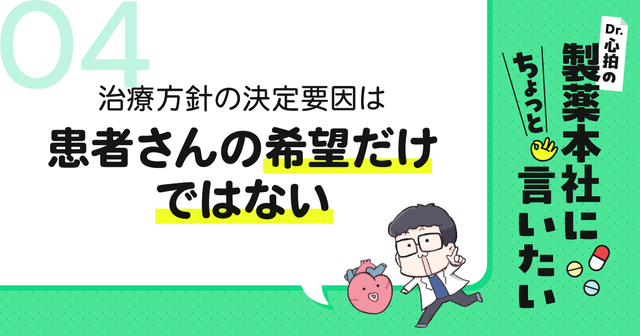

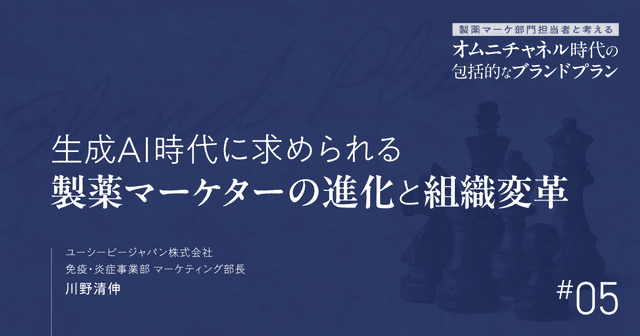
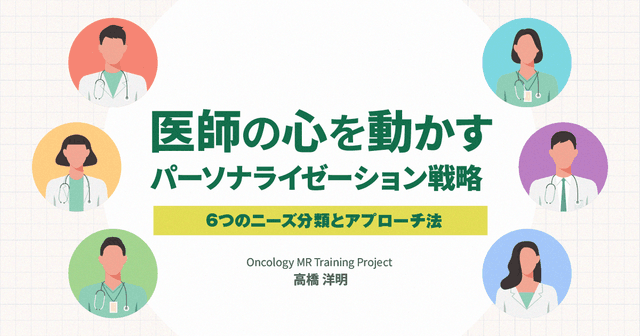
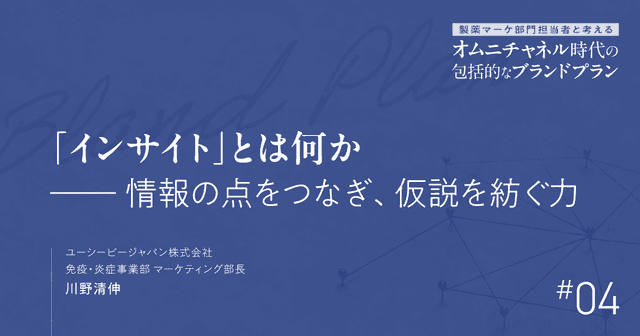


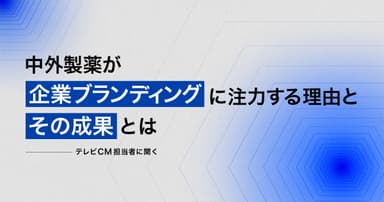



.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



