オフライン施策を戦略チャネルに。“可視化”と“個別化”の実践| MDMD2025 Summerレポート

2025年6月4日に開催された「Medinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summer」では、「製薬企業オフライン施策事例update:オムニチャネル戦略におけるオフラインの立ち位置とは」と題し、ラクスル株式会社 エンタープライズ事業統括部 アカウントエグゼクティブの太田百香氏が登壇。
オムニチャネル時代の今こそ活用が期待できる、製薬企業のマーケティング活動における紙DMの最新事例と可能性について、事例を交えて紹介しました。
オムニチャネル時代におけるオフライン施策の価値
医療関係者との接点が多様化・分散化する中で、製薬企業におけるオムニチャネル戦略の重要性が一層高まっています。オンライン・オフラインを問わず、複数のチャネルを統合的に活用しながら、医師やコメディカルの個別ニーズを汲み取り、最適なタイミングと手段で情報を届けるパーソナライズ施策が求められています。
太田氏は、「情報収集フェーズではインターネットを活用する医師が多い一方で、処方や薬剤採用といった意思決定フェーズでは、MRとの面談や電話など、人を介した接点が引き続き重視されている」と述べ、医師の行動フェーズに応じた適切なチャネル設計の必要性を指摘しました。
デジタルチャネルの限界と届かない層の存在
多くの製薬企業では、3rdPartyメディアやオウンドメディア、メールマガジンなどを活用したデジタル施策に取り組んでいます。しかし、太田氏によれば、「複数のチャネルに予算を投下しても、反応するのは同じ医師に限られている」といった声が現場から上がっているといいます。
とくに地方の基幹病院の医師やデジタルに不慣れな医師、あるいはそもそもオプトインを取得できない医師に対しては、どれほどデジタル上でコンテンツを整備してもリーチが難しいのが現状です。また、MRへのレコメンドが現場で活用されにくいといった乖離も課題として挙げられました。
オムニチャネル時代の今、こうした「デジタルでは届かない層」に対して、オフライン施策は代替チャネルとして機能するだけでなく、新たな接点創出の手段となりえる存在といえます。そのため、「郵送DMを実施する製薬企業は増えている」と、太田氏は説明しました。
紙DMが効く理由とは?定量・定性で見る効果
ラクスルが製薬企業とともに取り組んだ紙DM施策では、開封率70%、新薬案内におけるCV率5%といった成果が報告されています。薬剤師に向けたDMでも3.5%のアクセス率が見られるなど、外部メールマガジンと同等かそれ以上の効果が確認されています。
また、紙媒体ならではの「保持性」の高さも特徴の一つです。送付から2〜3週間後の講演会にあわせてアクセスが集中した事例が示すように、紙DMはすぐに廃棄されず、必要なときに再読される可能性があります。加えて、視認性や記憶定着にも優れており、訪問した際に「あのはがきの案内ですね」と話題にのぼることもあります。
オフライン施策の導入が進まない理由とその解決策
一方で、オフライン施策の最大の課題として「効果が見えづらい」という点が挙げられます。デジタル施策においては、KPIやROIを明確に設計したうえで、目標から逆算してセグメントを絞るなどして施策を決め、PDCAを回す体制が一般化しています。しかし、オフライン施策にはそうした仕組みが整っておらず、結果としてブラックボックス化してしまいがちです。
個別QRコードでログを取得・連携を叶える
こうした課題に対し、ラクスルでは郵送DMに個別のQRコードを付与し、読み取りログを取得する仕組みを提供しています。これにより「どの施設の、どの医師が、どのコンテンツに、いつアクセスしたか」といった行動データを可視化できます。
さらにこのログは、CRMやSFAと連携することでMRへのリアルタイム通知にも活用できます。そのため、例えばオウンドメディアに未ログインの医師であっても、「はがきから講演会ページにアクセスした」「このコンテンツも閲覧した」などの情報がMRに共有され、確度の高いフォローアップが可能となります。
コンテンツとターゲティングの最適化
太田氏は、「オフラインでもPDCAを設計することが重要」と述べ、オフラインチャネルのあるべき姿(下図)を示しました。
ラクスルは、DMの文面や同封するパンフレットの内容を、ターゲットの処方履歴や所属などに応じて出し分けるサービス「パーソナライズDM」も用意。
これは、デジタルのMAやレコメンド機能に近い発想で、オフラインでもターゲットの個別ニーズに応じた「届け方」の最適化を可能にしています。例えば、「処方採用したことのある医師」「一度も処方採用したことのない医師」でDMを出しわけることなどが可能です。
紙DMを「ただ送るだけ」にとどめず、あらかじめ設計された仮説と検証、そして投資判断につながる評価指標までを組み込むことで、再現性のある運用が可能になります。
実例で読み解く、オフライン施策の手応え
太田氏は講演で、ラクスルが支援してきた具体的な施策事例を3つ紹介。
いずれもデジタルチャネルでの接点獲得が難しいケースにおいて、紙DMの活用によって突破口を生み出したものです。対象や目的は異なりますが、それぞれの事例からは、オフライン施策がマーケティング活動のなかでどのように機能し得るかが具体的に見えてきます。
事例1:新薬承認直後の迅速展開と即時CV
新薬承認後、MRによるアプローチ優先度が低い医師や検査部・薬剤部に対し、パーソナライズされたDMを5,000通送付。QRコード読み取りの即時通知により5%以上の反応を得るとともに、MRによる迅速なフォローアップにつなげました。
事例2:50年超製品でも情報提供の継続に成功
MRが配置されていない長期販売製品に対して、圧着はがきを用いた情報提供を実施。限られた予算の中で、薬剤部・薬局1万件超に対し情報を届け、0.5%の読み取り率を記録した事例です。発送3週間後も資料請求の問い合わせがあるなど、次のアプローチへとつながるきっかけを生み出せました。
事例3:MRもデジタルも届かない層へのナーチャリング
オウンドサイト未登録・面談未実施の医師に対して、定期的なDM送付を実施した事例です。
まずは登録不要の製品情報など複数のコンテンツを案内し、QRコードの読み取りログを取得してCRMと連携しました。どういうコンテンツに反応しているのかを分析し、MRもデジタルチャネルも介さずに情報提供を継続する仕組みを設計。反応が見られた医師には、段階的に追加情報を届けることでナーチャリングを図り、結果として1〜2%の医師がオウンドサイト登録へと進んでいます。
オフラインチャネルでも「可視化」と「パーソナライズ」が重要
講演の最後に太田氏は、「オフラインチャネルにおいても、個別化された情報提供のニーズを把握し、それに対応していくことが重要」と強調しました。医師との接点が分散する今、オフライン施策もまた一斉配信から脱却し、データに基づいて反応を可視化し、属性や行動に応じてパーソナライズする段階へと移行しつつあります。
こうした姿勢は、オフライン施策を単なる補完チャネルではなく、デジタルと同様に設計・検証・改善を重ねる「戦略チャネル」へと引き上げるものです。今後のオムニチャネル施策において、オフラインの再定義と高度化は、ますます欠かせないテーマとなっていくでしょう。
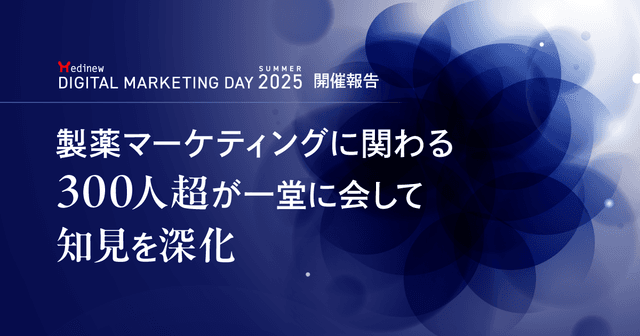
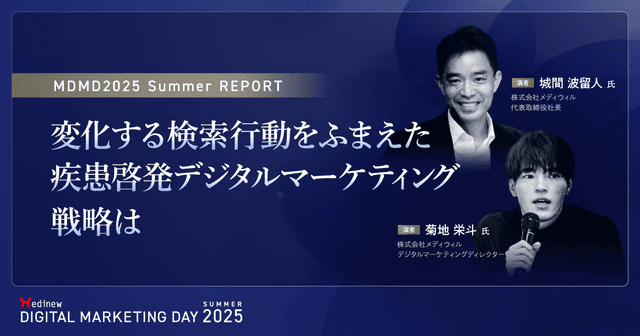
.png&w=640&q=75)

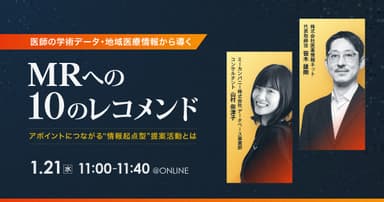





.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)


